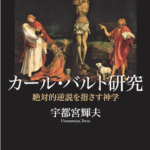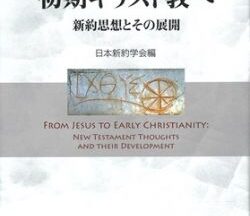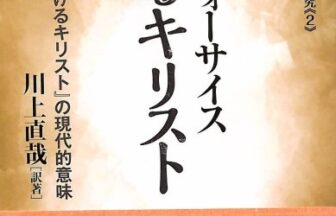共に賛美をささげるために
〈評者〉中山信児

本書には、三つの講演とパネルディスカッション、三つの実践レポートが収められている。
水野隆一氏による主題講演は、教会の音楽における「分断」について幾つかの視点から論じつつ、それらを相対化し、乗り越えようという試みである。その糸口としてポール・バズデンによる礼拝についての類型を手がかりにしながら、リタージカル・スタイルの礼拝の包容力と可能性に注目する。他方、コンテンポラリーな礼拝・音楽については、その存在意義を認め、一定の評価を与えながらも、批判的検討の対象と見ており、この姿は本書の各論に共通している。次いで、宣教との関連で、これまで歌われることの少なかった幾つかの課題が挙げられ、実例として著者による訳詞と作詞が収められている。このような課題の設定においても分断は生じうるが、礼拝や音楽の分野でも、多様性を認め合うことで分断の固定化を回避することが大切になるだろう。
招待講演において、荒瀬牧彦氏は「われわれはなぜ歌うのか」という問いについて、アウグスティヌスやルターの古典的理解から現代の見解までを一瞥した後、「天地に音楽が満ちているから」「共にするため」「震わせるため」「染み込ませるため」という四つの答えを挙げている。これらの答えには、牧師・賛美歌作詞者である著者の感性と問題意識がよく表れている。次いで、礼拝に仕える歌である賛美歌について考察がなされる。実際のところ、礼拝や賛美は、信仰者にとってあまりに身近な行為であるため、実践についてのノウハウは蓄積されても、神学的考察の対象とはなり難いところがある。一例を挙げれば「教区、教会の歩みにも着目し」て編まれた『日本基督教団史資料集』(日本キリスト教団出版局/一九九七│二〇〇一)中に、礼拝や賛美に関わる史料はほとんど収められていない。この点に限れば『植村正久と其の時代』(教文館/一九三七〜一九三八)より後退していると言わざるを得ない。近年、関連学会の設立、海外研究の紹介、各種讃美歌集の発行などの取り組みもなされているが、日本の教会の現場を見ると状況はさほど改善していないと思われる。本書にある様々な提言や招きが広く受けとめられ、賛美について考え、取り組む人たちの裾野が広がることを期待したい。
中道基夫氏による神学講演では「宣教における音楽」が正面から扱われている。まず日本のプロテスタント宣教史における賛美歌について概観し、現代の状況について触れつつ、そこからインカルチュレーション(「文化受容」「文化的受肉」)について考察している。音楽は、諸文化の影響を被りやすいだけでなく、良くも悪くも既存の文化を変容させる力を持っている。この点、日本の教会は十分自覚的であるとは言えず、本講演には傾聴すべき点が多々ある。
最後に「教会の音楽・若者の音楽」について論じられるが、その際、先行する時代や世代への「反発」が、新しいアイデンティティー形成の重要な契機とされている。しかし、文化的営みにおいて反発と受容は相容れないものではない。教会においても、多様な現実や異なる文化と真摯に向き合い、それらを自己変革とアイデンティティー確立の契機とすることが求められているのではないだろうか。

中山信児
なかやま・しんじ=一般社団法人福音讃美歌協会理事長
Warning: Undefined variable $post_types in /home/hiram2/honhiro.com/public_html/wp-content/plugins/molongui-authorship/includes/author.php on line 1447
Warning: Undefined variable $post_types in /home/hiram2/honhiro.com/public_html/wp-content/plugins/molongui-authorship/includes/author.php on line 1486