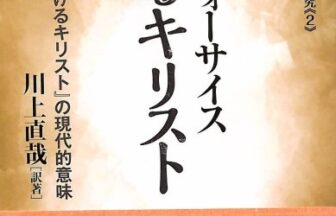信仰と知の関係を現代において改めて問う─宗教を哲学するということ
〈評者〉嶺岸佑亮
本書は、近代ドイツの哲学者であるヘーゲルの宗教哲学を、ヘーゲル哲学全体の中心部分をなすものとして初期から晩年の諸テクストに即して論じるとともに、現代におけるキリスト教信仰に対していかなる意義を有しうるかを示そうとした意欲作である。従来、ヘーゲルは内外で広く研究されてきたが、不思議なことに、宗教哲学に関するものは驚くほど少ない。ましてや、キリスト者の立場から正面切ってヘーゲルのキリスト教理解を解釈したものはほとんどないといってよい。その意味でも、本書の価値は大きいものといえる。
本書の第一章では、ヘーゲルの時間様相論が論じられるが、『大論理学』「本質論」の「現実性」を解釈して、「あらゆる出来事の時間的本質」としての「絶対的現実性」(三三頁)であるとする理解は、本書の基調をなすものである。そのことについては、ベルリン期の『神の存在証明講義』を扱った本書の第二章で、「永遠なる神の本質とはこの現実性(今ここ)のさなかにあるということである」(九〇頁)とする主張からも明瞭に見て取れる。
ヘーゲルによれば、無限なものとしての神に対し、人間は有限なものと特徴付けられるが、本書ではさらに、人間の根本特徴として偶然性が挙げられている。この世界に生きる人間は、どのように生きるにせよ、何を行うにせよ、そのあり方が限られているがゆえに壁にぶち当たる。それゆえに、人間は様々な苦しみを味わうことになる。だがそうであっても、「「あるがゆえにある」という絶対的な現実性」としての「現実性としての永遠」(一一二頁)へと開かれている。神の存在証明の確信とは、人間が自らの思考によって無限な神へと高揚することである。そのような高揚において、人間は神を精神として知るとともに、自らを精神として知る。このような事態は、「人間が神の精神を知るということは、精神に媒介として神自身を知ることである」(一一〇頁)と本書が述べるように、真実には、神自身の主体性に基づくプロセスのもとにとらえ返される。精神を軸にした、人間と神の間でのこうした関係を相互承認の観点から論じる本書の叙述は極めて示唆的である。
本書の解釈の背景には、「私はあるという者だ」という「出エジプト記」3・14についての著者の理解があるといえよう。そのことはとりもなおさず、「この純粋な現実性において自己が神に全肯定されている」(一〇一頁)とする主張にも表れており、ここに著者のカトリック信仰の反映を認めるのは困難ではなかろう。ヘーゲルは『精神現象学』で歴史性のモチーフを強調するが、本書のこうした論述が自己意識の歴史という、ヘーゲルの思想をどう発展的に解釈しうるか、ということは問う価値があろう。
本書のもう一つの特筆すべき点として、『精神現象学』における「不幸な意識」の解釈が挙げられる。「不幸な意識」がキリスト教の成立時期を念頭に置いて書かれたものであることは広く認められているが、同書の「啓示宗教」も踏まえた包括的な考察は驚くほど少ない。人間は生きている限り、それぞれに自らの十字架を担っていく。自らの不幸なありようにどのように向き合うべきなのか、まさにこの点において、本書は現代の読者に向かって語り掛けようとしている。