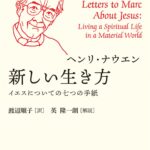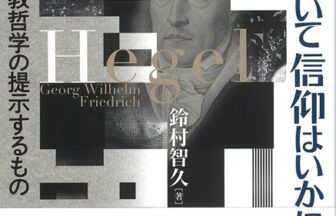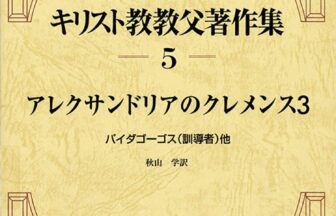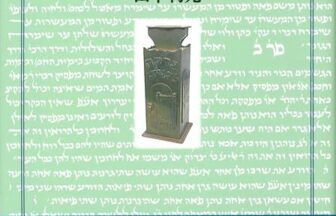戦争体験を証言する者と聞く側、読む側の相互作用
〈評者〉伊藤朝日太郎
先の戦後80年の節目に私の所属教会で教会員の戦争体験を聞く集いが開かれた。所用のため参加できず残念に思ったが、のちにその体験談が教会報に載り、貴重な証言を読めてほっとした。これはこの本の読後感でもある。
「今、思えば、あの惨状の中で一刻も早く逃げたいばかりに、悲惨な現状を見ても、その場を横目で見ながら立ち去ったことが残念でたまりません。どんなときであっても戦争だけはしてはいけないと思いました。… …原爆の体験は言いたくない、語りたくないと常に思っていましたが、一人でも多くの人が語り続けることによって、戦争を知らない子どもたちのために、また二度と戦争を起こさないために… …」(42ページ)とあるように、悲惨な経験をした方ほど語ることができない。本書の証言者は、教会の中で証言を求められることによって、あるいは『信徒の友』から執筆依頼や取材を受けることによって、重い口を開き、あるいは筆を執ってくださった。そのことが、戦争の美化や、歴史修正主義を克服することにもつながる。
本書で印象的なのは、聞き手との相互作用が働く3本のインタビュー記事だ。聞き手は戦争経験者の孫世代、私と概ね同世代だ。広島で被爆した牧師、沖縄戦で数名の日本兵から「子どもたちを殺すか、さもなくば、ここから出て行け!」と壕から追い出されて戦火の中で親きょうだいを失った司祭、満洲から引き揚げてきた教会員のお話を、その方にゆかりのある牧師や教会員が聞き、自らの課題として引き受け、変容していく姿が読める。いつも静かに教会の席に座っているあの方が、あるいはいつも元気に平和運動に邁進しているあの方が、こんな記憶を抱えていたのか、という聞き手の衝撃、発見、決意が伝わってくる。
私は以前から、教会は平和のために祈っているだけではだめだ、一歩でも歩みを起こさなければ、と歯がゆく思ってきた。しかし同時に、教会だからこそできることがあるのではないかとモヤモヤしていた。そのモヤモヤを解くヒントが随所に盛られているのも本書の特徴だと思う。
「人間はみな平等だ」という教えのもと、日本軍の傀儡政権下の満洲で、中国の青年のための無料夜学塾を開き、中国人の真の友が与えられた三田照子さん(106ページ)、「平和を祈る私たちには、神と人、人と人との間にゆるしが必要なのだと思っています。私たちの間に『ゆるす』との声が聞かれないうちは、この世の真の平和は来ないのだと感じています。全国の教会が礼拝前の10分間、平和のために悔い改め、ゆるし合えるよう祈ることを願います」と語る清水幸子さん(121ページ)の言葉には、教会が伝えてきた最良のエッセンスが感じられる。
また、「長崎の平和運動は教会間、信徒同士の柔軟な横のつながりや市民団体と共に歩む中で進められてきました」(63ページ)との言葉からは、教会やYWCAというキリスト教の伝統を受け継ぐグループが市民運動を支えてきた歴史が浮かび上がってきた。
戦後80年の今、多くの教会やキリスト教主義学校で、また家庭で、「私たちにゆかりのある人の言葉」としてこの本の多様な証言が読まれ、歩みが起こされることを願ってやまない。