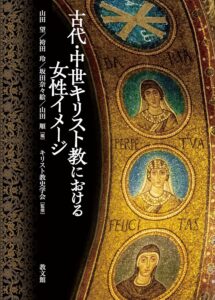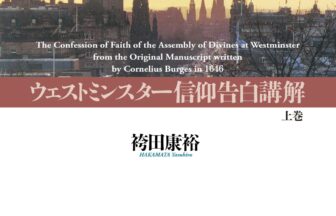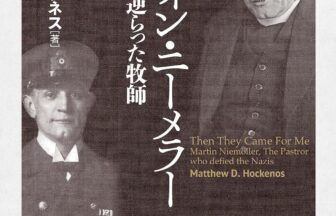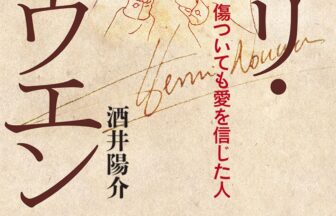女性たちはどのように生き、どのような活動をしていたのか
〈評者〉小松加代子
古代ローマから一三、一四世紀までという長い時間軸の中で、しかも壁画、図像学史料、文献資料など幅広い史料研究を解読しながら、その中に女性の生きた跡を探るという、地道ながら壮大な意図を持った研究書である。評者はキリスト教史学の専門家ではないため、ジェンダーの視点から、古代・中世の女性たちがキリスト教社会の中でどのように生きていたのかを本書から抜き出してみたい。
まず、四世紀後半から五世紀初めにかけてローマ市を中心に活動したペラギウス派による書簡群から、貧者や孤児の救済に関わる女性たちがいたことがうかがえる(第三章)。キリスト教徒ではなかったが、四世紀後半に哲学や天文学、数学の研究で歴史上名高いヒュパティアが生まれ、宗教間の対立を超えた教育活動を行っていたことが知られている(第二章)。また、五世紀のビザンツ皇妃エウドキア作とされる『ホメロス風聖書物語』では、従順なだけではない自主性ある聖母マリアが描かれ、女性から女性に向けられた励ましのメッセージが見られる(第五章)。四五世紀に書かれたアウグスティヌスの女性信者たちに宛てた書簡からは、禁欲的結婚生活に入る誓約のもとにある既婚女性、修道的生活に関心のある篤信の寡婦、独身女性がいたことが浮かび上がる(第四章)。さらに一二、一三世紀には修道院に属さずとも弱者の救貧活動に勤しんだベギンと呼ばれる女性たちが「敬虔な女性たち」と称されていたことが分かる(第九章)。
しかし、ペラギウス派の教義はのちに異端と断罪され、ヒュパティアは暴徒化したキリスト教徒集団に殺害され、ホメロス風聖書物語で語られた聖母の行動はその後の正典聖書には見ることができない。またベギン運動は一四世紀には異端とされる。アウグスティヌスは既婚女性たちに対して、夫の同意のもとにともに禁欲生活に入るよう諫めている。こうして、かすかに見えた女性たちの行動も、やがてキリスト教社会の中心から外される運命となっていく。
それではキリスト教会の中で生き残っていった女性のイメージはというと、その多くは結婚と処女という言葉とともにある。大聖堂の建立にあたって、献堂式が結婚イメージと結び付けられ、花婿であるキリストに捧げられる教会は花嫁で、唯一の神への愛を示し、神への忠誠は義務とされる(第六章)。ビザンツ帝国末期の正教を代表する思想家グレゴリオス・パラマスは、マリアは処女性を自らの意志で守ったことによって、自身も女主人として万物を治める権威を持つ、と考えた(第七章)。このような女性イメージを記述しているのは、ほとんどが男性である。第二章の出村氏が最後でまとめているように、史料に記された女性イメージは、「実在した個々の女性を離れて、実際には男性著述家によってそれぞれの論争的文脈の中で意図的に形成され、発展したイメージでもある」(七四頁)こと、また第九章の後藤氏が指摘するように「正統の代弁者として期待・利用された」(二四四頁)ことも明かされている。
あえて原典史料を精緻に読みこなし、状況証拠を丹念に積み上げることで抽出した女性イメージは、さらなる歴史解釈を求めており、その意味ではフェミニスト神学とつながることによって別の視点がみえてくるのではないかと思われる。