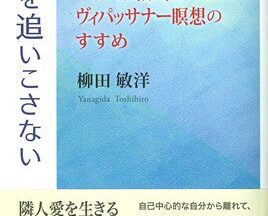学的に裏付けられた福音書テクスト研究から見えてくる原始キリスト教の風景
〈評者〉新免 貢
イエスはモノを書かなかった。われわれはイエスを直接知らない。イエスについて伝えられていることを知っているにすぎない。そういう意味においては、口伝、物語資料、言葉資料(Q)など様々な資料を駆使した正典福音書の著者たちのイエス像も、「昔のイエスはこう言った」と思いこみたい現代読者のイエス像も受け売りであり、セコハンの限界を免れない。しかも、書き記された仕方で残存するイエスの種々の言葉は、M・ディベリウスなどがすでに気付いていたように、そもそも起源ははっきりしない。それゆえ、「福音書の難所」は、本書で検討されている諸箇所に限らないであろう。
一─二章では、Q資料中の「神の国」発言(ルカ一七章21節)─「神の国は『あなたがたの内面に(エントス・ヒューモーン)』」(グノーシス主義文書トマス福音書三、一一三も参照)─、並びに、「禿鷲」発言(同一七章37節)─「体のあるところはどこでも、そこには禿鷲たちも集まるだろう」─が、「大旅行記」の一部をなす囲い込み記事(一七章20─37節)の前後関係を考慮に入れ、マタイ二四章23節以下の文脈とも比較しながら分析される。その結果、前者はファリサイ派の偽善的な内面に対する皮肉として、及び、後者は「人の子」来臨の宇宙大の可視的出来事に関する弟子たちへの教示として、ルカの編集作業に帰せられる。
また、イエスの「禿鷲」発言の類似例がアラム語ユダヤ社会に共有されていたプルタルコス『倫理論集』(九一八C)やルクレティウス『事物の本性について』(Ⅳ六七九─六八〇)の博物学的知識に裏付けられた格言に見出され、伝承史的に関連付けられる。こうして、「神の国ネットワーク」と著者自身が名づけるイエスの思想的原風景の中に加えられる。さらに、後代に影響を及ぼし続けたルカの歴史神学の構想─「人の子」到来までの「日々(ヘーメライ)」において様々な出来事が起こる─が、最後の審判に伴う災難の数々が襲う薄気味悪さを漂わせたマタイの対応箇所(二四章28節)とも比較しつつ説明される。これに加えて、ステファノ殉教事件をイエスの神殿倒壊予言の再活性化の結果とするルカの筆遣いが中途半端に終わったと著者は指摘する。私見によれば、ルカ文書よりも後代の非正典伝承(ペトロ福音書七章26節)がここで補足されるべきであろう。というのは、弟子集団は神殿放火未遂の責任を帰せられ、身を隠し、怯えていた。「人の子」再臨のアクチュアリティは著作家ルカにとっては失われたものであっても、身の危険を現実に感じる生身の弟子集団の間ではイエスの鮮明な神殿破壊予言のアクチュアリティは失われていなかったことが窺えるからである。
続く第三章は、タルグム訳との関連を多くの学者たちによって指摘されてきた「メーポテ」(マルコ四章12節)の使用例を広範に取り上げ、これを接続詞ではなく、「~かもしれない」という肯定的可能性を表す副詞と解する。
本書全体の約四割も占める第四章は、「ナゾーライオス」(マタイ二23節)、「ナザレーノス」(マルコ一章24節)、「ノーツリー・イエス」─バビロニア・タルムードはイエスを貶める対抗物語を提示─、「ナーツォライヤー」(マンダ教徒の自己呼称)をめぐるユダヤ主義キリスト教の系譜を素描する。こういう掘り起こし的作業は、ユダヤ教周縁の「遵守派」の把握、並びに、それと関係するイエス後のキリスト教の諸源流の宗教史的解明に接続する重要な試みでもある。イエスゆかりの「ナザレ」という土地名は、旧約聖書アラム語訳にもタルムードにも言及例はなく、そこには一筋縄では行かない複雑なテクスト問題が絡んでいることを本章は明かにしている。
聖餐式の原理的あり方─「キリストの肉を食べ、血を飲む」ことによって他者の苦しみに一体となって共感できる人間への変容─をヨハネ六章51b─58節に見出す第五章は、シモーヌ・ヴェイユの犠牲観念にも言及し、社会下層を食い物にする人間のあり方を問題にする。
付録二編は、今の立ち位置にたどり着いた著者自身が学恩を受けた荒井献氏と佐竹明氏に対する学術的追悼文である。著者は両氏の衣鉢を受け継ぐにふさわしい学者である。
最後に、先行研究としての欧米文献や邦語文献、及び、ギリシア・ローマの著作家たち(アリストテレス、セネカ、大プリニウスなど)の作品群、七十人訳、ユダヤ教文書(死海文書、フィロン、ヨセフス、ラビ文献など)、ナグ・ハマディ文書、マンダ教文書(ハラン・ガワイタ、ギンザー・ラバー)などからの関連原典資料の引用と分析は、本書を厳密な史料批判と文献批判の良き研究モデルの水準に引き上げている。本書は、後世に残る基本研究として、聖書学を志す若き学徒や関心ある他分野の専門家諸氏に読まれ続けること請け合いである。率直に言えば、本書の詳細な分析を読みこなすためには、ギリシア語・ラテン語・ヘブライ語などに関する基礎的素養が求められる。それが本書の「難所」でもあろう。しかし何にもまして、「イエスは何を考えていたのかを実際に知りたい」という強い動機と情熱が読者側に求められる。
世界水準の聖書学的知見に裏付けられた本書の各論考は、大学院ゼミ、教区・教会単位の信徒研修会もしくは牧師有志の継続学習会などの共同の場において、難所だらけの福音書テクストを再発見し、巻末索引を有効活用しながら忍耐強く学び直すための必読学術文献としての使用に十分に耐え得るであろう。