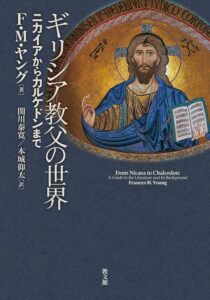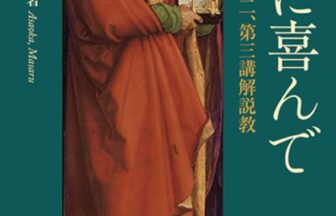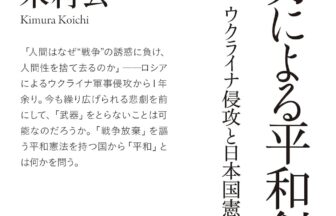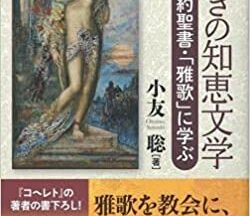教父たちの思想と信仰を伝える良質な入門書
〈評者〉土井健司
キリスト者は聖書という文書を読み、同信の交わりを深め、そして祈りのうちに呼びかけ、感謝し、さまざまな思いをもって求めつつ日々を歩む。それは古代でも同様であって、「教父」と呼ばれる人びとは、誰にもまして聖書を読み、人びとと交わり、さらに祈る人であったといえる。この点を理解しないと「教父」などはただの過去の人になってしまう。今日の教父研究は、教理よりも、むしろこうした人びとの生き様とその生きた思想を明らかにする必要がある。資料は乏しくとも研究の蓄積は数百年にわたっており、今なお更新中である。ここに翻訳されたフランシス・ヤングの本は激動の四世紀から五世紀に生きたギリシア教父たちの歩みを学問的にしっかりした仕方で、かつ躍動感をもって概観している。
著者のヤングは現在バーミンガム大学の名誉教授であって、新約学と古代教会史を専門とする英国を代表する教父研究者である。またメソジスト教会の牧師としても働いてきた。発達障害を抱えたお子さんについての著書もあり、決して研究室に閉じこもるだけの研究者ではない。今日教父研究は専門化し、同時代を扱っていても対象とする教父が異なれば研究状況が見えなくなるところ、この本は基礎的で信頼できる情報を提供してくれる。
教会史の父エウセビオスからはじまり、エウセビオスに続く教会史家が扱われる。エウセビオスは三世紀から四世紀をまたぐ教父であり、ニカイア公会議に出席したが、その教会史はコンスタンティヌス帝のところまでとなる。後継作はソクラテス、ソゾメノス、テオドレトスなどが著している(第一章)。そしてニカイアの立役者アタナシオスへと進み(第二章)、第三章は「信仰の英雄たち」と題して修道に専念した砂漠の師父たちの著作が扱われる。ここでアントニオスの後継者マカリオスも扱うが、偽マカリオス文書を含めて論じられるので、「祈祷派」と称されるマッシリウス派や聖書、聖霊の問題も詳論される。また「マカリオスがジョン・ウェスレーと同じ多くのテキストを用いていることは驚きである」と注記され(注295)、メソジストの背景をもつ著者ならではの視点も散見される。ここで砂漠の修道士たちを論じるところは本書の特徴であって、教父というと、そもそもは教理上の関心から論じられることが多く見られたが、ここでは信仰に生きた人びとが詳述されているのである。
第四章ではカッパドキア教父を論じ、第五章は「時代の特質──四世紀後半の対照的な人々」と題してシリアのエフライム、エルサレムのキュリロス、エピファニオスやヨアンネス・クリュソストモス、エメサのネメシオス、キュレネのシュネシオスを取り上げる。最後第六章ではキリスト論論争に関わるアポリナリオス、ネストリオス、アレクサンドリアのキュリロス等が扱われる。
本書ではラテン教父が取り上げられていないのでレオ一世やアウグスティヌスなどは登場しない。それでも全体で七〇〇頁超となっていて、激動の時代を生きたギリシア教父たちについて申し分のない叙述が展開されている。翻訳のための多大のご苦労に頭を下げつつ、本書を通して日本においてもこの時代を生きた人びとへの理解が深まることを期待したい。