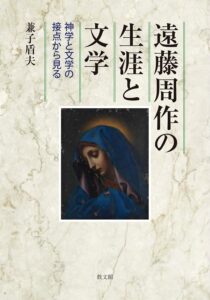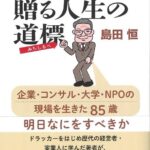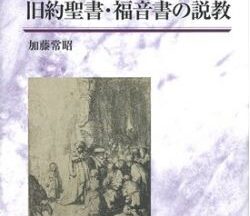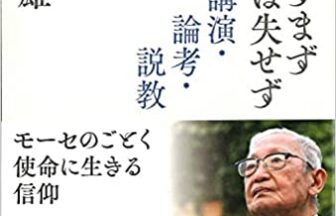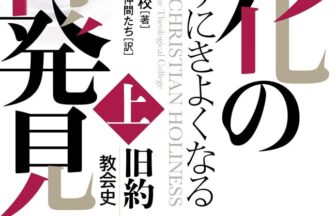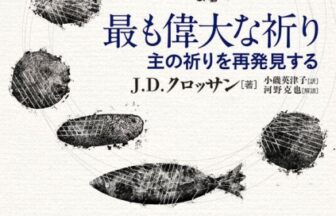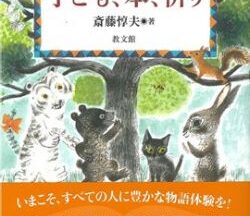象徴と隠喩から読み解く遠藤作品のメッセージ
〈評者〉奥野政元
兼子氏にはすでに二冊の遠藤論(『遠藤周作の世界──シンボルとメタファー』(二〇〇七年、教文館)と『遠藤周作による象徴と隠喩と否定の道──対比文学の方法』(二〇一八年、キリスト新聞社))がある。この度それらを統合集大成してまとめ、博士学位論文として新たに刊行されたのが本書である。
氏の遠藤論の特色は、遠藤の作品に見られる象徴や隠喩の意味を詳しく解きほぐして、作家固有のテーマに迫るところにある。この手法は文学研究者から評論活動を経て作家となった遠藤の特色によくかなったもので、つまり文学を対象として論理的に説明する際の手法や手続きが、自らの作品創造でも実行されているところにある。たとえば作品題名の付け方にもそれは窺えるもので、「白い人」「黄色い人」「海と毒薬」など、テーマが明確でその創作意図もメッセージとして単純明解に伝わってくる。
しかし、ことキリスト教のメッセージの単純明解さが、人間の罪と神の赦しといった究極の場に及ぶと、神の赦しを感じ認める場合でも、また逆にそれを認めずに拒否する場合でも、共に人間の傲慢さは現れてくるものである。この点に最も重大でしかも繊細な注目を寄せ続けるのが、作家遠藤の特色でもあって、それは『沈黙』のキチジローの形象や、無力な神のリアリティを描くところによく示されている。兼子氏は、こうした遠藤の手法を「否定の道」としても捉え、神を正面からは直視することはもはやできない現代においては、作家が聖なる存在にリアリティを与えるには、ガストンやミツのように、一見愚鈍なお人好しの道化として以外には、表現し得ないと指摘する。
作品『沈黙』こそは、こうした特色が十分に発揮されたもので、また西欧キリスト教と日本人の感性という空間的水平軸と、ヨーロッパ中世とポスト・モダンの現代日本という時間的垂直軸とが交差する十字路に、引き裂かれるように立ち尽くす作家遠藤が、主人公ロドリゴに日本人職人の手になるすり減った憂い顔のキリストを見せて、そこから「踏むがいい」と沈黙を破って語りかけたキリストを描くことによって、「王たるキリスト」ではない「共に苦しむ神」を創造し、そのことによって「西欧キリスト像のもつ距離感を克服した」(二六八頁)作品なのだと、兼子氏は説得力を持って言う。また本書後半では、神学との関係についてカトリックの「婚姻神秘主義」にも及び、「愛の置き換え」の手法を『侍』や『深い河』にも見ようとしているが、西欧キリスト教の根底にある異性愛と宗教的愛の激しさの相似形に触れる感性が、日本人遠藤には共感しがたいものがあって、その置き換えはモーリアックや二人のグリーンが試みた「愛の置き換え」とは異質なものとなっていると指摘する。たとえば『侍』では「地上の王」ではない「王の王」に心の内で会うことができたが、それは「淡々と運命に従って歩んだ」結果であり、そこにかえって「しみじみとした語りくち」が産み出されたと言い、『深い河』の美津子も自分以外のだれも愛してはいなかったが、最後には「自己無化」に目覚めたと読み解くところ(二八二頁)など、兼子氏の深い洞察に満ちている。