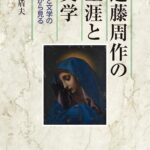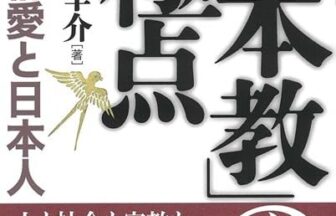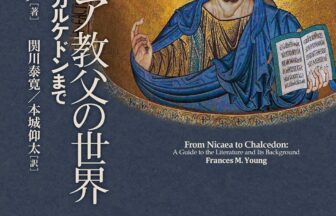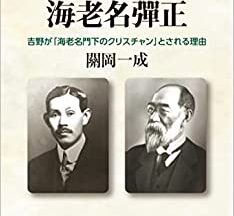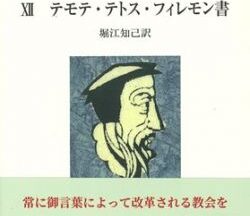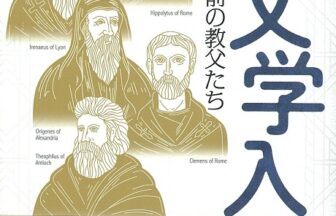「イエス時代のユダヤ人の言語」を論じる、研究者たちの多種多様の言語観
〈評者〉小河 陽
「イエスの言語」を巡る議論は、一九世紀末に至ってG・ダルマンの包括的な論点整理と方法論を経て、R・ブースの言う「唯一アラム語説」としてほぼ結実した。しかし、イエス自身の言語の問いや関心は古代には見られず、ルネサンス後人文主義の時代に入ってからのことで、それ以前はより広範に、パレスティナにおけるユダヤ人の言語を巡る議論であった。このテーマを巡る実に多種多様な所説が、入念に、そして手際よく時系列に纏められた本書の出版は、重要な問題のわりに類書が余り見当らないだけに、大いに歓迎したい。
本書は同志社大学神学研究科に提出された博士論文に加筆修正がなされたもので、膨大な文献の中から重要性に鑑みて選択された議論が論争史として簡潔に辿られており、その論述は賞賛に値する。
著者はイエスの言語を巡る議論の「噛み合わなさ」に着目し、それは「言語の呼称」でもって意味されているものについて研究者の間に見られるずれに由来するのだと喝破し、各時代の研究者らの言語観を詳述してゆく。
本論は二部構成からなり、第一部において「ヘブライ語」「アラム語」「シリア語」の呼称の発祥とその背景が調査・研究されている。そして第二部においては「ユダヤ人の言語」について、時代と研究者の間の言語観の違いが丹念に記述されてゆく。
その豊富な内容を簡潔に紹介することは到底できず、関心ある読者が是非自ら味わって欲しいと思う。実に多様な言語観が見事なまでに歴史的に描き出され、著者が着眼した研究者間の言語観のずれは綿密な調査を通して十分説得的に論証されている。ただ、惜しむらくはそこに重点が置かれて、各々の言語観がどのような資料と証拠に基づいて形成されたものであるかまでは殆ど論じられていないこと、そして探求が一九世紀末で終わっていることである。それゆえその適確性についての判断基準はそこから示唆されず、また二〇世紀に入って重要資料の爆発的発見、特に死海文書の発見によって、一九世紀末に確立されたかに見えた定説の修正が現在は余儀無くされている事態が反映されない結果になっている。その観点からは、「ヘブライ」の語源や、ヘブライ語旧約聖書や七〇人訳に見られる言語呼称を検討する第一部は評価できるが、第二部は少々物足りず隔靴掻痒の感がする。
著者はそれを今後の研究対象と心得ていて、本書はその全体構想の途中という理由にあるようなので、続刊に期待したいところである。この点の興味は、さしあたり土岐健治/村岡崇光『イエスは何語を話したか?』(教文館、二〇一六年)(ただし、土岐氏の論述は実質J・A・フィッツマイヤーの論考を焼き直したもの)やD・ビヴィン/R・ブリザード(河合一充訳)『イエスはヘブライ語を話したか』(ミルトス、一九九九年)で補うことができる。
最後に今ひとつの注文。翻訳引用には脚注に原文が添えられているが、残念ながら未だ稀には誤植の他にその訳に間違いもある(例えば、一九〇頁注三〇一、一九九頁注三三一)。