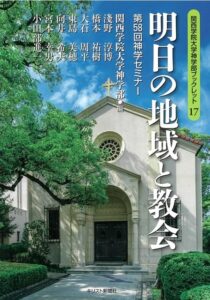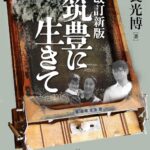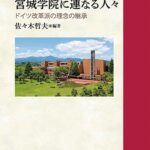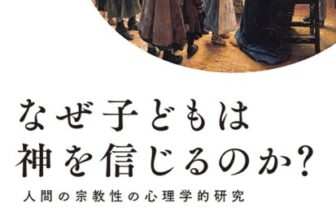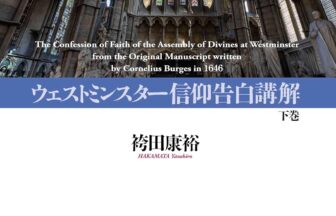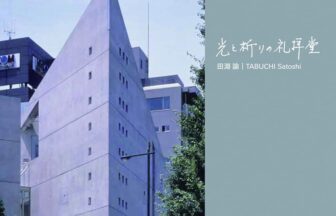制度ではなくアイデンティティの見直しから
〈評者〉伽賀 由
日本のキリスト教界隈で存在感の薄いメノナイト教会の筆者にとって、同労者である他のキリスト教会・教団教派の動向や情報を知るきっかけの一つに、キリスト新聞の松谷信司氏のSNSがある。今回そのユーチューブで大石周平氏のインタビューを拝見し、本書を知った。
本書は「明日の地域と教会」をテーマにして三つの講演、淺野淳博氏の新約神学と橋本祐樹氏の現代宣教学の二つの神学視点による講演に続き、大石氏の多摩地域教会の取組みの紹介を基調としている。
淺野氏は本書のテーマとして第一コリント書を取り上げ、その会食問題を通して教会が有機的に地域社会とつながる時、パウロは教会が何を大切にし、何に柔軟に対処すべきなのかをていねいに解き明かす。「食べる」という人間にとって極めて基本的な生活行為の中に、当時の地域社会で常識であった差別意識が如実に現れていた。このことが教会に入り込むことをパウロは阻止しようとした。神の共働者である信仰共同体すなわち教会のそのアイデンティティは平等なのであって、「パウロはこの問題を〈信仰〉の事柄ではなく〈良心〉の事柄として扱っていた」と明かす。さらにパウロは「洗礼と主の晩餐」を教会のアイデンティティの根拠として挙げ、このことを明確に維持することに心を配っていたと述べる。
続く宣教学的視点において橋本氏は、キリスト教も「もはや停滞ではなく衰退」という言葉で語られる現状があるとしながらも、いくつかの文献や統計学的数字から現代社会の無縁化する社会構図の中で、キリスト教会が大切にしてきた人と人との関係性は社会で大いに役立っており、それは宗教社会学的に認められているという。神の宣教に参与する教会として、この地上でのあり方・務め方が統計学上の数字にこそ表れてはいないが、しかし教会が地道にしてきた貢献が、互酬性の概念をはるかに超えて役立っているとの言葉に、日本のキリスト教会の持つ底力を感じ頼もしかった。
こうした聖書神学的講演と宣教学的講演に続く多摩地域教会の紹介は、日本キリスト教会の組織事情にまったく疎い筆者だが非常に考えさせられた。二つの異なる教会が「吸収合併」ではない方法を探る。これが簡単なことではないのは明らかだ。どの組織も機構改革しようとすると制度の見直しから始めようとし、それは教会も同じではないだろうか。
しかし多摩地域教会は制度ではなく、教会とは何か、自分たちの教会に適した枠組みはどのようなもので、どうあるべきか、その働きと務めを考える話し合いと祈りを重ねる。その間に多摩川の氾濫という水害とコロナ禍を経ながら、徐々に膨らむその話し合いが、常に教会のアイデンティティに基づくものであったのは確かだと推察する。なぜならまさにそれは初代教会がしてきたことであり、書簡はそれを示しているからである。
筆者は本書を「外からの言葉」として聴いた。教派組織を問わず「聖なる公同の教会を信ず」と告白する教会が、この目まぐるしく変化する社会で衰退の打開策を考える手立ての一つとして、教会で共に読みたいと思ったからである。