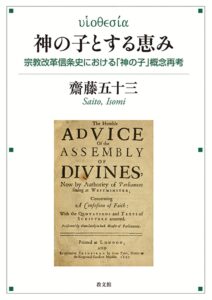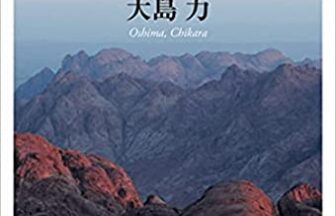生き生きとして有用な教理の再考
〈評者〉丸山忠孝
信仰者の救い全行程を一言で表現することは容易ではない。キリスト教の歴史で言えば、アウグスティヌスの『告白』、バニヤンの『天路歴程』、ウェスレーの『キリスト者の完全』を連想する者があるかもしれない。
ローマ・カトリック教会の基底を構成する救済論に信仰義認の立場から挑戦したルターは、ロマ書やガラテヤ書から信仰者の生涯を「同時に義とされ、かつ罪人」と理解し、それがその後のプロテスタント伝統では主要概念となった。しかし、宗教改革時代ではその他の概念も提唱されていた。同じくロマ書、ガラテヤ書やエペソ書からカルヴァンが信仰者を歴史的に捉え、神が与える「神の子とする恵み」を受ける者とみなす「神の子」概念も一例である。とはいえ、プロテスタント神学史ではこの概念は長らく等閑視されるところとなり、ようやく二十世紀末から再注目されるに至ったといわれる。
本書は「神の子」概念をめぐるこのような神学史の流れを背景として、オランダのフリー大学に神学分野で提出された学位論文に基づき、新たに書きあげられた著作である。そのため、一般読者対象の解説書を目指すよりは、現在進行中の学術論議を踏まえ、その過不足を見定めて著者独自の立場を提言する斬新な試みとなっている。とはいえ、論議展開における理路整然は当然としても、折々に広く読者を配慮した解説や注記が補足されていることから「今日、神学をすること」の意義や面白さを味わうことができる書でもあるといえる。
本書は確信の書である。これまで学位論文やそれに基づく著作に数々目を通してきたが、それらは研究書としての体裁さえ整っていれば、必ずしも確信の書である必要はない。しかし、パウロ書簡における「神の子とする恵み」(ヒュイオセシア)概念に魅せられて研究を始めた本書の著者は、この概念が救済論における単一主題であるに留まらず、義認や聖化などと関連する総合主題であり、さらに神の選びから教会論、終末論へと至る信仰者の全行程理解にとって不可欠であると確信するに至る。
本書の内容は、この「神の子」概念を十六、十七世紀のプロテスタント教会が信じ、教えた信仰告白文書の周到かつ緻密な分析をもって検証し、概念の今日的有用性を提言するものである。その核心部にはツヴィングリの六十七箇条提題、ルターの大小教理問答からカルヴァン関連のジュネーヴ教会信仰問答などを経て、ノックスのスコットランド信仰告白、英国教会の三十九箇条、ウェストミンスター信仰告白までの幅広い宗教改革信条の検証が置かれる。検証を通して著者が訴えんとする力点は、聖書から信仰者のあり方の抜本的再考を迫られた当時の教会が「神の子とする恵み」をいかに生き生きとして有用な教理であるかと信じ、教えたことに置かれていよう。そして、この訴えこそ本書をして煩瑣神学の落とし穴を回避させる一要因となっているといえよう。
急速に変遷する現代世界における家族の崩壊が取りざたされて久しい。「神の子」である信仰者個人、家庭人、教会人、社会人としてのあり方も危機に直面している。硬派の読み物ながら味わい深い本書が、読者の「現在」と「将来」に問いかけるものは必ずやあろう。