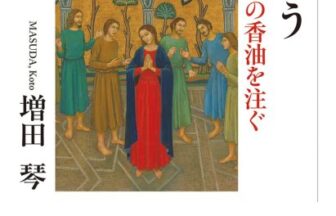霊性を「良心」で読み解く
〈評者〉斎藤佑史
霊性と言われても、宗教学の専門家はともかく、一般の読者にはその概念をすぐに思い浮かべることが難しい言葉ではなかろうか。本書はそのなじみの薄い言葉について長年マルティン・ルターを中心にキリスト教思想史研究に力を注いできた碩学の著者が、良心というキーワードで、一般の読者にもわかるように東西古今の古典と言われる宗教、哲学、文学作品を取り上げ読み解きながら、霊性の理解に資することを試みた書である。
ただし良心と言っても、その意味する範囲は幅広く、起源を辿れば、ギリシャ悲劇や旧約聖書の時代まで遡るとして著者はまずヨーロッパ精神史の観点から良心概念を辿っていく。その中で最も重要の役割を果たしているのはルターであるとして、本書ではルターの良心の問題が中心に論が展開される。ルターほど「霊」の観念を「良心」と結び付けて思索した神学者は他にいないからである。そこで著者は手始めに「良心」の問題を日本人の恥の意識と関連付けて分析する。日本と欧米の文化の違いを、恥と罪の文化の違いとして問題提起した文化人類学者ルース・ベネディクトの『菊と刀』は、日本と西洋の比較文化を考える上で欠かせない書であるが、本書でも「良心」の問題を恥と罪の文化の違いとに注目して捉える。その違いは端的に言えば、他者の目が気になる文化と、他者の目がなくても自分の犯した悪事は罪として罰せられるという文化の違いである。ドイツ中世史家の阿部謹也はその他者の目を「世間」という言葉で西洋の「社会」と「個人」とは違う日本の問題を追及したが、本書ではその世間の目が気になる日本文化の恥の文化と、西洋のキリスト教の罪の文化と対比させて、恥の意識と「良心」の関係を見ていく。そこで取り上げられるのが夏目漱石の『こころ』に見られる恥と良心の関係である。そこでは恥の意識が「良心」を抑止するという日本人特有の恥の形態が主人公の心理分析から鋭く読み解かれていて大変興味深い。本書の魅力は、何よりも良心の問題を東西の名作と言われる文学作品の人物たちを通して検討されている点にあると言ってもよいであろう。
ところで本書は、恥の問題は日本だけではなく、欧米にもあると言って比較検討し、公恥、自恥、羞恥の恥の三形態の説明後に本論とも言うべき良心の現象について詳述される。注目すべきは、恥にも三形態があるように、良心現象にも社会的、倫理的、宗教的な三形態があり、しかも恥と同様、段階的な差があると言って、これも古今東西の古典作品を引用しながら紹介、考察されていることである。社会的な良心の問題は、たとえばドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』、太宰治の『人間失格』、倫理的な良心の問題は、シェイクスピアの『リチャード三世』、ゲーテの『ファウスト』、ホーソンの『緋文字』などの分析によって検討される。その上で最後の段階として宗教的な良心の問題が、ルターの良心理解と漱石の『こころ』の問題を中心に展開されるのである。本書ではその他、良心概念の多義性と統一性などを含め、良心の問題がさらに幅広く考察、紹介されているが、いずれもよくまとめられていて、良心で読み解かれた霊性というものが明らかにされている。霊性の日本と西洋との違い、比較宗教思想史に関心ある人にはぜひ一読を勧めたい書である。