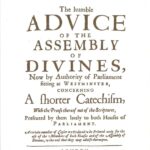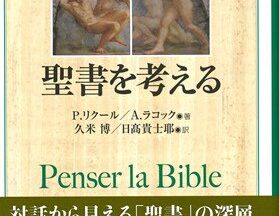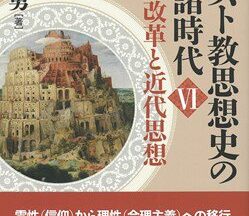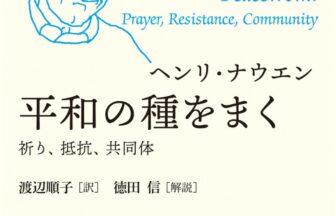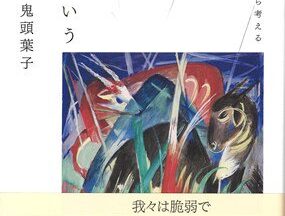『アウグスティヌス著作集』ついに完結!
〈評者〉片柳榮一
『アウグスティヌス著作集』の最後となった『詩編注解』は独特の魅力をもっている。アウグスティヌスは聖書注解において、次第に比喩的解釈を避け、字義通りの「逐語注解」に努めるよう傾いてゆく。しかしこの『詩編注解』においては、比喩的解釈がかなり自由に用いられ、彼の想像力はのびやかに、生き生きと飛翔している感がする。しかもその言葉は彼の生の深みから汲み出されている。
有名な「バビロンの川のほとり」(一三六編、新共同訳では一三七編)を取り上げてみよう。アウグスティヌスは「バビロニア」とは「混乱」を意味するという。「(我らは)エルサレムからの、すなわちシオンからの市民であって、この生の中に、この世のこの混乱の中に、このバビロニアに市民として住まうのでない」(二四七頁)。そして深い警告を語る。「バビロンの河々の流れに注意しなさい。バビロンの河々の流れは、この世で愛されて過ぎ去りゆくものすべてだ……それが流れることに、注意しなさい。それが滑ることに」(二四九頁)。さらに比喩的解釈は広がる。「じっさい、いたるところでバビロンの河々は早瀬のように流れ、あえて中に入るひとたちをひっくり返して、流し去る。……だから捕らわれの身にあってわれらは低められて、バビロンの河々の流れのほとりに座ろう、われらはおのれを、あえてその河々の流れに投げ落としてはならない。……おのれをあえて高ぶりで持ちあげずに、座ろう」(二五〇頁)。アウグスティヌスにとって「座る」とは、流れ去る喜びにひたって己を高く上げるのでなく、この過ぎ去りの悲嘆のなかで己を砕かれて低くされることである。バビロン捕囚の悲哀のなかで故郷シオンを思って歌われたこの詩編は、アウグスティヌスにおいて、過ぎ去り行く事物への愛に虜とされながら、なお永遠的なものを喘ぎ求める人間そのものの形姿へと彫を深めてゆく(パスカルはここから深く学んでいる─パンセBr.459)。
「深き淵より」で始まる一二九編を見てみよう。アウグスティヌスにとってここで問題の「深淵」は、この詩人だけのものではない。人間一人ひとりが抱える「深淵」のことである。「それゆえ、わたしたち一人ひとりがどのような深淵にいて、どこから主に叫ぶのか、見るべきである」(一二二頁)。アウグスティヌスが見る「深淵」とはどのようなものか。「どんな深淵から主に向けて叫ぶべきかを我々も理解しなければならない。実に、わたしたちにとって深淵とはこの死すべき生である」(一二二頁)。そしてこの深淵からの叫びは遮るものを切り裂く。「その声はすべてを貫き、すべてを引き裂き、神の耳に達した」(一二二頁)。しかしこのことが可能であったのは、己の力によるのではない。「神の耳が祈願する者の心の内にあったのを、すべてが引き裂かれてその声が神の耳に達するのだと言うべきであるならばだが」(一二二頁)。アウグスティヌスによれば、神の耳はすでに人間の心の内の、心そのものより奥底にすでに在り、耳を傾けているという。「内在的超越」の秘義を、ここにもアウグスティヌスは読み取っている。