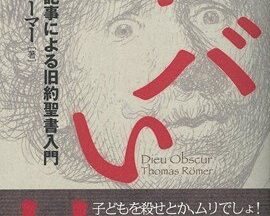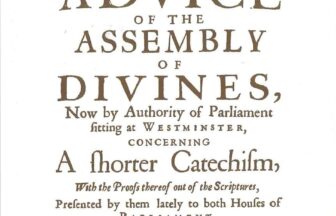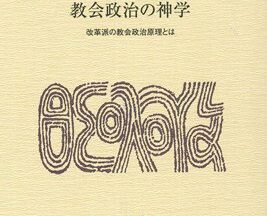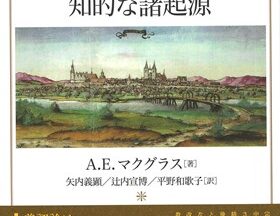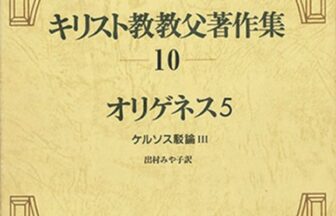古代末期の教会人の肉声を伝える「歴史小説」の秀作
〈評者〉出村和彦
本書は、古代末期、教会人・牧会者として生きたアウグスティヌスの最晩年の日々(四三〇年八月)と若き司祭としての活動(三九一─三九五年)を中心にその生涯を生き生きと浮かび上がらせる「歴史小説」の秀作である。
物語第一部は、アウグスティヌスの弟子であり長年の同僚であったポシディウス─彼は現存する伝記『聖アウグスティヌスの生涯』の著者でもある─の目に映った臨終の床に就く師の姿から説き起こされ、三九一年司祭叙任時へと場面をフラッシュバックする。ここでは、回心に至る彼の心の葛藤も、三七歳のアウグスティヌス自身による回想の中で印象的に示されている。
第二部は、三九一年から三九五年の補佐司教叙任までのヒッポの若き司祭アウグスティヌスの活動を同時期の著作や書簡・説教を典拠に的確に記述され、初期キリスト教思想史的にも十分首肯し得る若き司祭アウグスティヌスその人の生きた姿を提示してくれる。旧友ホノラトゥスを配して描かれるマニ教指導者フォルトゥナトゥスとの対論、色や臭いまで伝わる洗礼式の描写、「偉大なる謙遜」、「愛すれば愛するほど」、「愛は赦すこととして姿をあらわす」、「神の恩恵は愛と共に旅を続ける」という小見出しのもとに現実の「ドナトゥス派との対峙」が描かれる第二部は圧巻である。ドナトゥス派ティコニウスの立ち位置が正確に記されていることも重要である。
終部では、陥落間近のヒッポでの最晩年のアウグスティヌス図書館の模様に引き戻され、ペラギウスとの残念なすれ違いと、臨終の床でひたすら祈るアウグスティヌスが照らし出され、若き日の『主の山上のことば』説教を再び味わいつつ本書を閉じることになる。
有名なアウグスティヌスの『告白録』には三九七年の司教の現在とその十年前の回心とその翌年の母の死までの前半生の事象が記されているが、その後故郷アフリカに帰って「神の僕」の生活を始めた様子やたまたま訪れたヒッポで突然司祭に挙げられた子細などについては教えてくれない。本物語はその間の彼を知りたいという読者の飢えを癒してくれる待望の書である。
特筆すべき点として、ヒッポの前任司教ワレリウスがアウグスティヌスを教会人として立たせるのに配慮を怠らなかったことや、北アフリカの全教会の監督者であるカルタゴ司教アウレリウスとの補完的関係が丁寧に描かれていることがある。アウグスティヌスは神学的に孤高の境地にあったが、しかし多くの友人を持ち、決して孤立した存在ではなかった。その中で特に、タガステの神の僕たちの「家」とヒッポ教会の庭園の修道院をつなぐ存在としてポシディウスを配し、本書は、彼の目を通して、司祭叙任の時から終焉に至るその生涯を俯瞰しつつ、アウグスティヌスがいかなる人であったかを描くことに成功している。
この「古くて新しい物語」は、「自分の弱さを率直に開け広げることのできる偉大な教父、繊細な魂をもって生きた信仰者、目の前にある人を神の民として愛した教会人アウグスティヌス。その人に、わたしは友人に覚えるものに似た親近感を覚え、その言葉に励まされてきた」と言う著者ならではこそ語り得た快挙であり、我々に与えられた大きな恵みである。