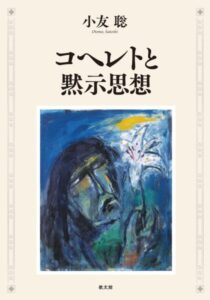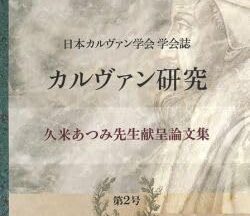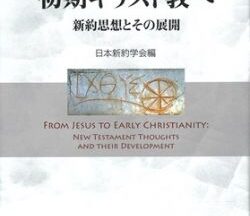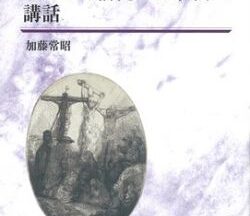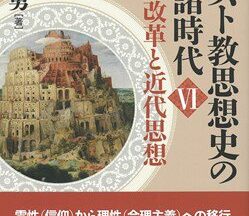真意を読み出す熱意とスリル
〈評者〉並木浩一
コヘレト書が人々に与える印象は厭世的な世界観の展開であるが、この書物は見かけと違い、実は同時代に出現した「黙示思想」批判の書である。黙示を重視するダニエルのような賢者は、神が歴史に終末をもたらす「将来起こること」の「秘密」を言葉の解釈によって認識し、それを誇りとする。しかし人々が終末の予知に没頭すれば、現世に対して消極的となり、人間の自由と責任とを放棄して民族の連帯を危うくする。実際、その頃にエッセネ派はエルサレムの祭儀団体を離れ、死海のほとりで閉鎖集団を形成した。
ダニエル書は一般的にシリア王による神殿の汚辱を拭った後の前一六四年頃に成立したと見なされている。他方、著者によれば、コヘレト書はシリアによるギリシア文化の押しつけがもたらした混乱が収まっていない前一五〇年頃に成立した書物であり、黙示重視のダニエル書を批判する。著者のこの大胆な推測は一九九〇年代の後半のドイツ留学の所産としての博士論文として結実した。しかしこの革新的な見方はダニエル書を旧約文書の最終のものと見なす通説を訂正することになり、コヘレト書をダニエル書批判と関係づける研究者も存在しないので、学会では顧みられなかった。そこで著者はコヘレトの黙示批判についての一層の証拠づけを求めて、二〇〇〇年から二〇一七年にかけて一四編もの論文を執筆した。本書は自説補強のためのこれらの研究論文を収め、巻末には的を射た書評二編を添えている。
著者はこの間の洞察に基づいて、『コヘレト書』を二〇二〇年に出版したが、注解書であるゆえに簡潔な叙述を心がけており、「黙示とは何か」などの総論的な問題についても、個々の問題についても、詳しい考察を省いている。それに対し本書に収録された諸論文は、ダニエル書とコヘレト書が前二世紀中頃のユダヤ教の混乱期にいかなる役割を果たしているかを熟慮する。著者は作者が現実主義の徹底のために「最悪のシナリオを想定」する作戦を取ったと考え、その観点から個々のテクストについて立ち入った考察を展開する。自説を確立しようとする著者の議論には気迫が溢れており、注解書における著者の発言を納得させる。
著者のコヘレト書理解は学位論文の執筆時に一気に獲得されたわけではなく、その後にも論拠発見のステップがあった。著者は信濃町教会での講演の際、反黙示の意図と「ヘベル」(新共同訳「空しさ」、聖書協会共同訳「空」)との関わりを問われてそれを有効に説明できなかった。しかしその後、作者は黙示が終末の時に関心を集中させることに対抗し、現在の時の貴重さを際立たせるために、人間活動のすべては「束の間」だと言ったと気づいた。書物冒頭でのこの言葉の多用は読者に悲観的だとの印象を与えるが、作者は誤読される危険を恐れていない。作者の意図は人を惑わす文言をちりばめて、その「謎解き」を読者に迫ることにある。例えば、千人の中に男はいるが女は一人もいないという女性蔑視と見える言葉(七・二八)は、男はいざというときには軍隊の一員として戦うのだと解すべき謎掛けである。見かけに捕らわれてはコヘレト書の挑戦に立ち向かえない。本書は読者に真意を読み出すスリルを味合わせる労作である。