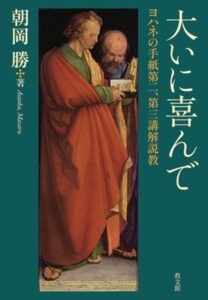聖書講義を超える、講解”説教”の本来のあり方を示す説教集
〈評者〉牧田吉和
本書は「愛の手紙」と呼ばれるヨハネの手紙の第二・第三に関する連続講解説教集である。収められている九編の説教は、著者が二〇年にわたって牧師として仕えてきた群れのために、群れを辞し、新しい任に就こうとする狭間の中で、しかもコロナ禍、会堂建築のただ中でなされたものである。パウロのエペソの長老たちへの告別説教にも似た、去り行く群れへの牧会者の全ての思いが込められた説教集である。
一読して思わされることは、説教者としての著者の姿勢である。著者自身がキリストにおける神の愛に捉えられ、生かされ、動かされつつ牧師・伝道者として全身全霊をささげて説教をしているという事実である。「大いに喜んで」という本書のタイトルは何よりも説教者自身の思いを言い表している(一二九─一三一頁)。この意味で、本書に収められた説教は「キリストの愛に生かされた説教者が、キリストの愛に生かされた群れの一人一人に、キリストの愛に生き続けるように、大いなる喜びに生き続けるように促してやまない説教」と性格づけることができる。「愛の手紙」といわれるヨハネ書簡の性格と見事に響き合って語られた説教である。
本書は講解説教の”本来のあり方”を提示している。単なる聖書講義ではない。確かに釈義を踏まえているが、テキストの核心を捉え、”講義”ではなく、講解”説教”として語られている。このような講解”説教”が成り立つためには、一方では説教テキストに対する、他方では聴き手としての群れとその一人一人に対する祈りを伴なった深い「黙想」を必要とする(二一─二二頁)。本書には「黙想」の果実をあちこちに見出すことができる。教会の具体的な諸問題、群れの一人一人の羊たちのことが御言葉の光に照らされて語られている。しかも、個人的霊性の枠にとどまっていない。聖餐を中核とした教会論的見通し、社会と世界に対する見通しの中で語られている(一〇二頁、一四七─一四八頁)。説教の背後に堅固な神学的基盤がある。この意味でも本書は、講解”説教”の本来のあり方を示していると思う。
本書の巻末には、小論「語られ、聴かれ、生きられるみことば─説教を巡る小さな論考」が掲載されている。著者の説教論の一端を明らかにしている。そこでは「説教者と聴衆の「思いのすれ違い」の問題が取り挙げられている。説教者の側からは「どのように聴かれ、どのように届いているのか」の問題、聴衆の側からは「御言葉が聴けない」という苦悩の問題である。この問題は”公に”論じられることはあまりない。時には触れてはならない問題でさえある。説教批判に結びつき、教会に混乱を招きかねないからである。この問題は説教学的にも十分に論じられてきたわけではない。しかし、この両者の「思いのすれ違い」の問題が健康な姿で教会内で”公に”話し合われる時、説教には大きな希望が生まれる。著者が目指すように「語られ、聴かれ、生きられる説教」が生まれるからである。巻末の小論をテキストにして、教会内で語り合われることを強く期待したい。本書は小さな説教集であるが、霊的にも、説教学的にも読むに値する説教集である。