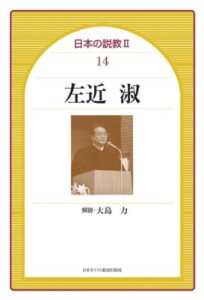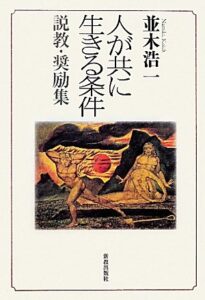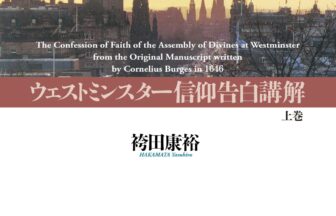「もし旧約聖書がもっと頻繁に説教されるなら、新約聖書の説教はもっと深いものになるはずです(なぜなら、新約聖書は、旧約聖書を前提にし、言及し、引き合いに出し、暗示しているからです)。旧約聖書を無視することは、一六章からなる小説の最後の四章を読んで、全容を把握したつもりになるようなものです」。デューク大学の旧約聖書学者エレン・デーヴィスが率直に書いている。
ただ、そうは言われても、旧約聖書の説教をする際に、どうしても二の足を踏んでしまうのが、与えられた箇所の歴史的背景や文脈についての知識への不安や、(いわゆる「復讐の詩編」などに響いている)予定調和を突き崩す旧約聖書的な語り口への違和感などかもしれない。そこで旧約聖書説教の三冊をあげる前に、比較的最近出版された、説教準備に有益な(何よりも手に取りやすく読みやすい)いくつかの書物を紹介してみたい。並木浩一/奥泉光著『旧約聖書がわかる本─〈対話〉でひもとくその世界』(河出新書、二〇二二年)、トーマス・レーマー著『100語でわかる旧約聖書』(久保田剛史訳、白水社、二〇二一年)、長谷川修一『旧約聖書─〈戦い〉の書物』(慶應義塾大学出版会、二〇二〇年)などがある。それぞれに旧約聖書の泰斗が、旧約全体を視野に入れて、歴史的背景について、最新の学問的知見を反映させながらも、平易な切り口で叙述したものである。読み終えると旧約聖書の世界と思想を的確に把握できるものといえよう。また山我哲雄著『聖書時代史─旧約篇』(岩波現代文庫、二〇〇三年)は、旧約聖書理解に欠かせない古代オリエント世界と聖書記述の歴史的連関をダイナミックに捉える助けとなる。やや大部ではあるが、説教の黙想に資するものとしてW・ブルッゲマン著『旧約聖書神学用語辞典』(小友聡/左近豊監訳、日本キリスト教団出版局、二〇一五年)がおすすめである。神学的考察によって現代社会に旧約聖書の言葉を響かせる手がかりを、豊かなアイデアと斬新な視点で読者に与え、黙想を深めさせる。
もう一つ、旧約聖書の説教者が自らを「ストーリーテラー」あるいは「詩人」としてイメージすることで、「聖書から説教へ」、「聴き手から聖書へ、そして説教へ」ということから更に進んで「聖書を説教へ」ということが意識されるようになる、との平野克己氏の指摘も有益である(越川弘英/平野克己/大島力/並木浩一著『旧約聖書と説教』日本キリスト教団出版局、二〇一三年)。旧約説教は、旧約聖書について説明するのではなく、旧約聖書に照らして引証するのでもない、旧約聖書そのものに語らしめることが求められているといえよう。説教者自身が旧約聖書の語りに耳を傾け、圧倒され、挑戦を受け、巻き込まれ、突き動かされ、説教者をはじめとする礼拝者すべてが、生きて働かれる神のみ言葉に打たれるものとなろう。
ふと一九五〇年代のニューヨーク・ユニオン神学校で学んだ小説家F・ビークナーが短編にしたためた、旧約聖書学教授J・マイレンバーグに関する叙述を思い起こす。
「教室の通路を縦横無尽に歩き回りながらマイレンバーグは戦いの歌、あざけりの歌、そして古代イスラエルの崩壊を悼む挽歌を口ずさんだものだった。体を硬直させ、膝を折り、両腕をかかしのように両側に伸ばしながら、彼は単に旧約聖書を教えただけではなかった。彼自身が旧約聖書だった。……彼の祈りは、(詩編詩人のように)もうそれはほとんど泣きじゃくるかのようで、いつまでも終わらなかった。……親しいのは暗闇でありながらも、光というものを、あたかもしっかりと?めるものででもあるかのように?んで離さなかった。自分の心を抱きしめていながら、その心はどこか破れていた。満杯の教室を前にしている者でありながら研究室では一人ぼっちであった。……彼が最終講義をユニオンで行ったときには、私はもうそこにはいなかったが、こんな話を聞いた。道を隔てた反対側にあるユダヤ教神学院からたくさんの学生がその最終講義を聞きにやってきたというのだ。そして部屋に入る前に、廊下で靴を脱ぎ、マイレンバーグと共に立っているその場所が聖なる場所であることを表したと」。
ちなみに、このマイレンバーグの教え子にブルッゲマンや左近淑ら旧約説教者がいる。左近淑の教え子には大島力(『自由と解放のメッセージ─出エジプト記とイザヤ書から』教文館、二〇二二年)や大野恵正(『永遠の支え─大野恵正説教・講演集』教文館、一九九五年)などがいる。聖書に証される生ける神のパトスに打たれたものたちの説教の系譜をたどることもできよう。
現在入手可能で、神の熱情がほとばしる旧約聖書の説教集の中から三冊をあげたい。それぞれに教会の信仰に堅く立って語られた旧約説教集である。歴史的教会の教理と信仰に立ってなされる旧約説教は、み言葉の説教である。「生きていて、力があり、いかなる両刃の剣より鋭く、魂と霊、関節と骨髄とを切り離すまで刺し通して、心の思いや考えを見分ける」(ヘブライ四・一二)「神の言葉」が、御前に集う者たちを礼拝者とする。
パウル・ティリッヒ『地の基は震え動く』
「(預言者の)一つ一つの言葉がまるでハンマーの一撃です」。エレミヤとイザヤの言葉を聞いてから、そう語りだされるのは、ユニオンでマイレンバーグの同僚であったパウル・ティリッヒの『地の基は震え動く』(茂洋訳、新教出版社、二〇一〇年)である。鋭い現実批判に貫かれた、プロテスタントに典型的な預言者的説教の範例といえよう。冒頭の説教では、天地創造の秩序が混沌へと巻き戻されてゆく様を語る預言者の言葉への戦慄が、核兵器を弄び破局の引き金に指をかけた現代世界を震わす言葉として響く。徹底的で絶望的な崩壊を透徹した眼差しで見据え、そのただ中に永遠なるものの出現を、冬枯れの季節にアーモンドの枝に目覚めを見たエレミヤと共に「永遠の巌と終わりのない救いに目を注げ!」と叫ぶ荒野の預言者の声を聴く。きな臭さ漂う・戦前・に差し掛かっている今、教会が旧約聖書の預言者の言葉を聞く感性を研ぎ澄ますことを促す説教集といえよう。
左近淑『日本の説教Ⅱ 14 左近淑』
「(破局の果てに生き残った者の世界は)“終わり”を通り抜け、『死の内の生命』(R・リフトン)であり、生かされた枯れた骨であります」と述べるのは、左近淑『日本の説教Ⅱ 14 左近淑』(日本キリスト教団出版局、二〇〇七年)のエゼキエル書三七章をテクストとする語りである。旧約聖書を紐解くことは、現代を独特な切り口で鋭くえぐり、そこに語り掛ける神の言葉に聴くことになる。「今日の破れを引きずりながら、会衆と共に上から語りかけられるみ言葉を聴く」ものとされる。エゼキエルと共に累々たる骨の山、憂いに満ちた魂を携えて干からびた現代人の破れを目の当たりにし、そのただ中に身を置きながら、生命の泉湧き出させる神の御前に立つ恵みが沁みてくる。そしてこの恵みへの応答として、礼拝者が、恐怖と死の言葉に終止符を打たれたキリストによる復活と命の言葉に生きることへと、心を高く上げるものとされる説教集である。
並木浩一『人が共に生きる条件』
「人間の自発性を、人が自由であることを尊重し」、不条理にのたうつ人間との弛まぬ対話の相手となられる神と対峙させるのが、並木浩一『人が共に生きる条件─説教・奨励集』(新教出版社、二〇一一年)である。ヨブ記、創世記、詩編などのテクストを通して語りだされる言葉が、神の民の魂に清冽で自由な精神の横溢をもたらす。数年来顕著になっている、自主と自律の放棄、魂の鈍麻、妄想への陶酔、自由から逃走し漂流し蝕まれた閉塞に喘ぐ社会にあって、吹きかけられる命の息吹を胸いっぱいに吸い込んで、答えなき世を目覚めて良心を保って歩み続ける上よりの勇気と力が漲ってくる説教集である。