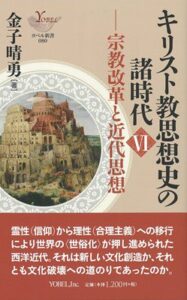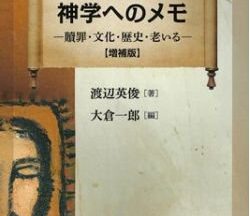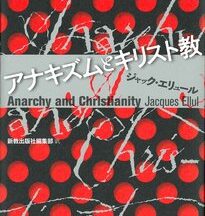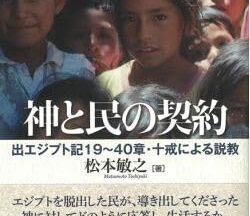宗教改革と近代を貫くヨーロッパ精神の地下水脈
〈評者〉佐藤真一
近代ヨーロッパは啓蒙主義とともに始まる。このように捉えたのはトレルチの洞察であった(「啓蒙主義」一八九七年)。啓蒙主義は、ヨーロッパの生活全般に大きな変化をもたらしたばかりでなく、超自然主義を排除することによって伝統的な哲学、歴史学そして神学に変容を迫った。こうした指摘は、宗教改革と近代との間には溝が存在するという理解を前提としている。
著書『ルターの人間学』(一九七五年)以来ヨーロッパ思想史の緻密な原典研究と取り組んでこられた金子晴勇氏が、こうした問題意識を共有するとともに、神秘主義の伝統の中で培われた「霊性」思想に着目することによって宗教改革から十九世紀に至るドイツ思想史に新鮮な光を投げかけていることに、本書の大きな意義がある。
本書の問題関心を印象的に示しているのは、ブリューゲルの名画「バベルの塔」(カバーと本文扉参照)についての一節である。「この塔は上部が欠けた円錐形で描かれているが、実は欠けているところが『霊』に相当し。その下部が魂と身体になっている。霊の部分の損傷は激しくその痕跡がわずかに残っている」(七〇頁)。ここに著者は、近代に顕著となる超越的なものへの眼差しの喪失を見る。すなわち啓蒙主義の合理主義が理性の自律化を招き、ヨーロッパ的霊性を追放し精神の深みを失ったとするのである。
著者によれば、ルターはエラスムスやカルヴァンとともに、「霊(spiritus)・魂(anima)・身体(corpus)」というキリスト教の人間観をあらわす三分法(Ⅰテサロニケ五章二三節)に依りながら、霊性を重視する。ルターの信仰義認論の背景には、概念的に把握するのは困難であるにしてもこうした霊性が豊かに見出される。そこには、「魂の根底」について語ったエックハルトやタウラーからルターが継承した中世ヨーロッパの神秘主義が息づいている。
この「霊性」思想は、宗教改革と近代の間に存在する溝にもかかわらず、十七世紀後半に生じ十八世紀に全盛期を迎える啓蒙主義のもとでも、地下水脈のように受け継がれている、と著者は指摘する。ライプニッツは宗教改革と啓蒙主義の対立を克服しようと試み、『神義論』で懐疑的なピエール・ベールを論駁する。とくにドイツ敬虔主義においてはルターの伝統に立つ霊性が継承された。その指導者の一人フランケは、学問と信仰との葛藤を経験しつつも、シュペーナーの感化を受け、啓蒙主義との対決の中で霊性を養ってゆく。つづくツィンツェンドルフは啓蒙主義の影響を深く受けながらも、敬虔主義の代表的な担い手として神秘主義の伝統を堅持した。ヘルンフート兄弟団の設立はその活動の実りであった。シュライアマッハーは敬虔主義に養われ、超越者に対する感情である「心情」(ドイツ神秘主義に通底する「根底」と同義)を重んじ、『宗教論』(一七九九年)で啓蒙主義の宗教蔑視を批判した。
こうして、啓蒙思想の支配的な潮流の中にあっても、ルターに示された注目すべきヨーロッパ精神の伝統が脈々と流れていたことを、著者は浮き彫りにしているのである。
そしてこうした学問的な考察の背後に、現代の精神状況に対する碩学の瑞々しい問いかけをわれわれは聴き取ることができる。本書が広く読まれることを願っている。