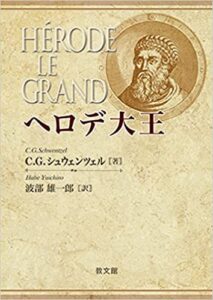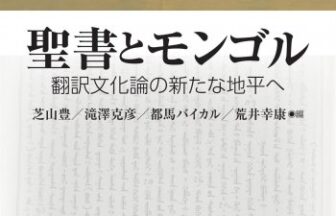ヘロデ大王とその後継者たちの歴史的実像に迫ろうとする意欲作
〈評者〉小河 陽
ローマ皇帝アウグストゥスをして「ヘロデの息子であるよりは豚である方が良い」と言わしめたと伝わるヘロデ大王と言えば、残酷で陰険な暴君というのが一般的な印象である。しかし本書は、このようなネガティブなヘロデ像を相対化して、ローマとユダヤ人の双方を同時に見る二面性を持った複雑な個性として見極めようとする目的のもと、彼の王国のイデオロギーや政策など、テーマ別にまとめた考察を一般読者向けに読み易い筆致で提示している。
全体は四章に分けられ、第1章では、ハスモン王国の片隅の地イドマヤの地方長官にすぎなかった父アンティパトロスの台頭からヘロデによる権力の掌握、そして皇帝の友として権力の絶頂に至るまでの歴史的展開が、必要十分な情報でもって辿られる。
第2章は本書の特色を成しているテーマでもある「プロパガンダと王のイデオロギー」を取り上げ、ヨセフスの記述や碑文、また硬貨に残された数々の図案、とりわけその頭飾りと冠などの分析を通して、ヘロデのイデオロギーの復元を試み、ヘロデ王朝がユダヤとヘレニズムという「二つの顔」の特徴を持っていたことを論じる。
第3章では宮廷の様態、行政機構、王国財政が取り上げられるが、全体として示されるのは、ヘロデの豪奢な生活と壮麗な建造物など、豪華な環境と生活様式はヘレニズム時代の諸王と共通していながら、そこにユダヤ教の規律と両立し得る生活が存在していたということである。
第4章のテーマはヘロデの後継者たちの治世であるが、二面性を持ったもうひとりの王アグリッパ一世を除けば、いずれも時代環境の中を巧みに立ち振る舞う才覚も能力も持ち合せることのなかった様が描き出される。
一九世紀以降の実証的研究、そしてまた本書の中でも紹介されている様々な先行研究の中で、「残虐な暴君」だけではなかったヘロデの優れた政治的才覚と手腕が確認されてきた中で、本書に見られる独自性を挙げるとすれば、訳者があとがきの中で好意的に指摘しているように、特に第2章に提示される解釈であろう。先行研究の多くがヘロデにとってユダヤ教の伝統と律法の尊重は政治的利用のための表面上のものに過ぎなかったとするのに対して、著者はヘロデのユダヤ教信仰が実質を伴うものであったと主張する。そのために、マサダ出土の壺に認められるラテン語銘文「ユダヤ人ヘロデ王に」を「ヘロデ王に、ユダヤ人に適切なものとして」と読み、ワインがユダヤ教清浄規定に従ったものであるとまで結論する(九二頁)。だが、タキトゥスのベレニケ描写Florens aetate formaqueを「花のように美しい盛りの」と訳す著者のラテン語読解(二六二頁)同様、素直には頷けない。それは、ヘロデの宮廷がギリシア教育を受けた者たちに取り巻かれ、王国の非ユダヤ的諸都市に異教神殿を建てさせたような側面を打ち消すほどのユダヤ的性格なのか。鷲をケルビムと同一視して、神殿の門上への鷲の設置が第二戒の古い聖書解釈に回帰するものとの主張は文献証拠で支持されるのか。著者独自の主張が説得力を持って展開されているか、読者の判断が待たれるところである。
とまれ、エトナルケースがエトナルコスとなるなどは気になるが、こなれた訳文には、その労を多としたい。