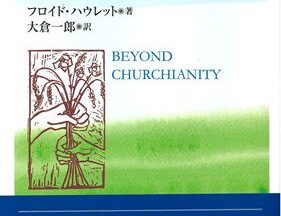キリスト者・日本人として誠実なる探求の粋
〈評者〉佐々木亘
著者は北海道大学教授で、オランダのライデン大学から博士号を取得し、外国語の書籍や論文を多数執筆するなど、国際的に活躍されている。その著者が昨年の『古代キリスト教研究論集』(北海道大学出版会)に引き続き、東方キリスト教研究も加えた本書を今回公刊された。「あとがき」で、著者は「謝らない態度」が「ヨーロッパの文化の特徴の1つを成している」が、「キリスト教のメッセージは罪の自覚を促し、そして赦しの必要性を説くもの」であり、「赦しが必要であることを認めるためには、自分の非を認める、つまり謝ることが不可欠」である以上、「ヨーロッパは果たしてキリスト教を理解した(或いは根本的に受容した)のだろうか」と問いかけている。キリスト教はヨーロッパの宗教だと考えている人にはとても衝撃的だが、これを機会にキリスト教を、地理的にも時代的にもより幅広い視野から捉え直してみたい、と思われる方には必読の書である。
本書は3部構成になっている。第1部「キリスト教修道制、古代末期」では、主に著者の『キリスト教修道制の成立』(創文社、二〇〇八年)を巡っており、「殉教を求める人々の熱情が禁欲実践へと向かったことによって修道制が成立した」(三〇?三一頁)。このように成立した修道制のあり方は、現代における信仰の意味に多くの示唆を与えるであろう。
第2部「東方キリスト教とその周辺」では、まず『エジプト人マカリオス伝』の伝承の過程が、コプト語、シリア語、アラビア語等の写本を丁寧に読み解く仕方で示され、後半では聖人伝が取り上げられ、バルダイサンによるシリア語の『諸国の法の書』の翻訳(第7章)がなされている。まさに八面六臂である。難解だが、謎解きの興奮を堪能できる。
第3部「その他」では、主に著者の翻訳であるマックス・ヴェーバー『宗教社会学論集 第1巻上』(北海道大学出版会、二〇一九年)を巡って展開される。既に多くの翻訳が存在しているが、ヴェーバーが西洋古代学者であるからこそ、著者が翻訳する必要性と独自性が存している。古代・東方からヴェーバーに至る展開は著者の真骨頂と言えよう。このように本書では、現代的な問題意識を全面に出しながら、「キリスト教とは何か」が多元的に問われており、この書を手にした読者にはきっと様々な新しい発見がもたらされるであろう。
さて、著者は自らがプロテスタントの信者であることにたびたび言及している。例えば、第1部では主に修道制を論じているが、ルターが修道制を否定していることから、その現代的な可能性にも触れている(第5章)。たしかに著者の驚異的な研究業績は、まさにヴェーバーの禁欲(第1部第4章)がなせる業である。一方、中世哲学の山田晶先生はことあるごとに、「ルターはカトリックの恩人だ、ルターがいなかったらもっと悲惨なことになっていた」と評者に言われた。カトリックだ、プロテスタントだという区別を、そろそろ卒業する時期に来ているのではないだろうか。たしかに、両者は思想的にも典礼的にも大きく異なっているが、この違いは「神のこと」じゃなくて「人のこと」(マタイ一六章二三節)では?この点、著者の見解をいつかお聞きしてみたい。