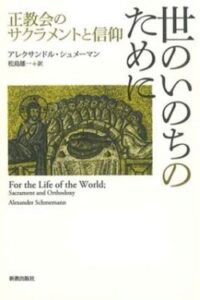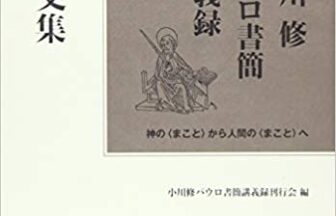アレクサンドル・シュメーマン「世のいのちのために」(新教出版社)
待ちに待った朗報である。二〇〇三年に新教出版社から翻訳(訳者本稿筆者)、出版され、広く我が国のキリスト教界で新鮮な感動を以て読み継がれた「世のいのちのために(For the Life of the World)」がこの春、再版された。著者は、キリスト教の奉神礼(Liturgy)の神髄を語る神学者として、教派を越えて受け入れられてきた故アレクサンドル・シュメーマン神父(アメリカ正教会)。本書は一九六三年全米キリスト教学生連盟の四年に一度の大会で「学びの手引き」として執筆された。体系的な神学論文ではなく「キリスト教の世界観の輪郭、正教会の奉神礼体験が明らかにする世界と人生への見方を示そうと試みたものにすぎない」(まえがき)。しかしその後、米国内はもとより、イギリスでも出版され、さらにフランス語、イタリア語、ギリシャ語に翻訳され、ソビエト政権下での地下出版の一つとしてロシア語にも翻訳された。
私がこの書を初めて手にしたのは、神学校卒業後、司祭として働き始めてまだ間もない頃である。本書第一章「世のいのち」のページを繰るごとに高まっていった衝撃は忘れられない。正教会はきわめて奉神礼的な教会である。その奉神礼世界の中心に置かれているのが、聖体礼儀(カトリックのミサ、プロテスタントの聖餐式にあたる)と、そこでキリストの身体と血として、パンとぶどう酒(日本正教会ではこれを尊んで「尊体」「尊血」としばしば呼ぶ)を分かち合う「領聖」である。当時は、ほとんどの信者が「尊体尊血」はその「尊さ」ゆえに「みだりに受けるものではない」というあやまった敬虔主義の影響で年に数回しか領聖していなかった。その現状を打ち破るべく、故フェオドシイ府主教が粘り強く頻繁な領聖を呼びかけ、その呼びかけがようやく実り始めていた時代であった。ただ、今振り返ると、私たち司祭たちも含め一般の理解は、「尊体尊血」の「尊さ」ゆえに、もっと頻繁にその「かたじけない御恩寵」に与るべきであると、一八〇度転換しただけで、それはなぜ尊いものなのかは十分に掘り下げられず、「領聖体験の繰り返し」のなかで自然に「ありがたみ」が会得されてくると「託宣」されたというのが実情であった。私自身もその「託宣」に加わっていたひとりである。「それを食べる人は、決して死なない。いつまでも生きる」(ヨハネ6・49-51)と主ご自身がおっしゃったじゃないか! ヨハネ伝第六章の「いのちのパン」を「み言葉」への象徴的表現とは解釈しない正教会では、こう言うほかなかった。
シュメーマン神父はこの「託宣」の背後にある神秘へと私の目を開いてくれた。神父はまず第一章で「食べ物」を論じる。
「聖書では、人の食物、すなわち人が生きるために関与しなければならない『この世』は神から『神との交わり』として与えられたものです。……存在するものはすべて神の人への贈り物です。人が神を知り得るため、また人のいのちを神との交わりにするための贈り物です。人に食物を与えいのちを与えたのは神の愛です。神はそのお造りになったものを何もかも祝福します。『主の恵みふかきことを味わい知れ(詩編34:8)』と聖書にあるように、神はすべてを『しるし』として、ご自身の存在と知恵、愛と啓示の手段としてお造りになりました。人は飢えた存在です。しかしそれは神への飢えです。私たちのいのち(=生命、生活、人生)のあらゆる飢えの背後に神への飢えがあります。すべての欲求は最終的には神への欲求です。……全被造物は食物に依存しています。しかし、人のみが神から受け取った食物といのちを讃えるべく存在している点に、全被造世界での人の独自の位置があります。人だけがその讃美(blessing)によって神の祝福(blessing)に応えます」。
この讃美と祝福の応答、ひとたび罪によって失われたこの交わりが、キリストによって回復され、人は被造世界全体への司祭としてよみがえったことこそ、キリストによる救いの本質である。その救いの「現前化」こそ教会であり、「キリストのからだ」によって開始された感謝と呼ばれる奉神礼、聖体礼儀なのだ。「尊体尊血」は「神からの贈り物」として回復された「この世」「世のいのち」へと私たちを導く入り口である。ゆえに「尊い」のだ。
これが本書を貫く著者の確信であり、同時に、古代教会から受け継がれてきた正教の核心である。
ティモシー・ウェア「正教会入門」(二〇一七年 新教出版社)
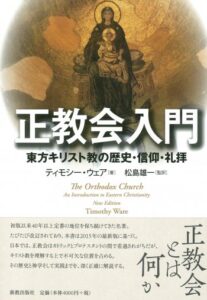
AmazonBIBLE HOUSE書店一覧
『正教会入門 東方キリスト教の歴史・信仰・礼拝』
・ティモシー・ウェア:著
・松島雄一:監訳
・新教出版社
・2017年刊
・A5判 400頁
・4,400円
大変喜ばしく、かつ残念なのが本書である。もっか絶版である。しかし、正教会について何か確実な知識が必要になったとき、最初に参照すべき書としてぜひ広く知っていただきたく、紹介した。また本書の翻訳には監訳した私を始め三人の正教会司祭、四人の信徒が協力した。著者はオックスフォード大学で長く正教を研究する碩学であると同時に、正教会の主教でもある。内容は広く正教会の歴史、信仰、奉神礼、霊性の各分野に及ぶ。原著は “The Orthodox Church” 1963年初版。世界中の正教に関心を持つ人々に読み継がれた定番図書である。再版が待たれる。
「キエフ洞窟修道院聖者列伝」(三浦清美訳、二〇二一年、松籟社)
ルーシ(ロシア、ウクライナの古名)の時代、十一世紀なかばにキエフのドニエプル河畔に創設された洞窟修道院で祈りと斎(断食)の日々を送った修道士たちと、彼らを取り巻く人々の伝承集。十一世紀末から十三世紀始めにかけてまとめられた。文字通り「キリストに倣って」聖書を生きた人々の姿が活写されている。
前半は洞窟修道院を創設したアントーニイとその弟子フェオドーシイのエピソードである。隠修者アントーニイのもとに修道を志す人々が次々と集まり、「地上の天使、天上の人間」と称えられたフェオドーシイが修道院の基礎を整えていった。フェオドーシイは主イエスの「わたしは柔和で謙遜な者だから、わたしの軛を負いわたしに学びなさい(マタイ11:29)」という言葉通り、常に自分を低くし、「仕える者」として弟子たちに心を配った。重労働を率先して行い、パンを焼き、水が足りないと聞けば、即座に水くみに行き、薪が足りなければ斧を手に薪割りを始めた。のんびり食事をしていた修道士たちは修道院長の働く姿を見てあわてて仕事に加わったという。
一方、兄弟争いの絶えないルーシの支配者、公たちにも丁重に、親しく聖書に従う生き方を伝えた。大公位を兄から簒奪したスヴャトスラフ公には「あなたの兄の血の声がアベルのカインに対するそれのように神に届いている」と非難の手紙を送った。周囲は公の逆鱗に触れるのを恐れたが、フェオドーシイは「投獄であろうと死であろうと心の準備はできている」と歓喜に満たされていた。また、公の方もフェオドーシイが「神に似て正しい」ことを知り危害を加えなかった。それどころか数日後、修道院を訪ね、フェオドーシイの語る聖書の兄弟愛の話に感銘し、神を讃えながら帰っていったという。
この『キエフ洞窟修道院聖者列伝』には、師父への従順と真の謙遜、祈りと斎(断食)によって自らの罪を見、悔い改め、愛によってひたすら神の国を求める中世ルーシの修道の姿が生き生きと伝えられ、今でも正教修道文学の最重要な一冊として広く愛読されている。
今年二月、ロシアのウクライナ侵攻が始まったとき、キエフで司祭を務める友人はSNSでこう語った。「今まで見かけたことのない人がたくさん教会に来て、痛悔(懺悔の機密)を受けます。多くの人が、戦争が始まって、今まで自分が神の道から離れていたことに気付かされたと告白しました」。添えられた写真では、聖堂は跪いて祈る人々で埋め尽くされていた。痛悔し、血の滲むような祈りを捧げ、愛を実践したルーシの修道師父たちの「キリストにならう」姿が今も生きている。クリスチャンとして生きるなら、どのような時代にあっても、とりわけ今、その姿に立ち帰るべきである。