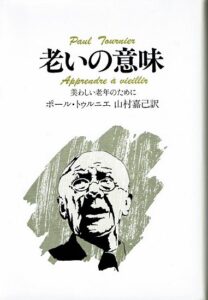P・トゥルニエ著『老いの意味』―美わしい老年のために
【固定型】
アドラーは(フロイトが主張した)性本能の重要性は否定していませんが、それを人間の精神作用の唯一の原動力と見ることには賛成していません。彼は本能(老年期の生きる力)を〝権力意志〟と名付けます。人間はそれによって自らを確認し、他人に照らして自分を測り、競争心を持ち、障害を打ち破り、行動によって社会生活に勝利を収めることができるというのです。(中略)(このタイプの人間)《自分の地位にしがみつき》・《職業上の引退を拒み》・《家庭や社会にあっていつまでも指導者になりたがり》(中略)《自分の意見は絶対的なもの》として、《服従され尊敬されるように要求》する人は、自分の限界を認めようとしない人、すなわち、老いのために行動や支配の世界はもはや無力になった今も彼は無意識にその保証を求めます。つまり彼らは過去の栄光を埒も無く物語ってみたり、権威主義の中に閉じこもったり、若者たちを非難したりするのです。
【無気力型(引きこもり型)】
もう一つの老人の例、それは無気力と無関心に落ち込んだ人ですが、(実は)彼は自分の権力本能を押し込めてしまっているのです。彼が活躍していた頃の職業や、成長した子どもの教育などの直接的対象に向けていた、この本能のやり場が今はなくなり、もはや何ものにも興味を持てず、自分の権力意志にさえ気が付かなくなっているのです。ただ残るのは、後悔、苦々しさ、頑固といった権力意志を裏返しにしたイメージばかりです。進化する力がないのですから退化するばかりです。
《硬化…苦渋…閉鎖的性格、これらは未完成な人間のしるしだ》と、デュルクハイムは書いています。
【冒険型】
しかし第三の型の老人もいます。それはこの権力意志の昇華に成功した人の場合です。つまり、本能衝動の他の対象への転換に成功した人です。(中略)生命活動とは単に拡張、攻撃、支配だけではありません。それはまた、愛、受容、交換、伝達でもあるのです。活動期には職業とか社会とか、或いは軍事とか経済とか、さらには知的、文筆的な成功などによって人は力を獲得していますが、老年になれば今度は心情によって、すべての受容によって、あるいは寛大さや無私の心によって、力を示すことができるのです。」(340―342頁)
私はこれを読んで二人の隠退牧師のことを思い起こした。いずれも〝生涯現役〟と称して九十代半ばまで教会指導者の地位に留まっていたものの、その手法は第一世代の教会指導者にありがちな強権主義であり、後継者問題をめぐって教会はほぼ分裂状態、また信徒の実際はA・グリューンが『従順という心の病い』(ヨベル)の中で示唆した従順・無気力型で、とうてい〝みんなの教会〟でも〝地域に開かれた教会〟でもないのである。
私はふと思った。
戦後の日本のキリスト教界は伝道、伝道。あるいは聖書知識の取得や神学的研究に力を注ぎながら、肝心のキリスト教的人格形成とその〝社会化〟である〝人間的成長・成熟〟というテーマは殆ど等閑視されてきたのではないだろうか。というのも一九七〇年代、日本にライフサイクルなる概念が導き入れられて以来〝アイデンティティ〟問題は、臨床精神医学や発達心理学において必要不可欠の要素として認識されてきたにも関わらず、神学校教育にはこうした面への関心は著しく欠けているように思えるからである。(例:E・エリクソンの人間の八つの発達課題)
P・トゥルニエ著『生きる意味』―来日講演集
前者の要点は〝捕らわれの身で生んだ私の子オネシモ〟と〝オネシモの負債を私が負う〟という表現であり、後者は洗足式に至る記述である。
この捕らわれの身で、私の子オネシモを生んだという表現は、老人期のGenerativity(神谷美恵子氏の訳では生殖性と訳されるもので、子孫や自分が造りだしたものを世話し、後世に残すこと)であり、後者はとりなしの祈りである。世に残される者たちへのとりなし、つまりCareの概念である。実際多くの人々は仕事から解放されると、残された能力を何らかの社会活動(ボランティア精神)によって世に還元しようとする。
しかるにどうだろう〝生涯現役〟と称するキリスト者の実際は【固定型】であり、後進に道を譲り〝育てること〟も有終の美を飾るべく引退して〝道を譲ること〟もできず自己顕示欲を昇華できないでいる。
また【引きこもり型】に関して言えば、トゥルニエは「老年期もまた霊的成長の時であり狭い自己愛の世界から無私の愛に成長することができるのです」と主張している。
つまり成長から成熟への発展である。
言うまでもないことであるが、【固定型】はその人の愛が〝利他性〟に到達しない自己中心性の〝自己愛〟に留まっていることを意味する。そして、老人の美しさはその〝表情〟とりわけ〝顔貌〟に現れる。私が本書の聖文舎版を紹介するのは表紙のトゥルニエにその美しさを感じるからである。
トゥルニエは「ヨーロッパのデカルト文明は、見えるものを見えないものに優先させ、計量できるものをないものに優先させ、することを存在(あること)の優位に立たせ、〝ホモ・ファベル(工作人、物・道具を作る)〟を〝ホモ・レリギオシス(宗教的人間)〟の優位に立たせてきた。これは老年の生活には都合の良くない風土である。
今日老人たちは、自分たちが価値を認められておらず、居心地が悪い、また自分たちが役立たずだと思って苦しんでいる。」と論じているが(P・トゥルニエ著『生の冒険』一三八頁)、現代社会はデカルトを選ぶことによって、本来社会の宝とも呼ぶべき老人の存在価値を見失ってしまっているのでないだろうか。
H・ナウエン著『闇への道・光への道』―年齢をかさねること

教文館Amazon書店一覧
『闇への道 光への道』
年齢をかさねること
・ヘンリ・J.M. ナーウェン、ウォルター・J. ガフニー:著
・原 みち子:訳
・こぐま社
・2000年刊
・小B判158頁
・1400円(税別)
こうした若い人たちへの声かけ・応援という〝社会化〟こそが、より人間的な社会の実現のために老人に与えられた〝社会的使命〟であり、トゥルニエが、今こそ〝老人の出番〟と呼んでいる実際例である。
※引用文中の傍線、括弧書きは筆者によるもの
※紹介した本は品切れ、絶版など現在入手しにくい状態です。キリスト教系図書館などのご利用をおすすめします。