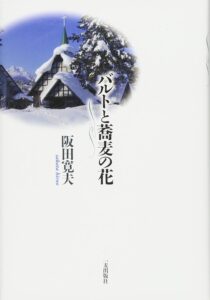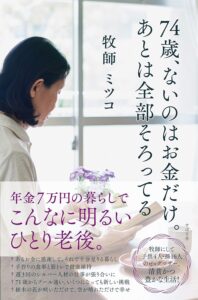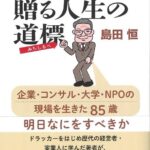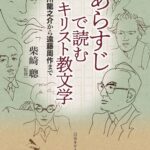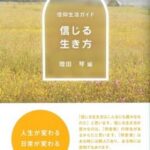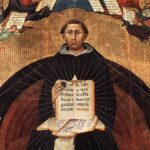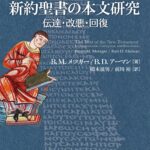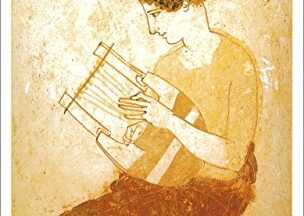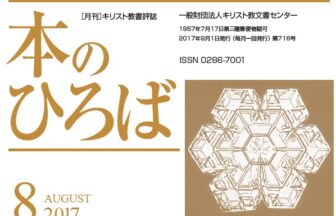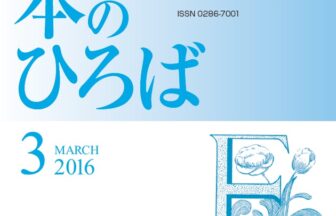『母の詩 河野 進 自選集』河野進/著
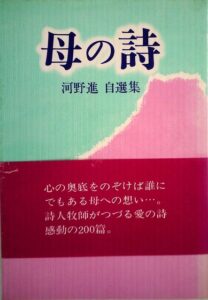
『母の詩 河野 進 自選集』
・河野 進:著
・柏樹社
・1980 年
・四六判 124 頁
・1,100 円
※現在は販売しておりません。図書館のご利用をお薦めいたします。
ぼくは神学校へ行って 牧師になると言った 父は怒りで 絶句し 親戚はあざけり ののしった 母は涙を流しながら 一言いった これだけ反対されるのですから 生涯やり通しなさいよ ぼくは母の涙ながらのはげましを 今も はっきりおぼえている(河野 進 はげまし)
高校二年生の秋、「神学校に行って牧師になりたい」と両親に告げました。父は黙っていましたが、母は怒り出し「親の期待を裏切るつもりか。牧師になっても貧乏生活が続くだけでしょう」とののしりました。長男のわたしは親の期待に応え大学に進み、大企業に就職して両親の面倒をみるつもりでした。それが突然崩れたのです。「牧師になりたい」のひと言で……。
牧師になってからも悩むことがありました。「お父さんは牧師さんですか?」「イイエ!」、「クリスチャンホームですか?」「イイエ!」答えるたびにこころが揺れ、痛みました。「親に対して信仰の導きもできない、牧師失格ではないか」そんな声が聞こえてくるのでした。
わたしの両親と妻の父は したしく交際の機会もなかったが 申しあわせたように 不治の病と自覚したとき洗礼を申し出た 主イエスの救いを信じてか 牧師である息子への最後のはなむけであったか どちらにしてもわたしは心から感謝した(河野 進 はなむけ)
詩集「母の詩」の作者河野進さんは日本キリスト教団玉島教会の牧師として長年伝道活動を続け、またハンセン病療養施設「長島愛生園」や「邑久光明園」での伝道や支援活動を行いつつ、こころの様を詩に託し最初の詩集「母の詩」(1980年)を発刊、続いて「おにぎりの詩」(柏樹社1981年)、「ぞうきん」(幻冬舎2013年)を刊行、多くの読者に感動と励ましを与えてきた詩人牧師です。
牧師となって30年あまり経った十二月のある夜、母教会の恩師から突然電話がありました。「キミ、ご両親がクリスマスに洗礼を受けたいと申し出てこられた」「教会に行っているのですか?」「いや」「それで洗礼はイイのでしょうか?」「本人が受けたいと言っているのだ。聖霊の働きがあったのだろう」
クリスマスの夜、恩師から再び電話がありました。「洗礼式は無事終わったよ。礼拝後のお祝い会でご両親が息子には親らしいことは何もしてやれなかったが、せめて最後に洗礼を受けることで息子孝行になればとあいさつされた。〝息子孝行〟だとね!」
高齢の両親が洗礼を受けたのは親不孝の息子への初めての、そして最後の〝子ども孝行〟だったのでしょうか。牧師としての無力さに苛まれつつも感謝の祈りを捧げたクリスマスの夜でした。
『バルトと蕎麦の花』阪田寛夫/著
鬼の面 つけたる老人 四人来て
我に罷めよと 連判状出す
北関東の山に囲まれた小さな町の教会のユズル牧師が詠んだ歌です。ユズルは農村伝道を使命とする神学校に入学しカール・バルトの神学に出会います。「歩き始めた赤ちゃんが、母親と手をつないで散歩に出た。この時、赤ちゃんが母親の手を固く握っている場合は、転ぶと手を離してしまう。逆に、お母さんが赤ちゃんの手をやわらかく握っている場合は、赤ちゃんが倒れそうになると、きつく握り直して引き上げてくれる。ゆえに〝わたしが神様におすがりする〟と思うのは、いかにも不確実だ。確かなのは〝神様が手を引いてくれること〟の方だ」ユズルなりのバルト理解でした。
神学校を卒業し都内の下町の教会に赴任しますが、ユズルがただ一人勧めて洗礼を受けさせた若い青年が自殺する事件が起こります。牧師にとって教会員の自死は再び立ち上がることができないほどの挫折と絶望をもたらします。ユズル牧師は教会を辞任し山峡の地の教会に転任します。数名の信徒によって設立された長い歴史のある教会ですが、就任八年目に牧師辞任の要求が突き付けられます。その折に詠んだのが先の歌です。
教会総会では「真面目で燃える信仰を持った老人が六年間二十人前後の信徒が少しも増えない、と怒り出した。それは牧師の使命感が足りないからであり、命を賭して伝道する気概に欠けるからだ。信徒が増えないから献金も集まらない」牧師への苛烈な批判が続きます。
我が裡の深き所にとどまりし
憎しみの小石 いつの日溶けん
ユズル牧師は教会を辞任し、蕎麦の産地で有名な隣県の農村の伝道所に転任します。
実は、ユズル牧師が辞任した30年後、わたしは都心の教会からその教会に転任しました。「鬼の面 付けたる老人」ではなく、信仰厚く心優しい教会員と四年間を過ごしました。聖霊の導きだったのでしょう、いまでは第二の「母教会」です。
さて、小説は転任した伝道所でのクリスマス礼拝の場面で終わります。「もう説教の後の祈りに入っていた。
ユズル牧師は一言一言はっきり神様に聞き取ってもらえるように、ちょっと短い舌で、力強く区切りながら祈っていた。『神さま。あなたの御子の、誕生を、心から、祝います。どうか私たちの、この、真中に、あなたが今日誕生してください』会衆は頭を下げたままゆっくり『アーメン』と和しただけであった」
牧師も失敗し、挫折を味わい、立ち直れないような状況に陥ることがあります。しかし、牧師のつたない働きや説教や祈りに「アーメン」と和してくれる教会員がいる限り牧師は立ち直ることができるのです。赤ちゃんのような私たちの手をしっかりと握ってくださっている方が会衆の「アーメン」に和してくださっているのです。
『74歳、ないのはお金だけ。あとは全部そろってる』牧師ミツコ/著
「まだやれるが辞め時で、そろそろはすでに手遅れ。辞めろと言われた時には死んだも同然」先輩牧師の言葉です。「まだやれる」と思いつつ70歳で隠退を考えました。その頃の夫婦の会話はもっぱら隠退後の生活。「隠退すると、謝儀はなくなるのね」、「そうだね」、「どうして生活するの?」、「年金だね」、「年金だけでやっていけるの?老後の資金は二〇〇〇万円が必要と新聞にありましたよ」「……」
近くの本屋である日『74歳、ないのはお金だけ。あとは全部そろってる』という本が目に留まりました。著者は「牧師ミツコ」とあり、神学校の同級生と結婚し、「牧師夫人」の役割を果たしながら四人の子どもを育て、牧師が病気で退任した後は教会の主任牧師として10年間教会の責任を持ち、退任後も協力牧師として働き続ける牧師とありました。思わず買って読みました。読後感は身も心もスッキリ、老後の生活は年金だけで足りる!
「牧師の家庭に生まれ育ったので、貧乏は慣れています。父は、家にお金がなくても、うちよりもっと困ってい5る人に分け与える、と思っていた人でした。そんな生活でしたので、あるものに感謝して、その中でどうにかする習慣が身につきました」と、牧師ミツコさん。「笑顔になれない時もあります。 そんなときは、無理はしません。落ち込むときは落ち込むし、泣きたいときは泣きます。…… 悲しいときや悔しいときは神様に祈ります。神様にいろいろぶちまけて、自分の感情を丸出しにします。そうすると、私はなぜ悲しいと思っているのか理由が分かり、す~っと冷静になれるのです」牧師ミツコさん自由で、自然体です。
「悩みがある時は、神様にお祈りして吐き出します。自分ひとりで背負っているとは思わない。半分は神様に託してしまいます。…… 私は聖人君子ではありません。いつでも悩み、迷い、苦しんでいます。泣くことも怒ることもあります。ありのままの自分を大切にし、生きていきたいと思います」
「明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労は、その日だけで十分である。」(マタイによる福音書6・34)とのイエスの言葉に生きる「牧師ミツコさん」74歳に完敗!「隠退牧師ジュン」84歳、いまだ迷える羊?