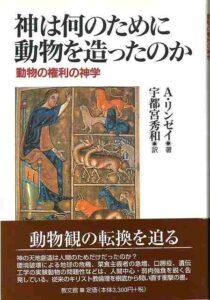産業革命以降、工業化と人口増加の両面から環境に対する負荷は高まり、二〇世紀後半には環境危機が叫ばれるようになりました。一九六二年、米国の生物学者・作家レイチェル・カーソンが発表した『沈黙の春』は、地球環境の危機を多くの人々に警告したことで知られています。
一九六〇年代以降の環境問題への関心は、欧米のキリスト教社会に対する批判も呼び起こしました。歴史学者のリン・ホワイトは、一九六七年の論文「私たちの環境危機の歴史的起源」(『機械と神』(みすず書房、一九九九年)所収)の中で、ユダヤ教およびキリスト教においては、人間は地球上のすべての生命に対して優越しており、一切の自然を利用するために創造されたという考え方が支配的であると批判しています。ホワイトによれば、キリスト教は「世界中で最も人間中心主義的な宗教」であり、「大きな罪
の重荷を背負っている」とされます。
ホワイトの論考は、神学者たちの間で、従来の神学に対する批判と新たな聖書理解を試みさせる契機となりました。「環境神学(ecotheology)」と呼ばれるこの新たな神学思潮は、人間以外の被造物への配慮や責任を考察します。エコロジーの視点から聖書を読むために適した書籍を三冊紹介します。
リチャード・ボウカム『聖書とエコロジー─創られたものすべての共同体を再発見する』

教文館AmazonBIBLE HOUSE書店一覧
『聖書とエコロジー──創られたものすべての共同体を再発見する』
・リチャード・ボウカム:著
・山口希生:訳
・いのちのことば社
・2022年刊
・四六判 364 頁
・2,420 円
ホワイトは、聖書の記述に依拠しつつ、キリスト教が人間による自然の過剰利用を助長してきたと批判しました。ホワイトの見解については比較的早い段階から、聖書学者らによる反論が寄せられてきました。たとえば、ドイツの神学者ゲルハルト・リートケは、一九七〇年代以降、旧約学を背景とした環境保護について論じています。
ボウカムもまた聖書学者の立場から、神の創造した世界における人間の役割を考察しています。ボウカムは、『ヨハネ黙示録の神学』や『イエスとその目撃者たち』(邦訳はいずれも新教出版社刊)などの著作で知られる英国の新約学者です。本書においてボウカムは、聖書全体が提示する被造世界についてのビジョン(ボウカムはこれを「被造物の共同体」と呼びます)を明らかにしています。ボウカムの理解によれば、創世記一章における「地を従わせよ」「あらゆる生き物を治めよ」との記述は、人間が地球上のすべての被造物の管理者・監督者になるようにという促しではなく、また人間による支配を責任ある「スチュワードシップ(受託者責任)」と理解する従来の見方も不十分です。ヨブ記をはじめ、創世記以外の聖書箇所では、人間もまた被造世界の一員であることが示されており、被造物の共同体のメンバーは、生命と繁栄に共通の利益を持ち、創造主を讃えるという同様の目的を持っているため、相互に依存し合っています。
ボウカムによれば、イエスの死は被造物全体の苦しみや滅びを分かち合ったことを意味しており、人間の贖いだけに焦点を当てたものではありません。キリストは十字架によって全被造物を和解させ、その復活によって万物を刷新します。教会が宣べ伝える和解には、神との和解だけでなく、神が創造したすべての被造物との和解も含まれることになります。
本書は、講演をもとにしているため読みやすいですが、ボウカムが提示する聖書の解釈には多くの驚きがあるでしょう。
サリー・マクフェイグ『ケノーシス─大量消費時代と気候変動危機における祝福された生き方』

教文館AmazonBIBLE HOUSE書店一覧
『ケノーシス─大量消費時代と気候変動危機における祝福された生き方』
・山下章子:訳
・新教出版社
・2020年刊
・A5 判 398 頁
・4,400 円
フェミニズムの分野でも早い段階から、環境について議論されてきました。一九七四年、フランスのフェミニストであるフランソワーズ・ドボンヌは「エコフェミニズム」という呼び名を提唱しました。フェミニズムの環境問題への注目は、開発至上主義による自然の搾取と、男性による女性の支配には連関があるという視点に由来します。
エコフェミニスト神学者のマクフェイグは本書で、環境危機は経済(特に大量消費社会)と密接にかかわっていることを指摘し、この社会には人生の目的を「消費すること」と捉える「消費主義」という「異教」が蔓延していると言います。環境危機を乗り越えるためには、これまでの生活のあり方を変える必要がありますが、それは容易ではありません。
ここでマクフェイグは、キリスト教会が「回心」と呼ぶ行動の変化に着目します。マクフェイグによれば、回心は私的な聖化にとどまらない、公的な領域への参与を意味します。取り上げられるのは、ネイティブ・アメリカンや黒人奴隷の正当な扱いを主張したクエーカー派の伝道者ジョン・ウルマン、ナチスに占領されたパリの人々に寄り添って餓死した思想家シモーヌ・ヴェイユ、そしてカトリック労働者運動の創立者ドロシー・デイの回心です。三人の回心には、いずれもその視線を自分から他者へと移す「普遍的自己」への変化があるとされます。マクフェイグによれば、宗教は単に「私と私の幸せ」に関するものではなく、人を個人主義から共同体へと動かすものです。ここからマクフェイグは「ケノーシスの神学」を提唱します。ケノーシスとは、フィリピの信徒への手紙二章五~八節にあるキリストの自己無化・自己空化のことですが、私たちもまた自己を空しくすることで、他者(すべての被造物)と自己を隔てる境界がなくなり、他者への愛に生きることになります。このようにマクフェイグによれば、個人レベルでよく生きることは、政治レベル・地球レベルでよく生きることと並び立つものです。
環境問題について、信仰に基づき自らの行動をどう変えるのかが問われる一冊です。
アンドリュー・リンゼイ『神は何のために動物を造ったのか──動物の権利の神学』
人間以外の被造物である動物も、エコロジーの観点から考えることができます。動物の動物的地位について考える動物倫理は、一九七五年にオーストラリアの哲学者ピーター・シンガーが著した『動物の解放』を契機に発展してきました。シンガーは、感覚を持つ動物は、人間と同じく平等な配慮に値すると主張しました。
本書(原題『動物神学』)の著者である、英国国教会司祭で神学者のアンドリュー・リンゼイは、人間と動物は道徳的には平等であるという点でシンガーに同意しますが、人間は創造において特別な地位を与えられ、「独自性」を有すると考えます。リンゼイにとって人間の独自性とは、人間だけが理性を与えられており、また神との関係を持ちうるといった伝統的な神学的理解にとどまるものではありません。人間は世界の贖いと解放に関して「神と共に参与する者、共にはたらく者」として人間性を発揮し、他者に仕える能力がある点で動物と区別されます。そしてリンゼイは、キリストの模範があるからこそ、人間には「キリストに似た支配と奉仕」、すなわち「より高いもの」が「より低いもの」に対して犠牲を払うことが求められており、脆弱なものに仕える者は、キリストにも仕えるのだと主張します。またリンゼイは、シンガーが提唱したような、人間と同じく動物の利益を平等に配慮する行動様式(「平等パラダイム」)を超えて、動物を利用せず、そのことで人間の生活に不利益が生じてもそれを耐える犠牲的な行動様式(「寛大さパラダイム」)を提案します。リンゼイによれば、菜食主義の実践は「寛大さパラダイム」の一例であり、聖書が理想とするものであるとされます。
本書は、聖書における人間と動物の地位や両者の関係性について、そしてキリスト者として動物をどのように配慮すべきかを考えさせてくれる一冊です。
おわりに
環境をめぐる神学的議論は現在も発展を続けています。世界改革派教会共同体(WCRC)や世界教会協議会(WCC)は今世紀に入り、文書や宣言を発出しました。またカトリック教会でも、教皇フランシスコが「回勅 ラウダート・シ─ともに暮らす家を大切に」(二〇一五年)と「使徒的勧告 ラウダーテ・デウム──気候危機について」(二〇二三年)を公布しています(いずれもカトリック中央協議会から書籍として刊行されており、ウェブサイトからも読むことができます)。
世界における環境神学の議論に比べ、日本からの発信は多くはありませんが、今後の展開を期待させる動きもあります。関西学院大学「キリスト教と文化研究センター」が二〇一九~二〇二三年度に行ったプロジェクト研究「エコロジカル聖書解釈」の成果が『エコロジカル聖書解釈の手引き』(関西学院大学キリスト教と文化研究センター編、キリスト新聞社)として今年三月に刊行されました。キリスト教主義学校の授業や教会学校での使用を想定しており、セクションごとに議論のための問いかけが置かれ、考えるためのヒントに溢れています。
エコロジーの視点から聖書を読むことは、私たちの生活に変革を迫りますし、またこれまでの聖書の読み方が変わるようなスリリングな体験になるはずです。
今回紹介した書物をとおして、聖書との新たな出会いがあることを期待したいと思います。