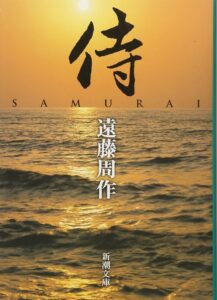フランス留学中の青年遠藤周作(一九二三~一九九六年)を捉えたのは、将来自分の小説をどのような技法によって書くべきかという問題でした。何を書くべきかについては、遠藤はすでに考えたことがありました。欧米のキリスト教を日本の精神風土に合わせて受容すること、そのためには人間内面の深部を凝視すること、それが遠藤が書こうとした内容でした。問題は、それをどのような技法によって書けばいいのか、ということでした。
自分の小説を書くためには他人の小説を読むしかありませんので、彼は多くの作品を次々に読破していきました。そしてある日、イギリスのカトリック小説家グレアム・グリーンについての研究書を読んだとき、ついに膝を打つ瞬間が訪れました。グリーンから遠藤が決定的に学んだこと、それは探偵小説の技法を用いてカトリック信仰をテーマにした作品を書くということでした。
探偵小説とは、言うまでもなく現場に痕跡を残した者と、その痕跡を追いかける探偵の物語です。で、遠藤は知っていました。人が人に出会うとき、必ずそこには何かの痕跡が残る。同様に、人と神が会ったときも、そこには神が残してくれた痕跡があるはずだと。欧米と日本の精神風土との差異に悩んでいた遠藤には、実はもう一つの悩みがありました。それは、自分の洗礼が「非自発的」であったことから生じたものでした。しかしながら、たとえそれが「非自発的」であっても、その洗礼によって神は遠藤の中に決して消すことのできない痕跡を残されたはずです。その痕跡を追跡することを、自分の小説は書かねばならぬ。その決心により、日本のカトリック小説家遠藤周作は生まれたのです。
遠藤周作の作品といえば、すでに読み慣れておられる方も多いかと思いますが、改めて遠藤の作品の骨組みは探偵小説的である、との視点で遠藤の作品を手に取られてはいかがでしょうか。まず以下の三作品を読まれてはいかがでしょう。
『おバカさん』
わけのわからぬ一通の手紙は、見知らぬ人が遠方から日本にやってくることを告げていました。「見るべき面影はなく、輝かしい風格も、好ましい容姿もない」あの人は、船の最下等席に乗ってきました。人々は彼のことを馬鹿にし、彼は多くの人に貶められましたが、彼は棄てられた人々の友になってくれました。
戦時中自分の兄に濡れ衣をきせて殺した上官たちを追いかける復讐心に燃える男がいました。この男自身も実は請負殺人者です。遠いところから日本に来たあの人は、この請負殺人者と一緒に居ようとし、その人のあとを追いかけて旅をします。また二人の日本人兄妹があの人の跡を追いかけていきます。ついにあの人は、請負殺人者が殺されかけた時、両手を広げながら自分がその攻撃を代わりに受け、深い湖の底に姿を消しました。しかしあの人探しに必死であった若い日本人の青年は、あの人が空の彼方に昇るのを見たような気がして、次のようにつぶやきます。
あの人は生きている。あの人は遠い国から、この人間の悲しみを背おうためにノコノコやってくるだろう、と。
『沈黙』
あの有名な江戸川乱歩によれば、一流の探偵小説であるためには次の三つの要素が必要だそうです。まずは、不思議な事件が起きます。その事件は普通にありうるようなものではなく、一般的な考えでは信じがたい事件でなければなりません。また、その事件の真相を究明するために、人と人の間では緊張度の高いサスペンスが繰り広げられなければなりません。そして、もう一つの要素は、その探偵小説の結末が読者の予想を超えるものでなければなりません。小説を読みながら途中で誰が犯人なのかが見破られるような探偵小説なら、多分誰も最後まで興味津々と読もうとはしないでしょう。
この乱歩の話を頭に置きながら、遠藤の代表作ともいうべき『沈黙』を読んでみてはどうでしょう。ローマにある報告が入る、その内容は信じがたいものだった。『沈黙』の書き出しがそのようになっていることに改めて気づかされることになります。その信じがたい事件の真相を調べるために、ロドリゴという司祭が吉次郎という助手を連れて日本に派遣されます。まるで名探偵シャーロック・ホームズにワトソン博士という助手がいたように。(吉次郎はしかし有能な助手ではなく、その真逆でしたが。)
それから追いかける・追いかけられるの追撃戦が始まります。ロドリゴは棄教したと知らされたフェレイラ神父の跡を追いかけ、奉行の井上はロドリゴを捕らえるために追いかけます。
ついにロドリゴは逮捕され、踏み絵の前に立たされます。しかし、そこで読者の目を疑わせるようなことが起こります。なんと、踏み絵のあの方がロドリゴに向かって「踏むがよい」とおっしゃられたのです。しかし、本当の不思議な結末、読者の予想をはるかに超える結末は、さらに後ろに書いてあります。まるで付録のように小説の末尾についていて、読者にあまり読んでもらえないといわれる部分─実は遠藤はこの事実にかなり不満をもっていたそうです─、すなわち「切支丹屋敷役人日記」にこそ、『沈黙』の真の結末が隠されています。必ず読んでみてください。
『侍』
仙台藩の下級武士支倉常長は、慶長一八年(一六一三年)のある日、月ノ浦(現在の石巻市)を船出しました。ノベスパニヤ(今のメキシコ)との通商交易の道を開けという、主君伊達政宗の命によるものでした。しかし、任務は失敗に終わり、常長は日本にむなしく戻ってきました。慶長遣欧使節団を率いたこの支倉常長の人生を基にして、遠藤は長谷倉六右衛門という侍の一生を物語る『侍』を書きました。
侍は太平洋を横断してメキシコの総督に会い、仙台藩との交易を頼みましたが、総督はそれはスペインの王様が決めるべきだと言いました。侍は再び大西洋を渡りスペインに入りましたが、カトリック国の王様である教皇の許可が要るということがわかり、今度はローマのバチカンまで行くことになります。そこで侍は、自分の任務を達成するならという覚悟で、「形だけ」のキリスト教の洗礼まで受けます。
しかし侍の願いは受け入れられず、彼は再び長い長い旅をして、ようやく日本に戻ることができました。故郷を離れてから七年もの歳月が流れたあとでした。しかも、戻ってきた日本はキリシタン禁止の時代に一転していて、侍は「邪宗門」の洗礼を受けたことが問題視され、評定所への出頭を命じられます。そして、侍は処刑を待つ身になります。
侍が日本を離れたのが不思議な運命によるものであったように、また不思議なことに、そのときようやく侍は、自分が「形だけ」で受け入れたキリストの姿が目に入ることになります。そして、自分とは何の関係もないはずだったそのキリストについて、今は、なぜか隔たりを感じなくなり、さらにはそのキリストが自分に似ているような気さえしたのであります。侍は地上の王様に会うための旅をつづけました。しかし、その旅で彼が実際に追いかけていたのは、地上の王様ではなく、天上の王様だったのでした。
こうした神秘について、遠藤は『侍』の中である司祭の口を借りて、つぎのように告白します。「洗礼という秘蹟は人間の意志を超えて神の恩寵を与える……彼ら〔日本人信徒〕の受洗に万が一、そのような不純な動機があったとしても、主は決してその者たちをその日から問題にされない筈はない。彼らがその時、主を役立てたとしても、主は彼らを決して見放されはしない」。
人は自分も知らないうちに、神の痕跡を追跡するものである。しかし、人がいつか、ふと後ろを振り向いたとき、そこに、人は自分を必死になって追いかけておられる神を見つけることになる。「探偵小説家」遠藤周作のメッセージはそこにあるのではないか、と私は考えております。