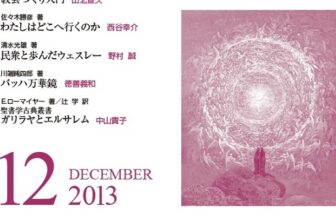クリスマス。冬至に近く昼の時間が一番短い「闇」の時期にもかかわらず、この祝祭によって、明るく、あたたかいものとして、私の心に感じられる。そこにはこれまで過ごしてきたクリスマスの、心に残る経験が影響している。
それだけに、今年、2021年のクリスマスはどのように祝い、過ごすべきか。「いつものように」を超えて、いっ
そう意義深く祝うにはどうすればよいのか。アドヴェント、クリスマスの祝い方を省みる際に助けとなる書物をご
紹介したいと思う。
聖書はイエスの誕生について何を語っているのか。授業でも常々、「聖書についてのお話し─絵本や物語─で、聖書のことを分かっているつもりになってはいけない。聖書そのものを丁寧に読むと、それまで思っていたことと違うことを発見する」と言っているが、クリスマスの意義を考えるためには、聖書を読み直すことが不可
欠である。そのための書物としてJ・D・クロッサンとM・J・ボーグの共著『最初のクリスマス 福音書が語るイエス誕生物語』(淺野淳博訳、教文館)を挙げたい。
『最初のクリスマス』福音書が語るイエス誕生物語
そして、紀元後一世紀のローマ帝国と いう歴史的背景の中で、とくに「ローマ帝国神学」とも呼べる思想に対抗し て福音書物語が書かれていると論じる。 「神の子」「救い主」などは初代皇帝アウグストゥスに献げられた敬で、 その誕生も「神的」なものと考えられていたこと、そしてそのような「神学」 の背後には、アウグストゥスの軍事的勝利(著者たちによれば「暴力」)による「平和」があったことが挙げられる。
イエス誕生の物語は同じような語彙を意識的に用いて、皇帝崇拝の神学に抵抗を示していると、著者たちは読み解く。「平和」は暴力によってではなく、正義によってもたらされるべきであり、それを実現するのが、イエス・キリストなのだとする。
著者たちは、 ローマ帝国神学の文献から根拠となる 引用をするが、同時に、イエスに関す る記述がヘブライ語聖書(旧約聖書) の伝統に基づいていることにも紙幅を 割いている。そして、最後には、クリスマスとアドヴェント(待降節)をどのように過ごすべきかという勧めの章(「第九章 世に満ちる喜び」)を置いて、この書のもう一つの目的を果たしている。 これは、聖書の物語に対する「イデオロギー批評」であると言えるだろう。私の方法とは異なるが、「政治的」な 主題に関心を持たずにイエス誕生の物語を読むならば、「半分を見過ごすこ とになるのです」という指摘(二四七 ~二七八頁)には心から賛同する。私たちは生活と政治が密接に関わっていることを知っており、私の「平安」は 世界の「平和」と繋がっているからで ある。
『毎日の読書「教会の祈り」読書第二朗読 第一巻 待降節・降誕節』カトリック中央協議会
全九巻からなるこのシリーズは、以前は「聖務日課」と呼ばれていた「教会の祈り」の中の「読書」(かつての 朝課)で、第一朗読の聖書と共に読ま れる教父や教会著作家、教会の文書から選ばれた朗読箇所を集めたものである。第一巻には、エイレナイオスをはじめとして、エウセビオス、ヨハネス・ クリュソストモス、アウグスティヌス等の著作から、また、第二バチカン公 会議の文書からも選ばれた朗読が収められていて、直に、著者たちの声に触れることができる。
私は、毎年、アドヴェントを迎えると「聖ベルナルド修道院長の説教」(待降節第一水曜日、一六~一八頁)を、クリスマスには「聖レオ一世教皇の説教」(主の降誕〈一二月二五日〉、七七 ~七八頁)を読む。 ベルナルドは、来臨には三種のもの があり、第一の来臨─ イエスの誕生 と地上での生活、最後の来臨─ 「再臨」というよく知られているものの他 に、この二つを結び、この二つの意義を信仰者たちに体得させるものとして「中間の来臨」の重要性を説く。それは、イエスが信仰者の「ところに来て住 む」ことであり(ヨハネ一四・二三)、 これによって、信仰者がイエスの「生き写しとなる」のだとする(一コリン ト一五・四九)。
レオ一世は、その説教で、イエスが 人間性をまとったことによって、人間は新しい被造物となり、「神の本性にあずかる者」となったと言う。その上 で、キリストの誕生にあずかって、キリストと共に生きる者(エフェソ二・ 五)、バプテスマによって聖霊の住まいとされた者としてふさわしい生き方をするようにと勧める。 古代や中世の著作には独特のレトリックがあるので、読み慣れない内は何が言われているのか、正直よく分からないところもある。それでも、キリスト教の歴史においてどのように考えられてきたかを知ることは重要であるし、今日においても意義あることが語れていると感じるものに出会うこと ができる。この二つの朗読に言われているような、キリストを心に宿しキリストと共に生きようとする信仰のあり方は、後のジョン・ウェスレーの思想 にも受け継がれていると、メソジストの伝統にある(と自認する)者としては感じる。
イーヴァントの時代も、現代も、基本的な問いは変わらない。説教すること、礼拝すること、祈ること、それら はすべて戦いだ。私たちはこの一年の 間、礼拝を献げられる自由が当たり前 でないことを知った。疫病の蔓延は容 赦ない。礼拝堂における公開での礼拝 を休止せざるを得ないこともありうる。しかし、安易にその道に逃げないよう にもしたい。私たちは今誰の目を気に し、誰に気を遣っていのるのか、もう 一度考えたい。ここにも戦いがある。
イーヴァントは、悔い改めは決して自分自身との関係の問題ではないと訴える。悔い改めは神と世界との対立における、神の世界への侵入箇所だ。「悔い改めたひとりのキリスト者が神を信じない人々の中にいるということは、その神を信じない人びとの住む領域に傷口が開いたということである」。教会は神とこの世界との戦いの現場だ。説教すること、祈ること、礼拝すること、それらはすべて戦いの業である。神の業が今ここでなされていることを確信したい。
『さんびかものがたりII この聖き夜に』 アドヴェントとクリスマス の歌 川端純四郎:著
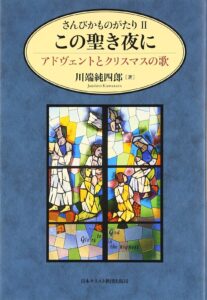
『さんびかものがたりⅡ この聖き夜に』
アドヴェントとクリスマスの歌
・川端純四郎:著
・日本キリスト教団出版局
・新教出版社
・2009年
・四六判258頁
・2640円
著者は、新約聖書の研究者、ブルト マンの著作の翻訳者として知られ、J・ S・バッハの音楽に造詣が深く、平和を求める市民運動でも活発に活動しておられた。私は、日本基督教団讃美歌委員会でご一緒したことが心に残っている。このシリーズの執筆中に、「今は一次資料にインターネットでアクセスできる」と、うれしそうにお話ししておられたことを思い出す。現代の利器も利用して、著者は、『讃美歌』 に収められている歌が、どのような状況で、どのような契機で作られたのかを明らかにしていく。
新型コロナ感染症によって不安や分断を経験し、また、罹患された人とそ の家族には身体的・精神的苦痛が与え られたこの二年間を思うと、フィリッ プ・ニコライの二つの歌「『起きよ』 と呼ぶ声」(二三〇番)「あかつきの空の美しい星よ」(二七六番)の解説が心に迫ってくる。これらはニコライが 牧師を務めていたペンナの町がペストに襲われ、ニコライが毎日数十人の埋葬を執り行う中で生まれたとされる。 ペストが去った後の一五五九年出版された『永遠の命の喜びの鑑』にこの二曲は収められている。
著者の解説によれば、厳格なルター派の牧師であるニコライがこれらの歌を生み出したのには、カンタベリーのアンセルムスや、上述のベルナルドの著作に触れていた影響があると考えられる。神秘主義的な神やキリストとの「合一」、「結婚」のメタファーが用いられているのも、納得できる。 圧巻は「きよしこの夜」(二六四番) の解説であろう。一般に流布している説を検証し、一八一八年の初演のさらに二年前、一八一六年に作詞されたと明らかにした上で、六節あった原詞の内、日本では歌われていない節の訳を載せる。
その背景に戦争の終結があったこと、それゆえに、「きよしこの夜」は「平和の賛歌」、ヘブライ語聖書の父祖たちの時代に約束された平和が実現したのがクリスマスであると歌う、「政治的」な歌であったことを説得的に示している。 「地に平和」はクリスマスの重要なテーマである。クリスマスに聖書を読み教会の伝統を受け継ぎ賛美歌を歌う 私たちは、キリストと共に生きる者として今年のクリスマスにどのような「平和」を求めるのか。これらの書物を読んで改めて思い巡らせたいと思う。