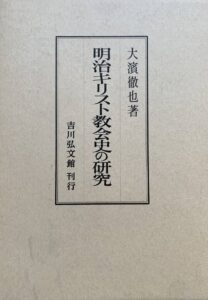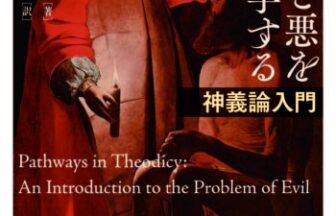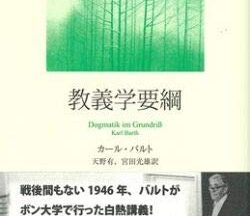筆者に与えられた課題は、「日本キリスト教史」を学ぶ上で手引きとなる三冊を紹介することである。ただ、キリシタン史研究に遡る膨大な蓄積から選定することは難しいため、ここでは筆者が専攻し、研究史を跡付け得る日本プロテスタント史を中心に筆を進めたい。
大濱徹也『明治キリスト教会史の研究』
昨年暮れに上梓した拙著『近代日本のキリスト者─その歴史的位相』(聖学院大学出版会、二〇二〇年)でも指摘したように、日本プロテスタント史研究は、その先蹤者・隅谷三喜男氏の課題意識に促され、「近代精神の淵源」たるプロテスタンティズムの思想的・社会的影響力を長らく問うてきた。如上の志向はしかし、西欧近代批判の浸透に伴い相対化され、今や研究の主流は、教会やキリスト者の「戦争協力」ならびにその「天皇制」や植民地支配との親和性を追及する論考に移行した感がある。
ただし前者の視座は、理念としての近代に引きずられるあまり、時代を生きたキリスト者の把握がやや観念的であり、また後者の場合、論者の依拠する価値観やその解釈枠組みが前面に押し出されがちなため、いささか外在的な「批判」に陥っている憾みがある。
こうした研究状況を乗り越えるには、近代日本におけるキリスト者とその信仰・思想を、時代社会をふまえて内在的に解き明かし、その具体的な相貌を積み重ねていくことで、近代日本という歴史的な場に根ざしたキリスト者の実態を明らかにすることが枢要である。
如上の基礎作業を遂行する上で、大濱徹也氏の『明治キリスト教会史の研究』(吉川弘文館、一九七九年)は、まず参照すべき文献である。氏は本書において、西上州、滋賀県、北海道空知という特色ある地域を中心に、明治前期におけるプロテスタント教会の形成過程と構造を分析した。そのまなざしは、時代の過渡期に輩出した種々の結社や民衆宗教と同じ地平でキリスト教を検証し、生活の場における教会とキリスト者の存在形態を凝視する点で、本書以前にしばしば見られた歴史叙述、たとえば明治国家をめぐる「受難」と「抵抗」の歩みとして描かれる「キリスト教史」や、あるべき「信仰」の立場を設定しそこからの距離を測ってキリスト者の「限界」を指摘するような論調とは一線を画していた。
本書で大濱氏が力説するのは、明治初期プロテスタント教会の基層に、平信徒が「家」を場として形成した聖書集会が存在するという事実である。その道統を継ぐものとして内村鑑三のいわゆる「無教会」を評価する氏は、後にこの視点を深め、教会設立の母胎となった平信徒集会をキリシタン時代のコンフラリアに重ねて問い、無教会集会を蓮如以来の寄合や講組の系譜に位置づけた(大濱「キリスト教会と信徒組織」、『講座日本の民俗宗教』5、弘文堂、一九八〇年、同「日本のキリスト教会─その構造と特質」、『内村鑑三研究』二三号、キリスト教図書出版社、一九八六年五月)。こうした見方は、ヴェーバーやトレルチの類型論とは別個の視座に基づく「無教会」論を可能とするのみならず、一九六〇年代に遡及するキリスト教の土着化論に接続させ得る点でも興味深い。
なお大濱氏の教会史研究は、他に『鳥居坂教会百年史』(日本基督教団鳥居坂教会、一九八七年)があり、また氏と視点や着想が近い作品として、大江満『宣教師ウイリアムズの伝道と生涯─幕末・明治米国聖公会の軌跡』(刀水書房、二〇〇〇年)、森岡清美『明治キリスト教会形成の社会史』(東京大学出版会、二〇〇五年)、山下須美礼『東方正教の地域的展開と移行期の人間像─北東北における時代変容意識』(清文堂、二〇一四年)等を挙げることができる。併せて参照されたい。
ただし前者の視座は、理念としての近代に引きずられるあまり、時代を生きたキリスト者の把握がやや観念的であり、また後者の場合、論者の依拠する価値観やその解釈枠組みが前面に押し出されがちなため、いささか外在的な「批判」に陥っている憾みがある。
こうした研究状況を乗り越えるには、近代日本におけるキリスト者とその信仰・思想を、時代社会をふまえて内在的に解き明かし、その具体的な相貌を積み重ねていくことで、近代日本という歴史的な場に根ざしたキリスト者の実態を明らかにすることが枢要である。
如上の基礎作業を遂行する上で、大濱徹也氏の『明治キリスト教会史の研究』(吉川弘文館、一九七九年)は、まず参照すべき文献である。氏は本書において、西上州、滋賀県、北海道空知という特色ある地域を中心に、明治前期におけるプロテスタント教会の形成過程と構造を分析した。そのまなざしは、時代の過渡期に輩出した種々の結社や民衆宗教と同じ地平でキリスト教を検証し、生活の場における教会とキリスト者の存在形態を凝視する点で、本書以前にしばしば見られた歴史叙述、たとえば明治国家をめぐる「受難」と「抵抗」の歩みとして描かれる「キリスト教史」や、あるべき「信仰」の立場を設定しそこからの距離を測ってキリスト者の「限界」を指摘するような論調とは一線を画していた。
本書で大濱氏が力説するのは、明治初期プロテスタント教会の基層に、平信徒が「家」を場として形成した聖書集会が存在するという事実である。その道統を継ぐものとして内村鑑三のいわゆる「無教会」を評価する氏は、後にこの視点を深め、教会設立の母胎となった平信徒集会をキリシタン時代のコンフラリアに重ねて問い、無教会集会を蓮如以来の寄合や講組の系譜に位置づけた(大濱「キリスト教会と信徒組織」、『講座日本の民俗宗教』5、弘文堂、一九八〇年、同「日本のキリスト教会─その構造と特質」、『内村鑑三研究』二三号、キリスト教図書出版社、一九八六年五月)。こうした見方は、ヴェーバーやトレルチの類型論とは別個の視座に基づく「無教会」論を可能とするのみならず、一九六〇年代に遡及するキリスト教の土着化論に接続させ得る点でも興味深い。
なお大濱氏の教会史研究は、他に『鳥居坂教会百年史』(日本基督教団鳥居坂教会、一九八七年)があり、また氏と視点や着想が近い作品として、大江満『宣教師ウイリアムズの伝道と生涯─幕末・明治米国聖公会の軌跡』(刀水書房、二〇〇〇年)、森岡清美『明治キリスト教会形成の社会史』(東京大学出版会、二〇〇五年)、山下須美礼『東方正教の地域的展開と移行期の人間像─北東北における時代変容意識』(清文堂、二〇一四年)等を挙げることができる。併せて参照されたい。
鈴木範久監修『日本キリスト教歴史人名事典』
日本キリスト教歴史人名事典
鈴木範久:監修
日本キリスト教歴史大事典編集委員会:編
教文館
2020 年
B5 判982 頁
49500 円(税込)
ところで「日本キリスト教史」を構想する場合、まず、統計上に表れた「信徒」や「教会」を対象とする描き方がある。これを狭義の「日本キリスト教史」と呼ぶことができよう。一方、「日本のキリスト教徒は、現在、信徒数の上では国民総人口の一パーセントにも達しないほどの少数であるが、思想界・教育界・宗教界に与えたその影響には、多大なものがある」(高橋昌郎『明治のキリスト教』吉川弘文館、二〇〇三年)として、「日本キリスト教史」を広義に捉え、キリスト教が諸領域に及ぼした潜在的な感化の様を跡付けていく途もある。
この点、鈴木範久氏が監修した『日本キリスト教歴史人名事典』(教文館、二〇二〇年)は、狭義の「日本キリスト教史」のみならず、広義のそれを企図する上でも有益である。というのも本書は項目を「キリスト者」に限定せずに、何らかの形でキリスト教と交錯しその影響をこうむった人々を広く収めているからである。統計上は「信徒」でない彼らについての記述をひもとくと、キリスト教との邂逅によりもたらされた刻印が、各々の内で消え失せず、当人を規矩する何ものかとして息づいていることがうかがえる。彼らはその魂に刻み込まれたキリスト教体験に促されたり、着想・希望を与えられたりして、抑圧的かつ排外的な文化風土を改善すべく、それぞれの持ち場において努力した。そうした「非キリスト者」による実践をも本書は伝えている。
無論、「信仰告白」を決断し、一つの信仰共同体に主体的な参画を続けた「信徒」の歩みは重視されるべきであり、彼我の差は掘り下げて問われねばならない。しかし「日本キリスト教史」の間口を拡げ、キリスト教が周囲に築いた磁場にも目を注ぐ時、その叙述は隣接諸分野と相渉り、一層の光彩を発揮すると思われる。如上の構想を具現化する上で、本書は無数の手がかりを与えてくれるに相違ない。
この点、鈴木範久氏が監修した『日本キリスト教歴史人名事典』(教文館、二〇二〇年)は、狭義の「日本キリスト教史」のみならず、広義のそれを企図する上でも有益である。というのも本書は項目を「キリスト者」に限定せずに、何らかの形でキリスト教と交錯しその影響をこうむった人々を広く収めているからである。統計上は「信徒」でない彼らについての記述をひもとくと、キリスト教との邂逅によりもたらされた刻印が、各々の内で消え失せず、当人を規矩する何ものかとして息づいていることがうかがえる。彼らはその魂に刻み込まれたキリスト教体験に促されたり、着想・希望を与えられたりして、抑圧的かつ排外的な文化風土を改善すべく、それぞれの持ち場において努力した。そうした「非キリスト者」による実践をも本書は伝えている。
無論、「信仰告白」を決断し、一つの信仰共同体に主体的な参画を続けた「信徒」の歩みは重視されるべきであり、彼我の差は掘り下げて問われねばならない。しかし「日本キリスト教史」の間口を拡げ、キリスト教が周囲に築いた磁場にも目を注ぐ時、その叙述は隣接諸分野と相渉り、一層の光彩を発揮すると思われる。如上の構想を具現化する上で、本書は無数の手がかりを与えてくれるに相違ない。
関根清三『内村鑑三 その聖書読解と危機の時代』
最後に評伝の領域から一冊を紹介したい。関根清三氏による『内村鑑三 その聖書読解と危機の時代』(筑摩書房、二〇一九年)である。筆者が手掛けた書評(『内村鑑三研究』五三号、教文館、二〇二〇年四月)でも指摘したように、本書はまず、蓄積の厚い内村鑑三研究に新知見を加えた点で瞠目に値する。戦争をめぐる議論に限っても、たとえば内村の「日清戦争の義戦論」に向けられてきた批判に対し、創造的な揺さぶりをかけたこと、また、「イエスは、そもそも非戦論者であったであろうか」と問い進むなかで、内村の自覚の深化を推し量ったこと、そして「内村の戦争論の到達点」が、「戦争を起こさぬための事前の永い努力」として、「聖書の研究を通した社会の精神の変革」への志向にあった点を明らかにしたこと等、研究史への貢献は大きい。さらには「『十字架教』を奉じ」た内村が、一方で、「現代神学に通ずる非神話化の醒めた視点」を併せ持っていた可能性の指摘等、キリスト者・内村を問い直す上でも興味深い言及がある。
方法の面でも本書は新しい。内村は「聖書の読解に基づいて、現実の問題と斬り結ぶところに」「真骨頂があ」ると見る関根氏は、内村の「聖書の読解」の具体相を時代の中で詳らかにすることに傾注した。思うにこのアプローチは、キリスト者ことにプロテスタントの思想家を読み解く際に、おしなべて応用されるべきである。というのも聖書と主体的に向き合う者は、己をとりまく現実を、聖書に啓かれた眼で問い直し、聖書に基づく意味づけを経て取り込み、その上で然るべき言動を紡ぎ出しているはずだからである。したがってキリスト者の「社会認識」や「政治実践」を考察する場合には、時代への目配りに加え、当人が聖書のいかなる個所を、いつ、どのように読んだかを検証することも不可欠と言わねばならない。本書の方法に注目を促すゆえんである。
以上、筆者の関心もふまえ三冊を選んだ。日本プロテスタント史研究は、活況を呈する近代仏教史・神道史研究を前に、一見「地味」にも映ずるが、豊かな創造性を秘めている。拙文が研究深化の一契機ともなり得れば幸いである。
方法の面でも本書は新しい。内村は「聖書の読解に基づいて、現実の問題と斬り結ぶところに」「真骨頂があ」ると見る関根氏は、内村の「聖書の読解」の具体相を時代の中で詳らかにすることに傾注した。思うにこのアプローチは、キリスト者ことにプロテスタントの思想家を読み解く際に、おしなべて応用されるべきである。というのも聖書と主体的に向き合う者は、己をとりまく現実を、聖書に啓かれた眼で問い直し、聖書に基づく意味づけを経て取り込み、その上で然るべき言動を紡ぎ出しているはずだからである。したがってキリスト者の「社会認識」や「政治実践」を考察する場合には、時代への目配りに加え、当人が聖書のいかなる個所を、いつ、どのように読んだかを検証することも不可欠と言わねばならない。本書の方法に注目を促すゆえんである。
以上、筆者の関心もふまえ三冊を選んだ。日本プロテスタント史研究は、活況を呈する近代仏教史・神道史研究を前に、一見「地味」にも映ずるが、豊かな創造性を秘めている。拙文が研究深化の一契機ともなり得れば幸いである。