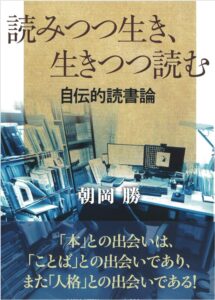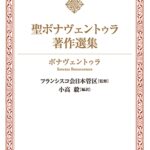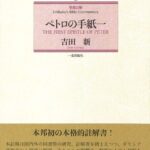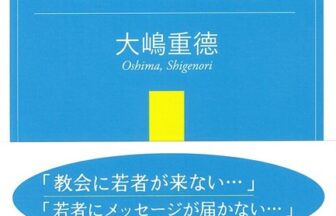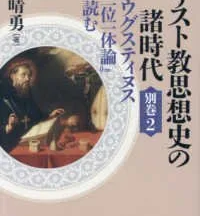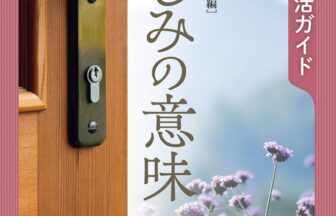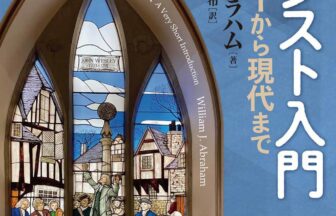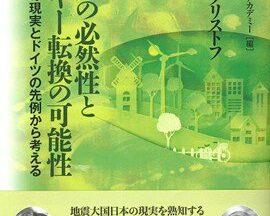豊かな読書経験への招き
〈評者〉石原知弘
本書は、著者が自らの歩みを振り返りながらこれまで読んできた書物について論じる、副題にあるとおり「自伝的読書論」です。執筆のきっかけは、友人たちとの会話の中でそうした本を書いてはどうかという話になったことと、ちょうどその日に出版社から同様の依頼が届いたことであったと「あとがき」に記されています。まず今この文章を記している私がその会話をした一人であることを告白しておきます。ですから評者としてはあまりふさわしくないかもしれませんが、著者の二〇代の頃からの読書遍歴を近くで見て学ばせてもらってきた者として、その恵みが本書を通して多くの方に届けられることをうれしく思います。
著者はこれまでの歩みを以下のようにおよそ一〇年ごとに区切りながら、それぞれの年代での読書のあり方を捉え、実際に読んだ本を紹介していきます。「少しずつ本と出会っていった一〇代から二〇代前半」「たくさん本を集め、読んだ二〇代後半から三〇代前半」「読まざるをえないものを読むようになった三〇代後半から四〇代前半」「土台が固まり、思考が動き始めた四〇代後半から五〇代前半」。年齢を重ねて立場や働きが変化していく中で書物との向き合い方も変わってきたことがうかがえます。紹介されるのは神学書が中心ですが、小説やノンフィクションの書物も取り上げられているので、広く多くの方が関心をもって読むことができるのではないかと思います。
多くの書物とともに、決定的な一冊との出会いということの大切さも本書から教えられます。特に神学校に入学する直前の一八歳のときに読んだという渡辺信夫先生の『教会論入門』は、大きな影響を受けた書物として、四〇代半ばを過ぎた頃の歩みについて述べられるところでもあらためてふれられています。こうした一書との出会いと長く続く対話も読書の醍醐味です。
自伝的な叙述が中心ですが、第一章には著者がどのように本を読んでいるか、本の探し方から買い方まで具体的な読書のための手引きが記されています。また最後の第七章では、今後の自分自身の課題図書などをあげるとともに、教会で本を読む文化を盛んにしたいという願いが述べられます。本書で多くの書物が紹介されるのは、自らの読書量を誇るためではなく、教会の仲間たちを豊かな読書経験へと招くためです。巻末には附録として「本書に登場してきた本たち」が一覧として挙げられ、読んだ本についてはチェックができるようにもなっているので、個人でも教会でも参考にしながら読んでいくことができます。
自伝とはその著者の人物像や大切にしていることが最もよくあらわれるものですが、本書についてもそのように言えます。著者はこれまで「読む」と題された書物を多く著してきました。同時に「生きる」という言葉が書名や副題についた著作も多くあり(ぜひ調べてみてください)、今回その両方が「つつ」で結ばれたわけです。著者は本との出会いは人格との出会いであると述べていますが、読者は本書を通してまさに著者の人格と出会うことでしょう。
もっとも、著者自身も本書の中で記しているとおり、自伝を記すというにはまだまだ若い年齢です。これからも読みつつ生き、生きつつ読んでいただいて、その得られたところを分かち合っていただきたいと心から願うものです。