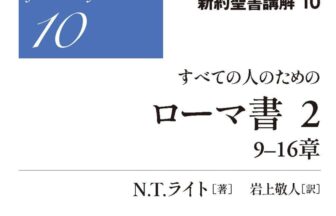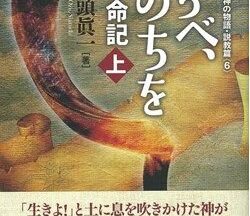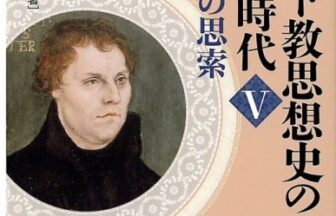ヨハネ福音書研究の集大成として貴重な作品
〈評者〉東よしみ
七月にヨベルから出版された本書は、大貫隆氏が二〇二一年度の「聖書学習講座」(無教会研修所主催)で行った講義を元にしている。本書は、ヨハネ福音書解釈におけるガダマーの解釈学の重要性を一般読者向けに平易に説明し、ブルトマン、ケーゼマン、ボルンカムという「ブルトマン学派の三角形」の中にガダマーを位置付ける。第一─五講は、ブルトマン学派とガダマーのテキストの抜粋に著者が解説を施す「講読」形式をとる。第六─七講は、ヨハネ福音書のテクストから「地平の融合」(ガダマー)を確かめる。
「わたしのヨハネ研究:序にかえて」は、半世紀あまりにおよぶ著者のヨハネ福音書研究の道のりを、個人的な話も交えて振り返る。著者は、ミュンヘン大学留学中、パネンベルクのセミナーでガダマーの解釈学に出会い、博士論文では、福音書テクストが読者に及ぼす効用に着目した。帰国後、『世の光イエス』(一九八四年)で「文学社会学」の構想を実行する。本書では初めて一般読者向けに、ガダマーの解釈学をヨハネ福音書へと適用していく。
第一─三講では、ブルトマン学派との批判的な対話が展開される。ブルトマンとケーゼマンは、歴史上のヨハネ共同体の聖霊体験への関心を示さない。ケーゼマンを批判するボルンカムは、告別説教で約束されている聖霊がもたらす「想起」(14:26)こそ、ヨハネ福音書の著者が読者に求める「解釈学的視座」であると正当にも指摘する。
第四─五講では、ガダマー『真理と方法Ⅱ』の十一の断章の解説とヨハネ福音書への適用がなされる。ガダマーは、「技法としての解釈学」(シュライアーマッハーとディルタイ)から「理解の存在論」としての解釈学への転回を宣言する。ハイデッガーに即してガダマーは「循環的理解は伝承の動きと解釈者の動きが互いに他に働きかける関係」であると述べる。大貫によれば、ここでの「循環」は「理解のための技法ではなく、解釈されるべきもの(テクスト)と解釈する者の中間で生じる出来事(事件)」であり、この出来事は「対話」と同義である(一一六)。ガダマーによる「伝承」の積極的理解は、聖書学の伝承史的・様式史的研究の見解と一致すると大貫は評価する。さらに、ガダマーがハイデッガーを越えたのは、「伝承」(伝統、テクスト)と解釈者の間を隔てる「時間の隔たり」に着目した点にあると指摘する(一二二)。ヨハネ福音書こそは、「時代の隔たり」を乗り越える解釈学的出来事のプロセスそのものを示す稀有な事例である。ヨハネ福音書の背後に潜む著者と教会共同体の独特な聖霊体験は、イエス伝承を歴史的状況の中で新しく解釈し直すという解釈学的体験に他ならず、そこでは「地平の融合」が起きている。
第六─七講では、ヨハネ福音書全体、特に告別説教が、解釈学的地平融合の最終産物のみならず融合のプロセスそのものを示すことを福音書テクストから論証する。告別説教、またヨハネ福音書全体の語り口は、歴史性と象徴性の間の境界を動く「境界上の叙述」(一八九)である。テクストで進行中の解釈学出来事に引きずり込まれる読者は、時の境界上に立たされ、「境界上の主体」となる。啓示者として歩む道のり全体を内包する「全時的」な人の子イエス・キリストこそは、境界が境界であることを止める「第三の地平」である(一九〇)。
第八講では、ヨハネが「地平の融合」を独特なキリスト論として物語の形式で論述するという大貫の主張は、ケーゼマンに対するボルンカムの批判を、ガダマーの概念を使って補完したものであると総括される。しかしボルンカムはヨハネの「全時的」な「人の子」キリスト論を充分に評価しない。これこそは「ヨハネの上に『吹いた』聖霊の働きの最たるもの」(一九九)である。最後に、ブルトマンとケーゼマンの解釈は、聖霊の「跡」をたどりながら福音書全体を読むという解釈学的視点に欠けると喝破される。
本書は、著者のヨハネ福音書研究の集大成として貴重な作品である。ガダマーを初めて読む者にも、その解釈学がわかりやすく解説され、ヨハネ福音書への適用が明晰に議論される。著者が述べるように、ブルトマン学派の論点は、今や古典の粋に達している。ヨハネ福音書、また解釈学に関心をもつ者にとって必読の書である。