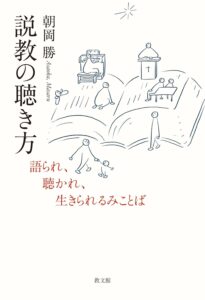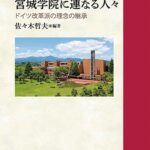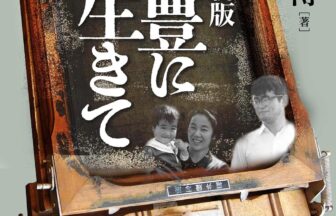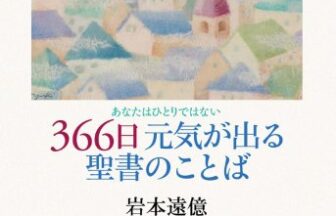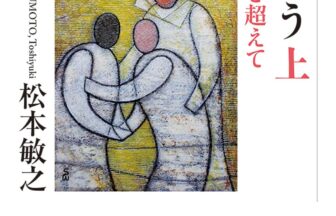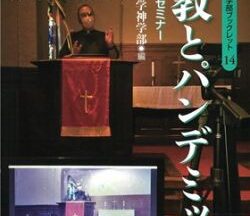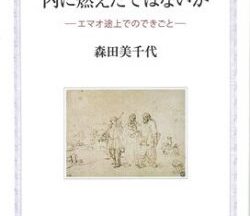説教に失望してはならない!
〈評者〉川﨑公平
本書の帯に、こういうコピーが書いてある。
「『説教で満たされない……』と悩む信徒たちへ
『説教が伝わらない……』と悩む牧師たちへ
説教の語り手と聴き手のあいだに、なぜ『ズレ』や『すれ違い』が生まれるのでしょうか? どうすれば、お互いの信頼関係を取り戻すことができるのでしょうか? 牧師と信徒が『説教』をめぐって語り合う、対話の心得を磨くための一一章」(傍点は評者)。
「私は、このような本を求めていたのだ」と思う。語る者も聴く者も、どこか満たされないまま、実は既に〈説教〉というものに失望しているのではないか。本書はそういうわれわれの姿勢を正してくれる。「説教に失望してはならない」。「教会は、神の言葉によって生きるのだ」。
まず心を打たれたのは第一章第三節「私たちは、み言葉を聞いた」である。オットー・ブルーダーの実話に基づく小説『嵐の中の教会──ヒトラーと戦った教会の物語』を紹介しながら、「しかし私たちは、み言葉を聞いたのです。私たちの耳が開かれて、そうして私たちは聞いたのです。私たちはそれを決して忘れることができません」という言葉を引用する(三八頁)。「これこそを、本書において私たちが目指す『説教聴聞』の姿としたいのです」(三九頁)。
説教の語り手のための書物ではない。聴き手だけのための書物でもない。〈教会〉が神の言葉によってのみ生きることを願い、そのことを信じて書かれた書物である。
「みことばの『語り手』と『聴き手』が分かたれた存在でなく、教会という『一つ』の存在であること、そしてそのような『一つ』の存在として、『語り手』も『聴き手』も、本来的には神のみことばの前に『ともにある聴き手』であるということ……の重要性を心に刻みつけておきたいと思います」(三五頁)。
そしてそのためには、説教者が「よい語り手」になることが重要であるのと同様に、「よい聴き手」が育たなければならない。そのためには努力が必要であると説く。
著者の考察は神学的であり、かつ教会の実践に即している。「説教の聴き方」の安易なノウハウを教えてはくれない。バベルの塔の物語や旧約の預言者の経験を紹介するところから始まり、主イエスご自身も、使徒言行録が伝える教会も、神の言葉を聴こうとしない罪に直面させられたことを思い起こしながら、まさにその罪こそが説教が伝わらない根本的な原因であると説く(第三章)。罪と戦うことなしに、み言葉を聞くことはできないのだ。
第五章も、そのタイトルが既に興味深い。「私は何を聴きたいのか、何を聴くべきなのか」。人間は本来、「自分たちの聴きたいことを聴きたい」という思いがあることを、正直に指摘する(九一頁)。だからこそ、「本当のところ」何を聴きたいのかと自問することが大事だ。聴き手は、「私は、生ける神の言葉を聴きたいのだ」という、自分の本当の飢え渇きに気づかなければならないし、語り手もまた、そのような聴き手の願いを知り、それを信じて説教しないといけない。聴き手にも語り手にも、神の言葉の前での自己変革・自己発見を求める論考である。
第九章「説教者に寄り添う」の第三節「説教者の孤立」も身につまされる。「牧師は孤独に耐えなければならないが、孤立してはならない」と言われる。厳しくもあり、また慰めに満ちたものである。礼拝堂における説教者の座席にまで話題は及ぶ(一六五頁以下)。このようなところにも滲み出ているのは、本書全体を貫く教会に対する愛、聴き手と語り手に対する愛である。
冒頭に引用した帯の言葉が言い当てているように、説教の語り手と聴き手の信頼関係を構築するための書物なのだから、それぞれの教会で本書の読書会を試みてもよいと思う。そこに新しく「対話の心得」が磨かれ、その信頼関係の中で「私たちは、み言葉を聴きました」と言えるようになったら、どんなにすばらしいことだろうか。この書物が目指しているのは、そのような教会の形成である。日本の教会の再生のために、本書をこころからお薦めしたい。