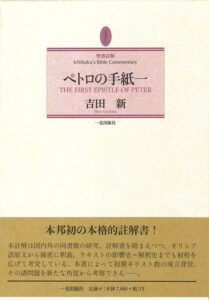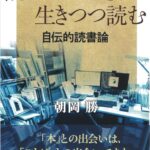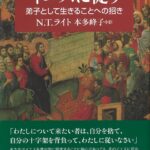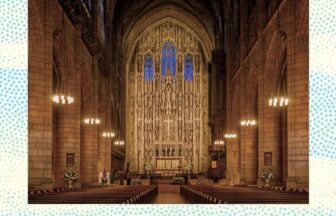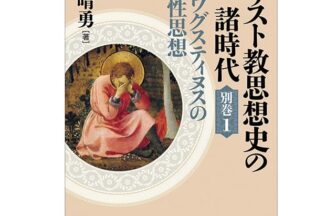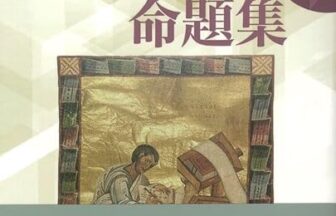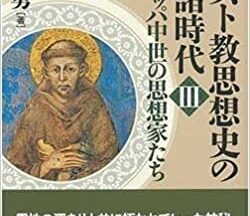本格的かつエンサイクロペディックな註解書
〈評者〉石田 学
「ペトロの手紙一」は、ルターが高く評価したにもかかわらず、教会の歴史の中であまり注目されず、時としてその内容が困惑の原因ともなり、礼拝説教の聖書箇所として選ばれることの少ない文書である。Ⅰペトロ書を単独で扱った日本語註解書は、ごく古いものを除いて刊行されておらず、新約聖書註解の一部として収録されているだけであった。数年前、筆者はⅠペトロ書からの連続説教をするにあたり、釈義に必要な註解書を求め、改めてその少なさに驚かされた。その時に本書が刊行されていたなら、どれほど助けになったことであろうか。このたびⅠペトロ書の本格的かつエンサイクロペディックな註解書が日本人聖書学者によって、翻訳ではなく日本語で刊行されたことは何よりの喜びである。本書は緻密な原典分析と豊富な文献に裏付けられた詳細かつ最新の註解というだけではなく、いくつかの重要な点において極めて特徴的である。第一に、「Ⅰペトロ書の構造と成立状況」「Ⅰペトロ書の文学的、神学的特性について」「Ⅰペトロ書の社会訓、家庭訓について」と題する九〇ページにわたる三つの章が序説として冒頭におかれている。Ⅰペトロ書はいわゆる家庭訓が重要な意味を持つが、著者は序説第3章で他の新約文書の社会訓、家庭訓との比較に基づいて、Ⅰペトロ書の社会訓・家庭訓が終末論的特徴を持つことを明らかにしている。序説は、本書の註解を読むにあたり、Ⅰペトロ書の特質と背景だけでなく、その時代の教会、特に辺境の地に生きる教会の置かれていた史的状況を読者に予め理解させてくれる。
第二に、本書の全体に亘り、随所に簡潔だが有益な補足説明・解説が挿入されている。それらはⅠペトロ書に直接関連することだけでなく、一世紀末にキリスト教がおかれていた史的・社会的な状況についても考察している。たとえば序説第1章には「周辺世界へのキリスト教の弁明と批判的言説」「皇帝によるキリスト教徒への弾圧について」「ユダヤ教とキリスト教の分離について」その他の補足項目が差し込まれている。こうした多岐にわたる補足的な解説は、序説だけでなく第2部の註解部分にも多く含まれているので、読者は註解部分を適切に理解するための有益な知識と情報を得ることができる。多くの場合、聖書註解書は必要な箇所だけを利用するものだが、本書は随所に興味深い補足説明が挿入されているので、全巻を楽しみながら通読することができる(わたしがそうであったように)。
第三に、日本語で書かれた本書は、当然のことながら日本語文献への言及が豊富である。欧文原書からの翻訳註解書の場合、引用や参照文献はほとんどが欧文であり、それらを日本で入手することは簡単ではない。日本語文献への言及が多いことは、さらなる学びをしたい人たちにとって文献の入手が比較的容易であり、研究の幅を広げることを可能にしてくれる。さらに本書が説教者にとって特に有意義なのは、主要な日本語聖書の訳を比較検討し評価していることである。著者はこの比較検討を意識的におこなっているように思う。著者が聖書の翻訳に深い関心を抱いていることの証なのであろう。
第四に、Ⅰペトロ書全文の著者訳が巻末に収録されている。ほとんどの註解書で聖書本文は註解の箇所毎に分割されていて、本文全体をとおして読むことは想定されていない。翻訳註解書の場合、本文の翻訳は註解部分との関連性がいっそう間接的である。本書の最後に収録されているⅠペトロ書全文は、著者による註解の集大成としての全訳なので、なぜこう訳したかという解釈上の根拠を註解部分で確認することができる。
最後に、筆者の関心領域の一つである宣教学の視点から本書の意義を述べてみたい。日本の史的・社会的・文化的視点から聖書をどう読み文脈化(contextualize)してゆくのか。吉田新氏はドイツで学んだ日本の聖書学者として、註解書本来の枠を越えて、この宣教学的課題に正面から取り組んでいる。補論「Ⅰペトロ2・17の影響史について」および3・8 −16の註解と補論「報復の放棄について」の論考がこの註解書に含まれていることは感動的でさえある。本書を踏まえて、もう一度Ⅰペトロ書からの連続説教に取り組みたいと思わされた。