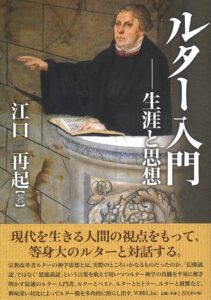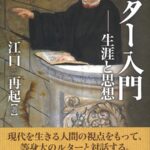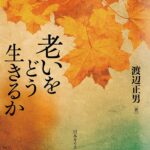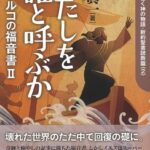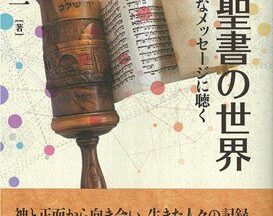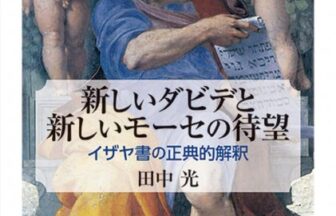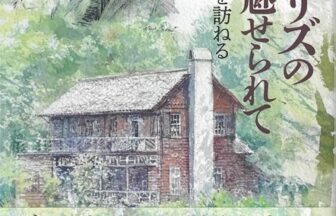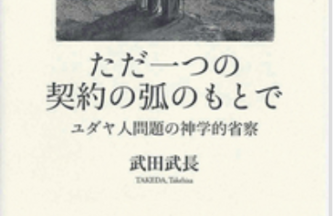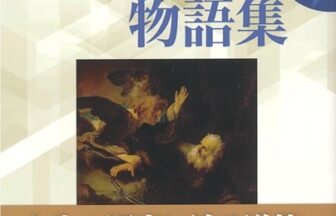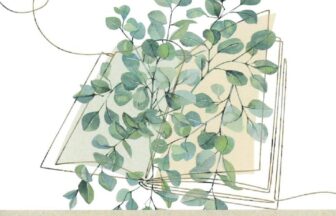教科書や事典の次に薦める入門書─平面から立体のルターへ
〈評者〉高村敏浩
本書は、二〇一七年、著者がNHKカルチャーラジオ「歴史再発見」の講師を勤めた際のテキストに加筆修正したものである。その執筆背景から、本来、クリスチャンではない人を聞き手・読み手として意識したものであることがわかる。本書は、教科書や事典を通して分かるルターよりも、もう少し深く彼について知りたいと願うすべての人にとって、入門書として最適である。
多くの日本人にとって、ルターについての知識とは、中高の教科書で触れる程度か、百科事典で紹介されているくらいのものなのではないだろうか。ルターの人物や神学、思想を紹介するものとしては、ここ数十年に限ってみても、徳善義和や倉松功、今井晋などの著作が思い浮かぶ。二〇〇〇年代に入って、トーマス・カウフマンやスティーブン・ポールソンの著作が翻訳された。これらは、「ルターとは誰か、どういう人だったのか」という問いに答えようとするものである。しかし、現実には、日本人読者にとって、入門書としては敷居が高いのではないだろうか。
入門書の難しさは、何を取り上げ、また、何を省略するかということであろう。専門家の多くは、入門レベルで書いているつもりであっても、情報過多によって読者を迷子にさせてしまうからである。だからと言って削ぎ落し過ぎてしまえば平面的になり、ステレオタイプなつまらないものとなる。本書は、一章の『九十五箇条』の紹介を導入に、ルター登場の背景である中世後期の紹介を含むルターの生涯を続く四章、さらに「恵み」と、聖書を含む「神の言葉」理解といったルターの神学思想に二章、「ふつうの人」としてのルターと、クリスチャンではない多くの人が悩むカトリックとの違いにそれぞれ一章、ルターの功罪を含めた近代への影響に二章、日本の宗教思想との対話の架け橋として親鸞の思想との比較に一章、そして私たちの生きる今との関わりに一章の、全十三章からなる。ラジオ番組のテキストだったということもあるのだろう、短い文章でテンポよく書かれていて、分かりやすく読みやすい。著者のこだわる「恩寵義認」以外の用語は、基本的にはこれまで用いられ、親しまれてきた表現や語彙を使い、定義の更新が必要なところでは丁寧に説明している。ルターを知る上でおさえておかなければならない出来事やテーマを取り上げ、予備知識のない人でも分かるように簡潔に説明しつつ、同時に、弁証法に代表されるルターの神学が持つ逆説的な緊張感を保持して伝えようとしている。これらの試みは、立体的に描き出されたルターとして成功している。
著者の江口再起氏は、日本福音ルーテル教会の隠退牧師であり、東京女子大学でも長く教えた。同教会の牧師を父に持ち、幼いときからルーテル教会で育ったため、自分のアイデンティティとの葛藤や、ルターやルーテル教会への反発も経験している。そのためであろうか、十六世紀のルターをそのまま現代に持ってくるのではなく、文化や社会問題、宗教思想や日本という私たちの生きる文脈においてルターを捉え、対話しようとするのである。
すべての人が満足することは不可能である。しかし、著者が意図するところの入門書としては、自信をもって誰にでも薦めることのできる良書である。