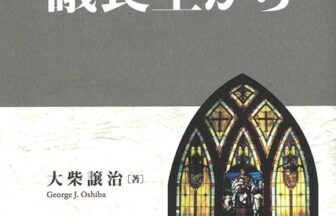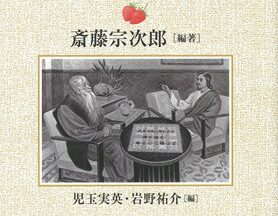本誌11月号に掲載された深井智朗氏の書評について、編集委員会で論議となりましたので、当欄を借りて報告させていただきます。深井氏は、過去の著書、記事において、捏造・盗作の不正行為を行っていたことが認定され、2019年、在職していた学校法人から懲戒解雇されています。また同氏の著作の一部は絶版回収扱いとなっています。また前年に受賞した吉野作造の授賞も取消されました。
その後、同氏は、自らの不正行為について、謝罪と反省を公にする発言を行っておられません。私たちは、深井氏が著述者として公にした業績を全て否定するべきだとは考えません。しかし、著述において深刻な不正行為を犯した人を、本人の明確な反省もなしに新たな著述に起用することは、たとえ小さな書評といえども本誌読者の信頼を失し、言論活動の自滅につながるからです。
今回の深井氏の書評は、書評対象となった書籍の出版元が提供した原稿でしたが、本誌編集部による事前チェックが十分でなく、11月号発行前に深井氏の寄稿を見過ごしてしまいました。今後は編集委員会の職責を果たすべく、チェック体制を強化し、このようなことのないように努めます。
ここに、当該書評掲載に関する私たちの考えを明らかにし、併せて読者にお詫びを申し上げる次第です。
『本のひろば』編集委員会
2024年10月
日本人のもつDNAを見事に分析・展開した西谷学
〈評者〉深井智朗
本書の著者が牧師としての責任を負う戸山教会は、もともと「陸軍戸山学校」があった場所で、教会の土台となっているのは、かつての「将校集会所」だ。マッカーサーが日本を去る際、「駐留軍宿舎を無償提供することで」できたのが「戸山ハイツ」で、「何かセンターになるものを」というGHQの提案に、都の建築局長が「教会」はどうかと返答したことで生まれた。不思議な歴史だ。軍事施設があたかも回心して洗礼を受けたかのように、教会の土台となった。ここにあった陸軍幼年学校の最上級生として敗戦を迎えた少年が、戦後、献身して牧師になった。実は、著者も評者も、若い頃この牧師の指導を受けた。時々、「天皇には奈良にお帰りいただき、皇居をセントラルパークにしよう」などと真面目な顔で言うので戸惑ったが、他方で、戦後の日本人は本当に新しい生き方を始めたのか、「日本は変わるか」と真剣に問い、独自の日本人論や「日本の神学」を展開した。批判もしたが、それ以上に多くを学び、また教えられた。
これまで日本人論はどれくらい書かれたのだろう。どれを読んでもしっくりこないのは、あまりにも分析が第三者的で、批判も手厳しく、これを書いている著者自身はどこに立つのかと考えてしまうものか、逆にあまりにも実存的過ぎて、日本への愛の告白のような議論のどちらかだからだ。でも、本書は違う。どちらの要素ももっているが、真剣さが違う。それは、著者が、これからの日本のために、将来生きる者たちに語りかけようとしているからだ。また、本書の根底にあるのが、伝道者としての願いで、パウロのように元来普遍的な問いでもある「人間とは何か」という問いを「日本人には日本人のように」語ろうとしているからだ。
著者は、既に英語と日本語で自説を公にしているが、本書で特に注目すべきは次の二点だ。第一に、日本人には暗黙の宗教としての「日本教」があり、その内実は「母子の愛情」だ、ということ。第二に、第一の事実に基づくなら、母親が子の抱える問題の解決に責任をもつのが日本の責任性の原型なのだが、現実は、「子の難局を解決すべき慈母たる親がむしろ自身で難局に陥り、そこに子からの救いを要求するという事態」であり、しかもそれに「子が応じる」という逆転が起こっている、という点だ。そのため「親の恩を忘れたか」という言い草で、子の報恩を親の権利として要求する。また、個人のレベルだけではなく、社会のさまざまな場所で、この構造を利用する日本システムがはびこる。その典型が、数々の日本人論に登場する「国民は天皇の赤子」ではなく「天皇は国民の赤子」という逆転だ。著者は、記紀 、日本ではほとんど知られていなかった英文の「神道信条」の文献学的分析や解釈、さらには日本の伝統芸能や文学のテクストを読み解きつつ、その上でこう言いたいのだ。この日本の曖昧さ、無責任性、弱点に気づき、これを克服せよ。「日本人がこの問題を克服できれば、日本文化は世界の諸文化に多くの面で貢献しうるのではないか」(28頁)。
この日本人論は神学的だ。神学は、人間に命を犠牲にすることを求める神や君主ではなく、人間を救うために独り子を十字架につける神がいることを知っていて、その土台の上で日本人論を展開する。
歴史の中に、あるいは個々の人生に新しいことが起こる。たとえば陸軍戸山学校が戸山教会になる。歴史学や社会学はその事態を、資料を使って説明したり、心理学的に分析したりもするのだろう。でも、神学的「日本人論」は、ここに神の真実と救済の歴史を見て、しかも永遠の相のもとに相対化し、社会や人間の現実の問題を抉り出す。いや、そこに留まることなく、最後には、私たち自身が自分に気づき、回心し「新しい人間」になることを勧める。私は他の誰かにではなく、自分に対してそのように語られたと感じ、本書を読み終えた。