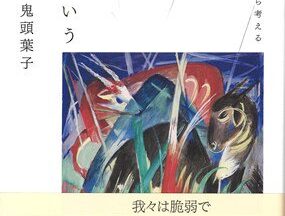旧約の解説とイスラエル神学思想史を兼ねる名著
〈評者〉月本昭男
学術的であってしかも読みやすい旧約聖書の解説書は多くはない。一九五七年の初版以来、重要な研究成果を加味した改訂がほどこされて、版を重ねている本書は、その両面を備えている。邦訳は改訂第五版(二〇〇七年)に基づく。著者はプリンストン大学、ボストン大学などの神学部で教鞭をとられた米国を代表する旧約聖書学者の一人(二〇〇七年に逝去)。
解説書といっても、本書は旧約各書を順次解説するわけではない。独自の神信仰を育んだイスラエルの民が時代ごとにいかなる課題と取り組み、それをどのように後代に伝えようとしたのか。そうした観点から、この民の歴史に沿って旧約各書の思想と信仰が明らかにされてゆく。その歴史は大きく、民族形成の時代(第一部)、王国時代(第二部)、第二神殿時代(第三部)に区分され、各時代には主題別にそれぞれ六つの章が設けられる。そして、近年の歴史学、古代オリエント学、考古学、文献学の研究成果をふまえつつ、各章に著者ならではの考え抜かれた聖書解釈が表明される。
たとえば、「モーセ律法の再発見」と題する一一章では、ヨシヤ時代の「申命記改革」に焦点があてられ、改革の神学的基盤とされた申命記が「モーセの説教」として提示される。そこでは、出エジプト伝承にあらわされたイスラエルの民に対する「神の愛」がこの民に「神への愛」を要請し、それが慈愛あふれる行動へと彼らを促す。それによって虐げられた者たち、社会的に弱い立場におかれた者たちの保護を旨とする「人道主義」が基礎づけられたのである。だが、そのような「愛と連帯の精神」を律法化し、戒律の遵守と違背を神の祝福と呪詛に直結させることによって「歴史における神の働きを単純化してしまった」と、申命記神学の欠陥を指摘する。そのために、「もし人が神の法に従っても苦難や困難に見舞われるとしたならば、神とはいかにして義でありうるか」という大きな疑問が残されたが、この疑問に正面から取り組んだ預言者がヨシヤ王の死の直後に登場したハバククであった(四六四-七六頁)。
各章がこのように印象深く綴られてゆく本書は、旧約聖書の解説でありながら、イスラエル神学思想史といったおもむきをもつ。そこに流れる通奏低音は「契約」思想であり、神と「契約」によって結ばれた民イスラエルの自己理解である。古代西アジアには、イスラエルの民が登場するはるか以前から契約観念が発達していたが、神と民の関係を契約関係ととらえたのはイスラエルのほかになかったのである。
それにしても、本文だけで八〇〇頁に及ぼうとする本書は簡単には読みとおせない。評者は、聖書に関心をもつ方々が旧約聖書の各書を学ぶ際に、その時代と思想的位置づけを確認すべく、本書を手もとにおかれることをお薦めする。本書には、時代ごとの詳しい年表は一〇点、地図は一四点におよび、旧約聖書理解に欠かせない重要概念が各章に二つないし三つ、最近の旧約聖書研究をふまえながら、わかりやすく説明されている。訳文はごく自然でなめらか、翻訳書であることを感じさせない。