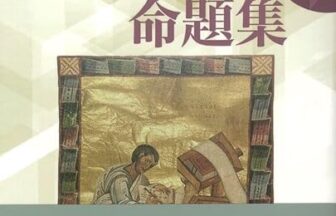生と死のはざまでの在りようを教える
〈評者〉原 敬子
「こんにちは。初めまして。この病院の牧師です」と言って、大野高志先生はチャプレンとして病棟の患者さんのお部屋を訪問されます。自然に、まるでそよ風がふっと窓から入ってくるように、患者さんのそばに「たたずむ」ために、病室を訪れます。併設されている特別養護老人ホームや介護老人保険施設、そして、ホスピスも訪問し、皆さんの声にじっと耳を傾けていらっしゃいます。患者さんたちが語られる声に耳を傾け、患者さんたちの声にもならぬ心の声に触れ、大野先生はただ一心に神に祈っていらっしゃる……。本書は、そんな大野高志先生のチャプレンとしての日々の生活の一場面に、読者のわたしたちをも招いている、そんな本です。
チャプレンシー、パストラルケア、スピリチュアルケア、そして、近年、グリーフケア、臨床宗教師と、さまざまな呼び名で生老病死の現場にかかわるワーカーの方々のお仕事があります。医療従事者、介護福祉でお働きの方々、また、教育現場に関わる方々でさえも、人間は生と死のはざまに存在し、単に生物学的、あるいは心理学的に割り切れるものではないということを、常日頃、考えざるを得ない。だから、ますます、こういった領域のフォーメーション(養成)が求められているのだと思います。
キリスト教には古来、メメント・モリ(死を忘れるな)という言葉があり、生と死のはざまに生きる人間存在について内省するよう人びとに求めてきました。人のいのちの儚さを「今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草」(ルカ12・28)になぞらえつつも、それでも、神さまが人間をどれほど尊ばれているか、どれほど美しく装ってくださるかを想像たくましく考えよというわけです。つまり、朗らかに生きているその瞬間も、死のリアリティをおまえの身に内包させておくようにという、これはひとつの戒めなのだろうと思うのです。
わたしは読了後、著者、大野先生はもう彼岸に足を一歩踏み入れておられるのではないかと感じてしまいました。生者の世に片足を残しつつも、死者の交わりの中にも片身(からだ半分)は入っておられるのではないか。そのように考えますと、まさに、大野先生は現代におけるメメント・モリの実践者。生と死のはざまでの在りようを教えてくださる方です。
ある患者さんは「先生ありがとうございました。私は明日、逝きます」と言って、ほんとうに翌日、息を引き取られます。まるで「いってらっしゃい」とでもおっしゃられそうな大野先生の柔らかな表情が目に浮かびます。もちろん、本書の中で幾度となく書いておられるような「書けない」「届かない」ご経験も想像できます。しかし、生と死が断絶ではなく、連続した一本の道の途上における決定的な出来事なのだということを、本書によってわたしは強く実感させていただきました。
大野先生がこの道の途上で神さまに祈ってくださっているように、わたしもたたずむ、わたしも聴く、わたしも祈る……。本書はキリスト教霊性の伝統を脈々と継承する実践神学の書として多くのスピリチュアルケア・ワーカーの元に届けられるでしょう。