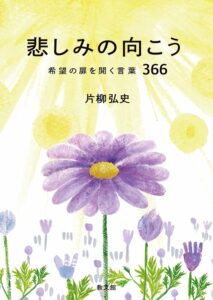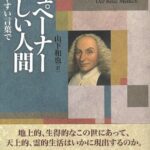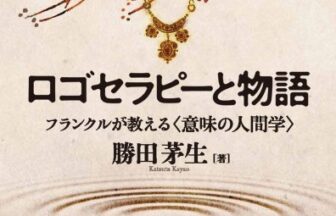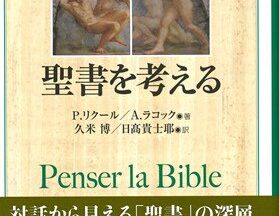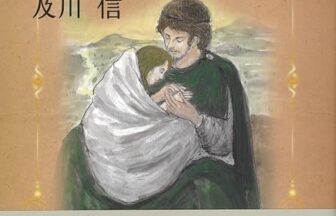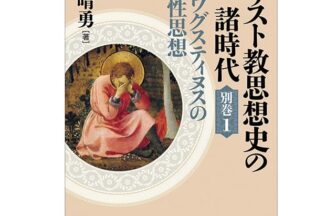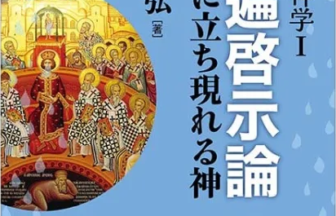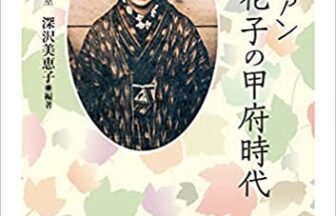悲しみの向こうにあるもの
〈評者〉横田南嶺
『悲しみの向こう──希望の扉を開く言葉366』の著者、片柳弘史神父とは、PHP研究所の企画で、何度か対談をさせてもらっています。温厚なお人柄で、キリスト教と仏教という宗教の違いを超えて親しくさせてもらっていて、また尊敬申し上げています。本書の書評を書くよう依頼されて、書斎にはいつもこの『悲しみの向こう』を置いて、折に触れては開いていました。この本を開くとなぜかホッとします。表紙を見るだけでも落ち着きを取り戻します。どうしてだろうかと考えてみると、人は誰しも悲しみをいだいて生きているからだと思うのであります。
思えば仏教を開いたお釈迦様は、お生まれになって数日で実の母を亡くしています。自分の命は、母の命と引き換えに賜ったのだという深い悲しみが、お釈迦様の教えの根底に流れています。「人生は、苦である」とは仏教の教義の根本でありますが、「人生は悲しみである」といってもよいかと思っています。
数年前に、石川県かほく市にある西田幾多郎記念哲学館で講演を頼まれて、哲学館を訪れたことがありました。記念館に入ってすぐに、「哲学の動機は『驚き』ではなくして、深い人生の悲哀でなければならない」という一文が掲げられてあって、感動しました。西田幾多郎にとっての人生の悲哀とは何だったのでありましょうか。十三歳で体験する姉の死をはじめに、弟の戦死、そして五人の子供を亡くしたことでもありましょう。深淵なる哲学は、この深い悲しみから生まれているのであります。
仏教詩人と呼ばれる坂村真民先生に「かなしみはいつも」という詩があります。その詩の中に「かなしみは みんな書いてはならない かなしみは みんな話してはならない かなしみは わたしたちを強くする根 かなしみはわたしたちを支えている幹 かなしみは わたしたちを美しくする花」という言葉があります。悲しみこそが私たちの人生を根底から支えてくれるものなのであります。ですから真民は「かなしみは いつも枯らしてはならない」と詠いました。悲しみをかみしめて一歩一歩歩いて行くのがお互いの人生であります。
さて悲しみの向こうにあるのはいったい何でありましょうか。高見順は「葡萄に種子があるように 私の胸に悲しみがある 青い葡萄が酒に成るように 私の胸の悲しみよ 喜びに成れ」と詠いました。悲しみはやがて人生の喜びへと熟成されるのでしょうか。それまでには幾多の苦難を経なければならぬのでしょう。苦難にくじけてしまってはどうなりましょうか。苦難を支えてくれるのは、やはり人の支えでありましょう。よき書物の言葉でもありましょう。
そしてそれらを通して人は、キリスト教の言葉で言えば「神の愛」を感じることができるのでありましょう。仏教で申し上げれば「仏の慈悲」にほかなりません。
本書を手にとって読んでいると、どの文章も短いながらも片柳神父の深い愛が感じられます。そして神の愛にいだかれているのだという安心を得ることができます。