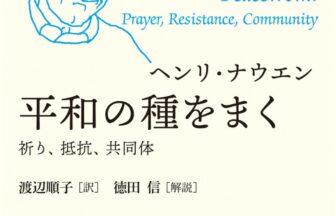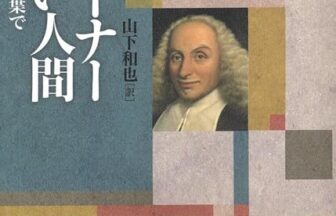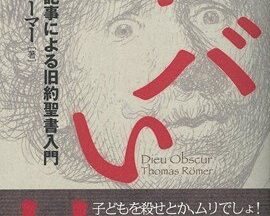日本文化の深層や日本人の心の深みを浮き彫りに
〈評者〉木村庸五
評者は以前本書初版の書評をしたことがある(季刊誌『教会』一二二号)。このたび、本書は改題され(旧題は「母子の情愛─日本教の極点」)、さらに補遺として「不当な連れ去りか母子の情愛の帰結か─日本人母親によるアメリカからの子どもの連れ帰り」の項を加え、改題改訂第二版として刊行された。改訂再版が出るほどに日本人論への関心は依然として続いていると思われる。
この補遺は、ここ数十年間の三百五十件ほどのアメリカ人父親と日本人母親の離婚に際し、そのほぼすべての事例で日本人母親が子どもを日本に連れ帰った、という日本人母親独自の顕著な現象に注目している。こうした場合、一般には、子を連れ去る父・母の割合は二対一であるにも拘わらずである(本書二一三頁)。そして、著者は、この現象が日本文化の内包する母性原理、「母子の情愛」に由来することを指摘して、その「日本教」の解明・探求のさらなる前進を示した。
一九七〇年以降、山本七平が「日本教」概念を用いた日本人論を展開し、注目をあびて久しいが、本書の著者は、その後公にされた様々な日本人論を踏まえ、日本人の宗教的内奥に厳存する日本固有の究極的価値観を究明し、日本文化の核心に迫り、それに起因する特徴的な社会的振舞いを解明する。「宗教は文化の内実、文化は宗教の形態」との基本に立ち、解明の手法として文化的事象から帰納的にその内実である宗教的価値観を解明する。日本人は人間味をことのほか重視し、神学は持たず人間学が思想や宗教に優先する。日本においてはキリスト教徒も日本教に包み込まれ「日本教徒キリスト派」となり、仏教徒やマルクス主義者は「日本教徒ブッダ派」「日本教徒マルクス派」となる。その日本教の核心は何か。
日本人は施恩には報恩を期待し、恩の合理的貸借関係を律義に守る。
著者は、①日本の人間関係は内密な二人称関係を通して成立するとする森有正の二人称関係論や②河合隼雄の日本人の「母性」優位論の指摘を、日本人論、日本教解明に寄与したとして評価する。精神医学においては一九七六年以降精神科医の古澤平作が阿闍世物語の紹介を通して「日本社会は母性社会である」という命題を提示し、これに沿って小此木啓吾と北山修が「阿闍世コンプレックス論」を展開し、父子の罪の因果であったフロイト理論に並ぶ有力な精神分析理論を確立した。古澤は物語を父子の罪の因果のテーマから「母子物語」へと変容させることにより臨床的にも有効な精神分析論を築いた。
さらに土居健郎が導入した「甘え」概念により、乳児が自己と別存在者である母を求める行為に準じ、相手の好意を当てにして甘え振舞う日本社会独自の現象をとらえた。
著者は日本教の核心に迫る概念としては「母子の情愛」という表現が至当であるとしてこの日本的な情緒を中心概念に据えて日本人論を展開した。母子の間には無制限の施恩と報恩関係が成立するが、他人どうしには恩の合理的な貸借関係のルールが適用される。
本書第三章においては、脳死臓器移植をめぐる日本人の特異な反応の分析を通じて、施恩と報恩に関する理論を実証的に裏付けている。脳死臓器移植に対する日本人の著しい消極性と、生体肝移植に対する積極性を、日本人の恩の貸借関係の特性から説明する。後者では血縁間の場合、恩の受贈の負い目に悩まないが、脳死臓器移植の受け手の場合は、他者の「施恩」に「報恩」することができず、負い目を感じてしまう。
著者は「おわりに」の部分において、神社本庁が一九九九年に公刊した英文パンフレットにある「神道信条」五カ条を訳出し、コメントした。日本文化の深層、日本人の心の深みにこびりついている古来の価値観が、この「神道信条」によってようやく活字化された。著者が願うように、神道側からの更なる説明を期待する。
本書が扱う問題は、評者が関心を持つ天皇に対する日本人の心性、霊性の根底にあるものの解明や、日本の国家・社会・国民意識の構造の分析、変革の指針の提供に大いに資すると思う。