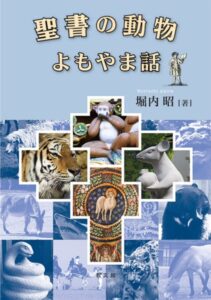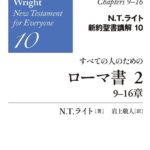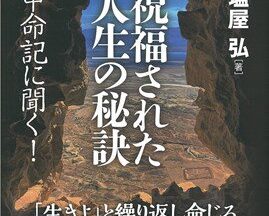化学者が案内する聖書と動物の心躍る世界
〈評者〉上田恵介
聖書は古い書物である。舞台は地中海の周囲、イスラエルとその周辺地域である。聖書が書かれたその時代、人々と動物との距離は、今の時代よりはるかに近かっただろう。聖書に登場する動物たちを見れば、当時のこの地域に住んでいた人々の動物に対する見方がよくわかる。
著者の堀内さんは立教大学理学部での私の同僚で、大学も先輩なので、専門分野こそ異なるものの、赴任当初から親しくさせていただいた。その堀内さんが聖書の動物というテーマでこの本を書かれた。堀内さんは有機化学の研究者だし、大学での講義も専門分野の講義だったから、彼が動物に興味をお持ちだったとはこれまで知らなかった。
本書は四つの章に分けられている。最初の章が「家畜・人間のそばにいるもの」で、私たちの身近にいたヒツジ、ロバ、ウマ、ウシ、ブタ、そしてラクダも登場する。中近東の人々にとって、ラクダは生活に必要不可欠な家畜であった。よく登場する動物もあれば、あまり出てこない動物もある、ヒツジは神への生贄としてよく出てくるが、ネコは一回しか登場しない。
次の章の「地の獣」で野生の獣たちが登場する。舞台が地中海周辺であることから、出てくる野生動物の種類は限られるが、シカやウサギはもちろん、サルやヒョウやトラも登場するのは当時の人々の交流の範囲がアジア、アフリカにまで広がっていたことの現れだろう。
三番目が「翼あるもの」で、家禽ではハトとニワトリ、野鳥ではカラスやスズメが出てくる。私はこれまであまり聖書には縁がなかったので、この本を読んで、はじめて知った話もある。それはノアの方舟の話で、ノアが陸地を探すために最初に放った鳥は、私はずっとハトだと思っていたのだが、じつはカラスだったということをこの本を読んで初めて知った。だがなぜカラスだったのだろう? カラスはその好き嫌いは別にして、確かに人々に身近な存在ではあるが、その時代の人々にとって、カラスとはどういう存在だったのだろう。そんなことに思いを巡らしながら、この本を読んでみるのも楽しいだろう。
イナゴやバッタも「翼あるもの」で登場する。じつは地中海沿岸のこの地域は昔から飛蝗による農作物の被害に悩まされてきた。蝗はイナゴを意味する漢字であるが、実はこれはイナゴではなく、砂漠周辺の半乾燥地で大発生する主にサバクワタリバッタである。当時の人々にとって、このバッタの被害は大きなものであったことだろう。だが聖書には食用にできるとも記されており、人々のたくましさも見てとれる。
最後の章は「水に群がるもの、地を這うものと海の魚」で、カエル、ヘビから、ウナギやクジラまで、様々な生き物が登場する。さらには真珠を取るアコヤガイはもちろん、染料となる貝紫を採取する貝のこと、香料として珍重された貝のことなども取り上げられており、著者が有機化学分野の専門家であることを彷彿させる。
聖書だけにとどまらず、コーランから仏典まで、古今東西の文献を渉猟されての執筆作業は、堀内さんにとってとても楽しい時間だったろうと推察する。