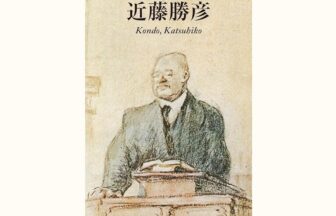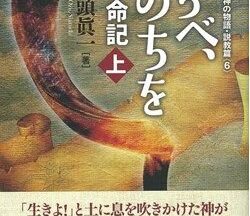近代ドイツ史研究に不可欠の書
〈評者〉猪木武徳
人間社会にとって、政治と宗教はどのような関係にあると考えればよいのか。「皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい」(マタイ22・21)という答えが与えられていても、実際の政治の場でこの言葉がそのまま具体的に実践できるわけではない。政治も宗教も、人間のこころに潜む混乱に、ひとつの秩序を与える仕事という点で共通しているが、これらふたつが相互に排他的な分野として截然と分けられることはないからだ。
桜井健吾氏の大著『近代世界と宗教』は、この政治と宗教の関係という根本的な問いに向き合い、抽象論・観念論に陥ることなく、文献資料に即して具体的かつ丹念に論究した歴史研究である。氏の長年の研究の集大成とも言える。本書を粘り強く読み進めることによって、ヨーロッパ社会における政治権力と宗教権力の錯綜した緊張関係を深く学ぶことが出来る。
本書の内容を敢えて簡略に示すと次のようになろうか。まず一八〇三年の「世俗化」を、近代の社会と政治の構造転換に対応するカトリック世界の自己変革の出発点として位置付ける。一八四八年の革命の産物である「カトリック教徒大会」は、キリスト教界による民主的な多元社会を目指す運動へと宗派を超えて展開した。慈善事業の社会運動「カリタス」の再生と展開は、国の行政機構に組み込まれつつも有効な福祉運動へと発展。一九世紀初頭のツンフト解体の後に生まれた職人組合は「職業、家族、宗教」を合言葉として、産業社会への移行に対応しようとする先見性を持っていたと論ずる。
続いて、近代ドイツのカトリック社会運動として生まれたカトリック労働者同盟が、一八八〇年代に階級縦断的な大衆運動として機能し始める過程を描く。だが宗教と政治双方に関わる二重の目的を持つこの組織は、経済面での自律性に特化した団体の運動を求めるようになる。その結果生まれるのがキリスト教労働組合である。この団体も労働者と労働組合の自律性をめぐり内部対立に直面し、社会主義勢力に対抗すべき力を生みだすことが出来なかった。
最後の二つの章では、宰相ビスマルク、カトリック弾圧に協力した自由主義者たち、そしてカトリック陣営の三者間の「文化闘争」の内実が論じられる。教皇レオ一三世が、ビスマルクと性急に妥協したにもかかわらず、教皇とドイツ・カトリック教徒とのつながりを強め、政治的利害を超えたところで世界の信徒と繋がり得る宗教・道徳上の地位を高めた、という指摘は興味深い。
こうした政治と宗教の対立と融和の問題が、時代の政治と経済状況を念頭に、清潔な文体で具体的かつ明快に論究する姿勢は見事と言うほかはない。近代に入って主流となった西欧キリスト教世界における「政教分離」の原則自体は、政治権力と宗教権力がお互いの侵入を避けるという意味では明快に見える。しかし分離が「いかなる事態を避けるためなのか」という点では日本と西欧は同じではなかった。自由の獲得をめぐる長い歴史をもつ西欧社会では、宗教が政治的関心を高めることによって、宗教の持つ本来的な力が弱まるのをいかに避けるのかも強く意識されてきたのだ。近代社会の難問を、具体的歴史事例をもって理解するための貴重な学術書の誕生を喜びたい。