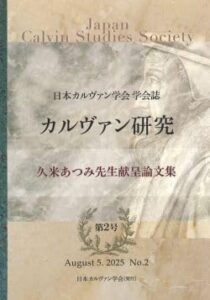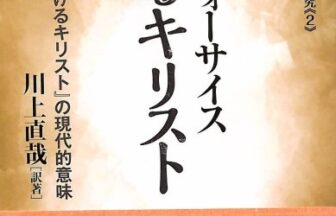専門研究への刺激を与えてくれる素材に満ちた論文集
〈評者〉宍戸基男
本書の内容は、学術講演が3本(「カルヴァンの義認論の再評価… …吉田隆、「礼拝の構成要素としての詩篇、J・カルヴァンの場合」… …菊地純子、「カルヴァンの聖書解釈:古代から中世を経て」… …野村信)、と研究発表2本(「カルヴァンの妻、イドレット・ド・ビュール」… …木村あすか、「晩年のポール・リクールにおける哲学的不可知論」… …山田智正)、最後に「H・オーバーマン著『二つの宗教改革』を巡って 訳者、編集者たちによる自由な語り合い… …発表者 金子晴勇、竹原創一、田上雅徳、野村信によるシンポジウム」、A5判、104頁の比較的小型の学術書であるが内容はどれも充実しており、扱われている分野も多岐にわたっている。自分の興味や専門研究への刺激を与えてくれる素材に満ちた好論文集となっている。
「日本カルヴァン学会」発足の経緯については本書1ページに野村先生によって記されている通り、組織の変遷もありアジアの国々の研究者たちとの交流を通じて、広くカルヴァンのプロテスタント信仰や教会に対する影響だけでなく、政治学や政治思想史、さらには経済史的な影響力の研究につながるような、カルヴァンの影響はどうであったのかといった問題も、この学会で論議されるようになっている(本号の田上雅徳氏の発表参照)。これらの傾向は歓迎すべきことであると同時に、公平に見てカルヴァンの大きな貢献はプロテスタンティズムの構築にあったことは否定できない。教会形成については、プロテスタンティズムの第二世代としていかにカトリック教会に対して自らの立場を構築するか、また再洗礼派などの対応にいかに腐心したか。これらはカルヴァン業績の主要な柱としていつも捉えていることは言うまでもないであろう。
今回の諸論文の中で、筆者の注目を引いたのは、「礼拝の構成要素としての詩篇、J・カルヴァンの場合」(菊地純子)。日本では詩篇を個人的信仰の養いという点からは受け止められているが、神の民イスラエルが神礼拝の重要な要素として、詩篇を歌うことをしていた歴史的事実を裏付けながら、これを回復しようとしたカルヴァンの業績の歴史的検証を踏まえ、それを日本の諸教会に根付かせようとする著者の冷静さと熱意が伝わってくる。また野村論文の第一論文「カルヴァンの聖書解釈」およびシンポジウムでの発表で、言及されている「聖書のみ」が日本の教会では「教理のみ」になり、人間の体でいえば骨格のみで、これが行き過ぎて過剰防衛となり、身動きが取れなくなって肉の成長が抑えられている。教理体系による枠がわたしたちを抑え込んで自らの首をしめ窒息しているというのが日本の現代の姿である(p92)。その解決としてのカルヴァン自身の聖書解釈の方法の提示は聞くべき論説である。
本号は長く学会を指導してこられた久米あつみ先生への献呈となっているが、筆者が1987年カルヴァンの生誕地ノワイヨンの記念館を訪ねた折、『綱要』の諸外国の訳の中に、日本語訳中山昌樹訳、渡辺信夫訳、そして久米あつみ訳があった。久米訳は1986年に出版されている。