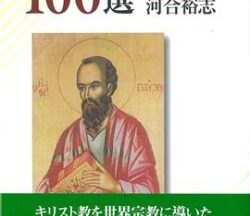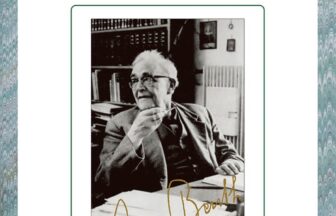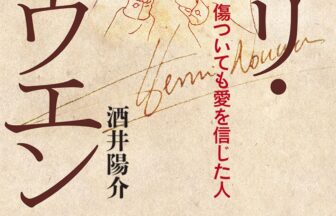あらわれ出る聖性
〈評者〉島薗 進
プロテスタントの牧師の息子だったゴッホ(一八五三─九〇)は一六歳以後、画商として働くなどした後、聖書を熱心に読みふけり牧師になろうともしたが挫折し、二七歳でようやく画家になる決意をする。不遇のまま三六歳になる頃から精神病院で多くの時を過ごすに至り、自らいのちを絶ったのは退院して二ヶ月余り後のことだ。この一〇年間に描いた作品は後世の人々の心を揺さぶり、あるいは深い慰めをもたらすものとなった。
二〇一七年刊行の『ゴッホと〈聖なるもの〉』(新教出版社)でゴッホの絵画作品をキリスト教信仰との関わりから読み解いた著者は、本書ではキリスト教の枠を超えた人類史的な宗教性の現れとしてゴッホ絵画を捉えようとしている。美術史研究の蓄積を十分に踏まえた上で丁寧に絵画作品を読み取りつつ、「哲学や思想、宗教人間学の視座から見据える」(九頁)という野心的な試みである。
本書は三章から構成されており、それぞれの章は焦点を当てられた作品をめぐって濃密な論が展開されている。第一章「《馬鈴薯を食べる人たち》──存在の大地」では、一八八五年にオランダのニューネンで描かれた食卓を囲む五人の農民を図柄とする作品が主題だ。著者は「この絵画では大地に支えられたいのちが前面に出てきている」とし、それを「大地性」とよぶ(四五頁)。この作品は、生きとし生けるものを根底から支える大地性の顕現を描いたものだという。
第二章「ゴッホの《ひまわり》」では、一八八八年に南仏のアルルで描かれた卓上の花瓶にいけられた多くのひまわりの花を描いた作品に焦点が当てられている。ゴッホはアルルにゴーギャンらの画家仲間を招き、理想的な共同体を作ろうと希望に燃えていた。実際は自ら耳を切り落とし、ゴーギャンは短期でアルルを去り、ゴッホは精神病院に入ることになった。その前の段階に光あふれるひまわりの絵画をいくつも描いていた。福音書がソロモンの栄華も及ばないとした草花の輝きがそこにある。「実際、ひまわりは画面に満ちる光と一体となって、美しく装われている。……ただあるがままにある。……その姿が名状しがたいほどに神々しく、光輝にあふれている」(一〇〇頁)とある。
第三章「《星月夜》の宇宙」では、亡くなるおよそ一年前の一八八九年六月にアルルからさほど遠くないサン・レミで描かれた《星月夜》とその前後の夜空や糸杉を描いた作品や自画像を論じている。糸杉は墓と連想されるものだが、教会の尖塔に代わり天に伸びてゆく生命力でもある。そこでは、「宇宙と自己の境界が取り払われ」、生と死の境界も越えていくような境地が描かれており、「最も救いのない状況にあったとき、不思議なことに救いの光が射しこんできたのではないか」(一七二頁)という。
ゴッホ絵画を人類共通の宗教的な基盤と結びつけて捉えるという視点が、ゴッホの絵に私たちが魅入られる理由を示唆してくれる。ゴッホの作品は画家の意図を超えて、そのような次元に届いているとする。宗教から遠いと感じがちな現代社会に生きる、私たち自身の内奥にある宗教的なものを見直すよう促す書物でもある。