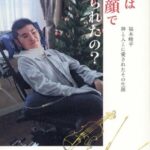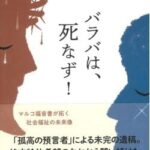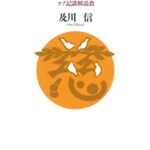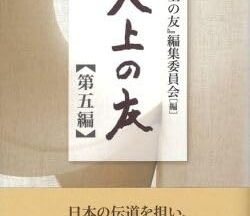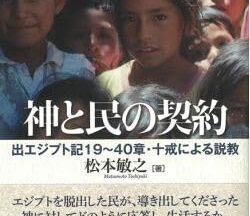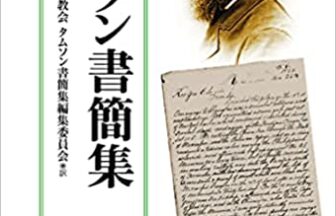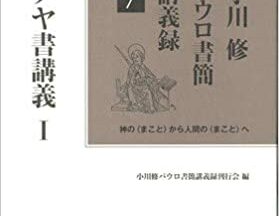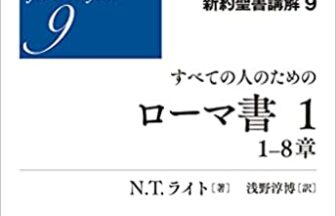今、あらためてこの時代にあって人格の完成を目指す教育の根本を問う
〈評者〉嶋田順好
本書は、青山学院大学総合研究所の研究ユニット「日本の教育における伝統思想とキリスト教学校の攻防」の成果として出版された。
内容構成は、第一章「日本の教育政策とキリスト教界への浸透」(森島豊)、第二章「戦後日本と国家神道──天皇制の宗教的側面(島薗進)、第三章「戦後教育制度の『デザイナー』田中耕太郎──その思想と教育勅語をめぐって」(島田由紀)、第四章「戦後のキリスト教学校は何と闘ってきたのか」(伊藤悟)、第五章「道徳教科化における思想的問題──『修身科』復活問題における天野貞祐と昭和天皇の関係」(森島豊)、第六章「キリスト教的な人格教育とは」(長山道)、第七章「キリスト教学校の攻防の可能性」(森島豊)となっている。
本書の主題の背景を正しく認識するために、先ずは第二章の島薗論文を精読し、天皇による祭政教一致の統治を実現させるための明治期における国家神道形成過程と、戦後の葦津珍彦に代表される「国家神道」復活を企図する人々の「見えない化」戦略を正しく認識する必要があろう。以下では、順不動で評者に与えられた気づきを列挙したい。
第一章では、明治政府が、キリスト教を、共存と抑圧という方策で管理しようとした際、当時のキリスト教界指導者たちが、国体思想とキリスト教信仰は矛盾せず、むしろキリスト教は国民の道徳的教化に貢献するとの弁証をもって存続の道を見出そうとした功罪が鋭く問われている。
第五章では、文部大臣天野貞祐が、一九五一年の修身科復活に関わる国会答弁で「国家の道徳的中心は天皇にある」と発言した背景に、皇室と国民との関係を良くしたいとの昭和天皇の意向が、田島道治侍従長から伝えられた事実が明らかにされる。象徴天皇による「内政干渉」の実態が、浮き彫りにされた論文として高く評価したい。その後の道徳教科化への歩みの背後には、常にこの天皇の意向が含意されていることを看過してはならないであろう。
第七章では、青山学院に関わりを持ち、「キリスト教信仰と国際的な感覚というキリスト教学校の重要な遺産」を継承した人々の戦時下抵抗の歩みが紹介されている。重要なことは、キリスト教学校が、この時代のなかで「国体思想」に抗うには、「国際的なネットワークと国内私立学校間の連携」を深めるべきであるとの指摘であろう。
第三章では、教育基本法制定の担い手であった田中耕太郎が、カトリックの自然法思想に基づき、教育の目的を「人格の完成」としたにもかかわらず、教育勅語を擁護する矛盾を犯したことが指摘される。それは戦後直後の混乱を防ぐべく「心情的・功利主義的な天皇・天皇制の理解を自然法思想に強引に引き寄せた」(一一五頁)結果で、後にこの見解は修正されることになるのだが、田中におけるこの「ぶれ」は、看過できないことのように思われる。
第六章では、田中耕太郎の見解とは切り離して「人格」、「人格の完成」という言葉を取り上げ、日本と世界の文脈のなかで、語義的、思想史的意味を精緻に吟味し、ドイツ語のBildung(陶冶・形成)を手がかりに、「神から与えられた像を追求し、それを回復し、神の像へと造りかえられていく」(二三三頁)終末論的なプロセスとして捉えなおすことが提言されている。「人格の完成」に関わる田中の見解を克服して、新たな神学的地平を切り拓いた貢献と言えよう。
第四章では、戦後の八〇年間を、①戦後教育の黎明時代、②教育大衆化の時代、③リベラリズム・国際化の時代、④第二の逆コースの時代、⑤高度デジタル改革時代に区分し、各々の時代のキリスト教学校の課題と闘いを明解に論じている。来し方を振り返り、これからを思い巡らす上で、大変有用にして適切な示唆を与えられる。
戦後八十年という節目の年に、欧米でも、日本でも、右派政党が台頭してくるなかで、本書が出版された意義は大きい。すなわち戦前戦後を貫いて日本のキリスト教学校が直面すべき課題が、「国体思想」にあることを剔抉しつつ、「教育勅語」から「道徳教科化」の流れに抗して、福音に基づく人格教育をこれからも貫徹することの意義を示した好著であり、まことに時宜に適った出版と言える。