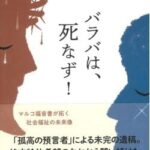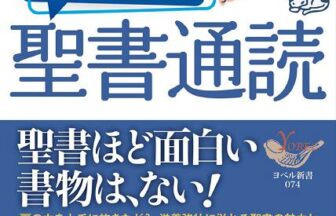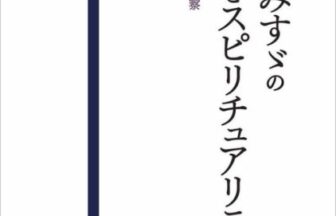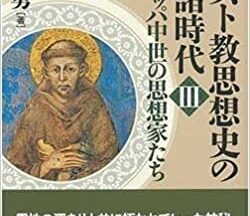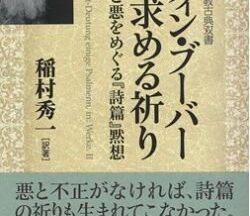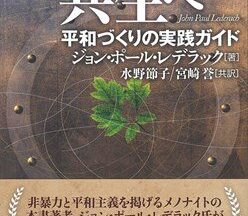絶望のなかの希望!
〈評者〉横山 穰
われ山にむかいて目をあぐ わが助けはいずこよりきたるや わが助けは天地をつくりたまえる主よりきたる(詩編一二一篇)
筆者が一九八二年に米国留学へ旅立つ際、授洗牧師であった著者が色紙に書いた聖句である。「主(神)」は「わが助け」であり、そこに希望がある。
ところで、本書は明日(未来)への遺言である。タイトルの『バラバは、死なず!』は、イエスの十字架上の死と引き換えに命を救われたバラバのことである。彼はローマの圧政に対して反逆し、人殺しをしたゆえに死刑に処せられる運命であった。しかしイエスの死が贖罪となって、自由の身となったのである。「絶望のなかの希望」を象徴するのが、バラバの人生だったのである。著者はバラバの苦難と苦悩に満ちた人生に自分を重ねる。絶望するしかない極貧生活の中で、「人とのつながり」を通して生きる希望を見出したのである。
著者は、本書のなかで「希望というものの現実的根拠」と「共生社会の将来を拓く力としての希望」について明らかにしようとした。希望は、「単なる人間的願望や期待ではなく、神の臨在によって注がれる将来を拓く力」とし、「弱さ、愚かさ、無力さのゆえに苦難を強いられ、絶望に喘ぎながらも約束を信じて希望を失わないこと」は、新たな共生の道を拓くことを可能にするという。
そして、著者は独自の福祉哲学(福祉思想)として、福祉の目的を「人間の絆の創造」の視点から見つめ、人間が尊厳をもって生きるための条件として、共感、連帯、共生、信頼と希望、愛と悲哀を挙げている。以下は、珠玉のことばである。
「福祉はその根底においては、常に人間の尊厳と自由に深くかかわっている……人間疎外や孤立が生じるときに『新しい連帯の基盤は何か』が繰り返し問い直されなければならない」「根本的な福祉実践は追い詰められた人間の苦難や孤独への共感と連帯である。それは『顔の見えない支援』ではなく、疲労と孤独の中に落ち込んだ人の『肩を抱きしめる』抱擁である」「人間福祉の本質は、他者に寄せる信頼と希望である。それば言い尽くしがたい深い哀しみ湛えた『愛』を示す……愛は『哀』に通じ、他者に注ぐひたむきで悲しいまでに切実な愛のかたちを意味する『悲哀』こそが福祉の本質である」「福祉は他者のいのちを『守ること、覆い尽くすこと』である」「福祉実践は、それが誰に対してであれ、徹頭徹尾、人間関係をもって始まり、人間関係をもって終わる……人間関係を構成する基本は『弱さ(ホダシ)を共生の絆(キズナ)とする』条件である。『ホダシ(弱さ)』を分かち合うことは、深い信頼の中で『未来』を育んでいく」
「福祉の実践は、〝自立の追求〟ではなく〝共生の道を拓く〟ことが課題である……共生が自立を拓くのであって、決してその逆ではない。共生なき自立は幻想である……相互支援が社会正義の基盤である……共生なき自立は偏狭と差別をうみだし、人格の尊厳性を踏みにじることになる」
本書は、生きることに絶望した人々が、人とのつながりを通じて、再び生きる希望と勇気を見出す命の書である。