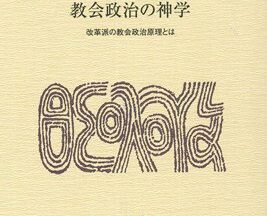ギュイヨン夫人の本格評伝に満腔の共感
〈評者〉西平 直
一七世紀フランスの知らない女性、ジャンヌ・ギュイヨン夫人。なぜ私に話が回ってきたのか。読み始めて驚いた。静寂者の〈内なる道〉を井筒俊彦の哲学に沿って読み解いていた。しかも「無心」や「肚」など、日本の言葉と重ねている。嬉しくなった。「ジャンヌの〈内なる道〉は、たましいの解毒、デトックスです。どのような集団的な抑圧にも押しつぶされたくない。どのようなイデオロギーにも囚われたくない。シンプルに自由でいたい。一人一人のたましいの尊厳を守って共に今日を生き延びたい。そう思う人なら、きっとジャンヌの姿に生き延びるヒントを見出すことでしょう」(はじめに)。
ジャンヌは知的な家庭で育った。聡明な少女が一六歳で結婚させられる。夫は完全な「マザコン」。自信がなく、いつも不機嫌で、癇癪持ち。母親は底意地の悪い人だったというから、その結婚生活は「奴隷のようだった」。
彼女は隠れ家(内なる砦)を求めた。祈ること。しかし神を実感できない。その悩みの中で「外側に求めるな」と教えられた。神を実感できないのは、神を外側に探すからだ。神を探すなら内側に求めよ。こころの中に帰れ。
この「こころ」について、山本氏は、日本語の「肚」を当てると分かりやすいと言う。「頭で神をわかろうとしてはならない。分節メガネを外して、「肚」で神を直観するのだ。言葉のすっかり落ちた、すなわち言語作用がすっかり麻痺した非活性化した根源的な〈沈黙〉の内に、生身で〈ことば〉を直感する。それが〈沈黙の祈り〉だ」。
「言語」ではない。深い〈沈黙の祈り〉。肚で感じ、流れにまかせる。やわらかな神の愛に、身をゆだねてゆく。空っぽの祈り。幸せな無関心。「あらゆる区別が消え去った」静寂者。
しかし夫と姑が、このジャンヌの〈沈黙の祈り〉に気づいてしまう。そして「抵抗としての沈黙」と見て妨害した。ジャンヌの人生にはこうした妨害が何度も繰り返される。〈沈黙の祈り〉は、宗教権力からも国家権力からも、危険視された。そして「スキャンダルなデマ」が流された。ジャンヌには「スキャンダラスな狂女」というレッテルが付きまとっていた。
その彼女が本を書きベストセラーになる(『短く簡単な祈り』)。何の肩書もない在俗の女性が、祈りの指南をして、しかも人気者になる。宗教界は許さなかった。
しかし理解者も現れる。ジャンヌの人生には、その時期ごとに、有難い理解者が登場する。彼女を導き助け、あるいは、彼女を慕う人たち。なかでもフェヌロンとの往復書簡は印象的である。知的な聖職者であった彼が、知性から離れ「体験者」になる。「肚の底で」瞑想する。その過程でジャンヌに問いかけ、ジャンヌが答える。禅が、男性的な気迫と鋭さで切り開いた道を、ジャンヌたちは、やわらかく自然に、ふわりと降りてゆく。
「自分を放ったらかしにしておくこと」。もはや「わたし」ならざる「わたし」。山本氏は〈わたし〉と書く。その〈わたし〉が〈沈黙のコミュニケーション〉の道具となる。しかも山本氏は(井筒哲学を土台に)その「先」も見ている。「分節世界が甦って見えてくる」。この分節世界は「神の自己顕現、自己分節としての世界」である(華厳哲学でいう「事事無礙」である)。
しかし神秘家ではない。ジャンヌは「超常的な体験」には縁がない。彼女によれば「超常」を重んじるのは、むしろ、知性偏重である。傲慢な知性こそが「超常」を騒ぎ立てる。ジャンヌは「静寂者」である。空っぽである。自分は恩寵が流れるための「空の運河」であるという。
どうやらこの女性は「無知で天真爛漫」と形容される人であったようである。山本氏は「天然」とか、「ぶっとんだおバカぶりが、彼女にはあった」という。彼女への最大の賛辞である。幼子のように無垢でいること。
しかも「〈あなた〉」(神)の「愛」に満ちている。山本氏は書いている。「ゼロ・ポイントの無分節態に〈あなた〉を嗅ぎ取るところが、ジャンヌらしい。〈あなた〉の〈愛〉の濃密な香りが芬々としている。むせかえるようだ」。
そうしたコメントまで含めて、まったく共感した。