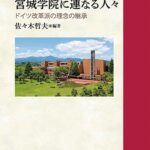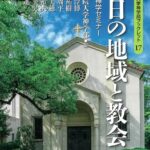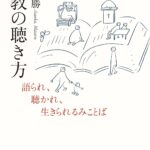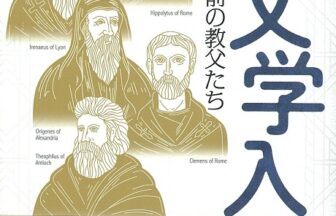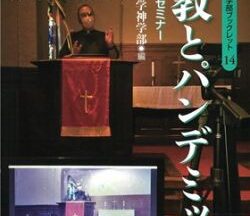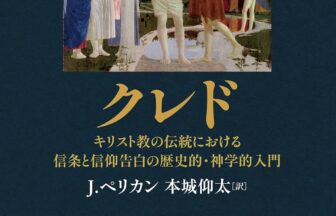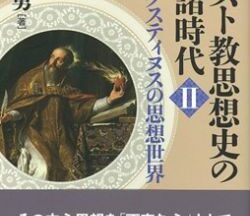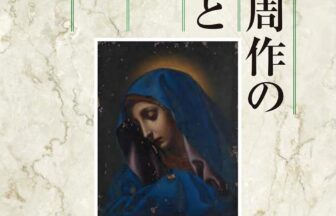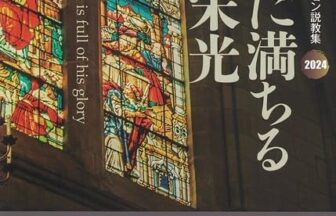創立初期の生徒・卒業生の活動を知る多様な考察
〈評者〉藤野雄大
建学の精神をどのように具体化・実質化していくか。これはキリスト教学校に務めるキリスト者にとって、共通かつ永遠の課題であろう。建学の精神とは、キリスト教学校のよって立つ基盤であるが、学校内外の様々な要因によって、常に有名無実化する危険性を孕んでいる。そのため、建学の精神の空洞化を防ぎ、キリスト教学校としての実質性を保つことが求められる。そして、各校の宗教主任(チャプレン)やキリスト者教員は、その中心的役割を担うことになる。評者自身も、キリスト教学校に務める者の一人として、そのような課題意識を抱いてきた。
そのような折、宮城学院から『宮城学院に連なる人々──ドイツ改革派の理念の継承』(教文館、二〇二五年)が出版された。同書は、同院の現理事長・学院長である佐々木哲夫氏を編著者として、各論を執筆した教職員による共著という形式になっている。同書では、建学の精神を「まさに建物を支える土台のように学校の存立や伸展の要」として捉えており(三頁)、同書の目的は、「『建学の精神』や『スクール・モットー』を視座に創立理念の継承を概観しようと試みる」こととされている(四頁)。
宮城学院は、一八八六年に合衆国ドイツ改革派教会のミッションによって創立され、以来、『神を畏れ、隣人を愛する』をスクール・モットーとして、仙台の地において、今日に至るまで一貫して福音主義キリスト教に基づく学校教育を行い、「人類の福祉と世界の平和に貢献する女性を育成すること」を建学の精神としてきた。この建学の精神に従い、仙台、宮城、そして東北各県を中心に、地域社会に貢献する数多くの人材を輩出してきた。また評者が務める東北学院とは、同じ教派的背景を持ち、共に宮城県仙台市に拠点を置くこともあり、建学以来、深い関係を保ってきた。
同書の内容は多様性に富んでいる。合衆国ドイツ改革派教会との歴史的つながりや、資料室の役割に関する論考に始まり、同院第七回卒業生の顔写真の目歯比率からの人物特定というユニークな考察や、バイブル・ウーマンとしてキリスト教伝道に活躍した同院卒業生の活動紹介、学生の文学活動やキリスト教活動についての考察などが収録されている。いずれも、それぞれの著者独自の関心・視点に基づいており、読み応えのあるものになっている。同書を通して、宮城学院の特に初期の歴史における学生生活や、卒業後の学生たちの活躍の一端を窺うことができる。
一方で、記述の対象がやや初期の歴史に偏っている印象は拭えない。現在まで一四〇年近い歴史を重ねてきた宮城学院の学生たちのライフ・スタイルの変遷や、卒業生の活躍、また建学の精神に基づく地域社会との結びつきや社会貢献などを、より幅広い年代を通して知りたかったというのが、率直な感想である。この点が惜しまれる。
とは言え、同書は、宮城学院関係者および同窓生はもとより、東北地方の諸教会、キリスト教学校に連なる者、さらに全国のキリスト教学校関係者にも貴重な示唆を与えてくれるものである。キリスト教学校における自校史の編纂のあり方を考える上でも一読をお勧めしたい。