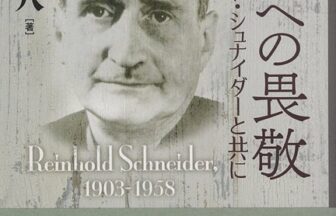真のエキュメニズムを目指して
〈評者〉菊地順
この度、佐々木勝彦氏の優れた訳によって、久しぶりにエーバハルト・ユンゲルの書物が出版された。『説教集4──中断』(佐藤司郎訳、二〇〇二年)が出版されてからほぼ二〇年ぶりである。ユンゲルはカール・バルトが注目した若き神学徒としてそのキャリアを歩み始めた。その注目度は、ユンゲルが若き日にバルトの許を訪れ、語り合った数日後に、バルトがそれまで書き上げた『教会教義学』全巻をユンゲルの許に送り届けたことにもよく示されている(本訳書三四七頁、他)。その後ユンゲルは順調にキャリアを重ね、チューリッヒ大学やチュービンゲン大学で教鞭を執るも、一九九〇年代に入るとその働きはやや精彩を欠き、「大きな書物は途切れて、沈黙が続いた印象」があったが、それを打ち破ったのが一九九八年に出版された本書であった(近藤勝彦「訳者あとがき」『説教集2──霊の現臨』二八五─二八六頁)。奇しくも、日本でもしばらくの間ユンゲルという名は人々の記憶から遠のいていたように思われるが、この度の本訳書の出版は、正にそうした状況を打ち破ることになるであろう。
本書は題名が示すように「義認」の教理を扱ったものである。しかも、キリストの福音の本質として義認を論じている。その背景には、ルター派とローマ・カトリック教会が一九九九年一〇月三一日に「義認の教理に関する共同宣言」に署名する以前に、その内容が公表されたことに端を発する義認をめぐる論争がある。ユンゲルは、そうした両グループの努力を歓迎しながらも、その内容に関してはある失望を禁じ得ず、改めて「妥協」することなく、しかもエキュメニズムを目指して、「信仰のみによる、神なき者の義認に関する《福音主義的基本条項》」を福音の本質として捉え、それを神学的に究明する。というのも、その根底には、福音の本質としての義認に立つときにのみ本当の意味でのエキュメニズムが実現するとの確信があったからである。
本書は全部で六章から成り立っている。しかし、その中でもより重要なのは第三章「義認の出来事──神の義」、第四章「虚偽という罪」、第五章「義とされた罪びと──宗教改革者たちが用いた排他的不変化詞の意味」であろう。第三章では、旧約及びギリシア思想における義の概念を踏まえて新約及び宗教改革者の義の概念が明らかにされ、第四章では、罪の認識の根拠が明らかにされた上で罪と悪の関係が明らかにされ、さらに罪に支配された人間と不信仰としての罪が明らかにされる。そして第五章では、宗教改革者たちが用いた「排他的不変化詞」である〈キリストのみ〉、〈恩恵のみ〉、〈言葉のみ〉、〈信仰のみ〉の四項目が扱われる。この四項目は相互に関連し合いながら義認の本質を厳密に捉え、語るものとして論じられている。そこには言葉を厳密に規定しながら事柄の本質に迫っていくユンゲルの妥協を許さない議論があり、何よりも信仰の恵みに対しての深い確信がある。
本書はユンゲルが渾身の力を込めて義認について論じたもので、深く耳を傾けるに値する書物である。また佐々木氏はすでにユンゲルの大著『世界における神秘としての神』の翻訳に着手されているようであるが、今からその出版が楽しみである。