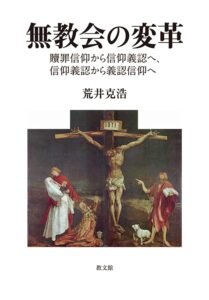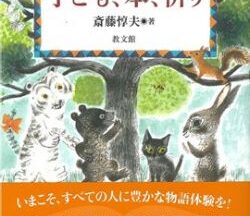キリスト教界への新たな信仰の提言
〈評者〉小林孝吉
著者は、内村鑑三を創始者とした無教会信仰の水脈に連なり、無教会・駒込キリスト聖書集会を主宰し、個人伝道誌『十字架の祈り』を主筆として発行する独立伝道者である。一人の伝道者として、聖書に救済を求める信徒と共に生きること、それは「弱さ」のままに受難の十字架についた人・イエスの苦しみをもとに、信仰者の傷みを人格的に受容しつつ、時代と社会の「強さ」を求める風圧のなかで、無条件の神の愛をありのままの自己が受け入れる、信仰の「正気」、また「多様性」でもあろう。
本書には、二〇二三年無教会全国集会聖書講話で、著者の最初の「義認信仰」の表明となった「私は福音を恥としない」を巻頭に(第一章)、「贖罪信仰から信仰義認へ」(第二章)、「無教会の信仰における断絶と継承」(第三章)から「信仰義認から義認信仰へ」(第九章)と、贖罪信仰との訣別から義認信仰へと至る決定的な信仰変転のドラマが、二〇二一年一一月から二年間(今井館建設移転の前後)に主宰誌に掲載された聖書講話等の文章として収められている。これに新たな書き下ろしとして、「『贖罪信仰』の底を割ってその先へ進む」(第一〇章)を加えて、著者における「無教会の変革」への問題提起が実験的に描きだされている。そこには、「十字架につけられたままのキリスト」=「罪となった神」と共に生きる、一伝道者の姿が見えてくるであろう。その姿は、信仰者の神証言をたどった最相葉月『証し』において、「信仰の新たな旅立ち」として注目された。この贖罪信仰から義認信仰への旅路は、青野太潮氏の十字架・パウロ理解、大貫隆氏の贖罪信仰の起源と変容などの新約学の研究に支えられ、作家椎名麟三やシモーヌ・ヴェイユへの信仰義認的な共感も底流する。ここでは著者の師・高橋三郎の絶筆「パウロの限界」も、「贖罪信仰の限界」としてとらえ直されているのだ。
著者は、総論となる第一章のなかで、人は十字架の贖罪信仰ではなく、神の愛によって無条件に救われ、義とされ信仰が起こされる(=義認信仰)といい、次のように語る。「救いとは、弱さから強さに変わることではありません。愚かで弱い者が、愚かなまま・弱いままで、無条件に神に受容され救われることなのです。……真の復活とは、愚かなまま・弱いままで強められることなのであります」。本書には「イエス・キリストの真実」(聖書協会共同訳)=「神の賜物」としての「ピスティス」(信仰)が全章を貫き流れている。
本書は、内村鑑三の贖罪信仰の刻まれた無教会への、広くはキリスト教界へも、大きな課題の提起となるであろう。その帰趨は、無教会にとっては揺るがせにできない関心事である。そこから「万人救済論」への一条の希望を見ることができるであろうか。それは、私たち自身に問われているのだ。著者は、「あとがき」に、こう記している。「私が本書で書いてきたことは『全ての人はすでに救われている』ということである。一人残らずである。……勝利者キリスト。私はこの言葉を廃棄しようと思う。そして次の言葉を語りたい。共なる神──インマヌエル」と。
インマヌエルなる神の愛の声は、すべての人が、希望とともに歩むべく、いつも呼びかけてやまない。本書には、その呼び声と響き合う著者の信仰が木霊している──。