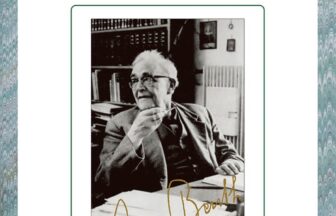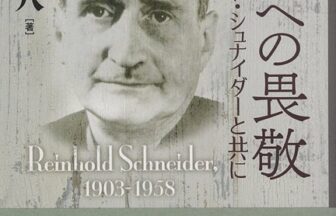こどもらしさを喜ぶ神学へ!
〈評者〉久保木聡
「あなた、どうしてこどもを静かにさせられないの! ちゃんと子育てしなさい!」
一喝の声が教会堂に集う親子に突き刺さる。震える親子は教会に自分たちの居場所を見出せなくなる。やがてこの若い親子は教会に足を向けなくなる。
一喝した人も悪気があったわけではない。静寂で秩序だった教会を目指していたのだろう。ただ私自身の限られた出会いではあるけれど、こうしたケースは、一喝した本人が常日頃から自分の中のこどもらしさを抑えつけ、自身のこども性を開示することが苦手なことが多いように思う。
本書はまず児童虐待の問題に焦点をあてる。虐待する親が非難されることが多いが、実のところ、その親自身も虐待の被害者として育ってきたケースも多い(もちろん、だからといって虐待をしていいわけではない)。自らのこどもらしさを健全に表現することができず、抑えつけ、わが子のこどもらしさを許容できなくなるがゆえに虐待行為に至ってしまう。
われわれはともすると、大人になっても自分の中にある、こどもらしさ、こども性を見ないようにしがちであるし、軽んじやすいのかもしれない。本書の特徴は徹頭徹尾、こどもであることに着目し、こどもであることを重要視しようとする。
こどもは虐待を受けやすい弱者であり、無力な存在である。そんな中で著者は、「神がその無能さ・無力さ・受苦の中でご自身を真の神として啓示されると主張するバルト、ボンヘッファー、モルトマンの見解を紹介し、続けて神が男性性と女性性、もしくは父性と母性を含んでいる両性的な方でありながら、同時に性を超越した方であると主張するモルトマン、リューサー、ラッセルの見解を紹介し」(八二頁)ている。そして「女性の神学を代弁する神学者たちは、こどもたちの解放に対しても十分な関心を傾けているが故に、こどもたちの解放に寄与する神学体系を実際に立てているだろうか。」(八二‐八三頁)と問う。こうしてフェミニズムの神学者たちと対話しながら、『こどもの神学』を打ち立てようとする。
第3章ではイエスの中にみるこども性を扱い、第4章ではこども性から着目した神観について、第5章では神のかたちとこどもについて扱う。第6章ではこども性に基づいた終末理解が語られ、最終章の第7章ではこどもらしい霊性について扱われる。つまり、この“こどもらしさ”を大切にするならどのような信仰生活が開かれていくかを描く。
評者は本書の訳者である朴昌洙氏を超教派のとある集会にて説教者としてお招きしたことがある。神学的に聡明でとても知的に語られる側面とともに、本書がこどもの特徴として語る純真さ、素朴さ、素直さ、謙遜さ、遊び心を併せ持った人格であるとともに、かつ情熱的な説教を語られることにとても驚かされた。朴氏が恩師である著者の『組織神学入門』に続いて本書を訳されたことに妙に納得している。本書『こどもの神学』は朴氏本人にとっての生き方そのものとなっているようだ。本書を読むことで、さらにこどもらしさを受け入れ、教会が弱さの中にある“こどもたち”をもっと受け入れていけることを願ってやまない。