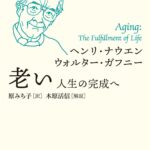原始キリスト教の力動的な伝播を誠実に読み解く
〈評者〉田中健三
本書は「贖罪信仰」をテーマに、Ⅰ章からⅤ章までは原始キリスト教においてそれがいつ発生し、どのような変遷を経たかということを一次文献に依拠しながら考察したものであり、Ⅵ章ではそれまでの章の結論を背景にしつつ、現在の「贖罪信仰」をめぐる議論に参戦している。
原始キリスト教がエルサレムを出発点にしたとしても、すでに早い段階から多様性を持っていたことは、新約聖書が示すところであり、ゲルト・タイセンはキリスト信徒第二世代において大きく四つの系統が見られると述べる(Die Religion der ersten Christen, 2000年)。すなわち「ユダヤ的キリスト教」「共観福音書的キリスト教」「パウロ的キリスト教」「ヨハネ的キリスト教」である。しかもそれらは単に並存していたのみならず、相互に影響し合っていたのだが、その相互作用について時間軸を含めて明確に立証することは必ずしも容易ではなく、タイセンもそこまで踏み込んだ記述はしていない。
その点で本書は、上記の4系統の相互関係を時間軸も含めて、「贖罪信仰」という観点からではあるが、提示している点が出色である。本書のような構想の論証には精緻な分析が求められ、その点で著者は自らの論証が必ずしも十分とは言えないことを良心的に記している。それにも関わらず、一次文献に依拠しかつ先行研究を活用し、説得力のある刺激的な内容となっている。
本書は復活信仰直後からだいたい2世紀末くらいまでの「贖罪信仰」の過程を提示する。「贖罪信仰」は原始エルサレム教会のペトロが指導者の時代に前面に出て来るのだが、次の指導者である主の兄弟ヤコブ時代になると贖罪論は後景に退き、モーセ律法遵守の救済論が前面に現れ、その後それは北トランス・ヨルダン地方からシリアへと伝播していった。一方「教理」化した「贖罪信仰」が西方キリスト教会に変容しつつ受容されていった。
Ⅰ章では、著者の師でもあるフェルディナント・ハーン著Christologische Hoheitstitel. Ihre Geschichte im frühen Christentum(1966年第3版刊行)の論述を活用しながら、原始エルサレム教会において、「イエスの受難の必然性」への問いがなされ、それに続いて「イエスの受難の自分たちにとっての意味」が探求され、彼らは「人の子」イエスの再臨待望を保持することとなるのだが、そこには未だ「贖罪信仰」はなく、その後ペトロが大いに関わり、新約聖書第一コリント書15章3b-5節に明示されている「贖罪信仰」が形成されるという過程が示されている。
Ⅱ章では、主の兄弟ヤコブによる律法遵守(但し動物供犠は除く)の救済論が形成されるが、そこには第一コリント15章のような贖罪論は見られない。このペトロとヤコブに救済論の分岐点がある。そしてヤコブのユダヤ主義キリスト教は北トランス・ヨルダンに受容されていく。キリスト教教父の一次文献を取り上げ、そこに見られるユダヤ主義を明示する箇所は、著者ならではの箇所であると言えよう。著者はその教父たちの救済論とヤコブのそれとの繋がりを見る(著者による仮説1)。
Ⅲ章では、ユダヤ戦争によってエルサレムから脱出したキリスト者たちに関連して、その脱出にはマルコ福音書14章58節のイエスの神殿倒壊予言が、根拠付けとなっているという仮説2を提示する。またここでも北トランス・ヨルダンからシリアにかけて展開した2世紀のユダヤ主義キリスト教を一次文献によって示している。
Ⅳ章では、エルサレム神殿崩壊から1世紀末までのシリアにおける異なる流れとして、マタイ福音書とヨハネ福音書を取り上げる。さらに洗礼と沐浴儀礼を強化していくユダヤ主義キリスト教の証言としてマンダ教その他のグループを示し、2世紀のユダヤ主義キリスト教の中での多様性を示している。
Ⅴ章はそれまでのまとめとなっている。
著者は、パウロを代表とする西方キリスト教の贖罪信仰が不在である東方のキリスト教の証言を提示しており、その際に著者がこれまで従事して公にしてきた教父その他の諸文書についての研究業績が十分に活かされている。東方に伝播したキリスト教がヤコブの後継者と自認していたことは、古代シリアの諸教会などの典礼において、ヤコブと関連付けられた奉献文が残されていることからも明らかであるが、ヤコブと東方教会の歴史的継続性が明確なものであることを本書では示している。著者が述べるように東方キリスト教への視点が西洋や日本では今までなおざりにされており、それは今後さらなる研究発表が期待される分野である。
さてⅥ章では現在日本において、キリスト教内外から「贖罪信仰」をめぐってなされている議論全体を整理しつつ、著者の考えを述べている。
著者は2008年公刊の『イエスの時』において、キリスト教の「贖罪信仰」の内容が今や不明瞭になっていることを指摘しているが、その後2011年3月11の東北大震災などを契機として高橋哲哉がくりひろげたキリスト教贖罪論批判とそれをめぐる諸氏の意見などに対して、ここで新たに見解を述べている。著者は高橋の指摘する「犠牲の論理」への批判に共感を示しつつ、関東大震災時に内村鑑三が述べた贖罪論についての高橋の理解を否定している。被災者自身が罪の主体であると内村が語っているという高橋の理解には反対し、むしろ被災者の無罪性を内村は前提としている、と述べる。「キリスト教の贖罪論は、犠牲者(供犠)の無罪性をほとんど無意識の内に前提してしまう」(本書226頁)という著者の指摘は大変興味深い。
著者はⅠ~Ⅵの研究から帰結されるであろう、贖罪論の相対化の土台に立って、現代における贖罪論に関する問題性を自覚し、その上で高橋の論理に批判も加えている。
しかし高橋哲哉の問題点は、より根源的なものであるように評者には思われる。
テキスト解釈において、語り手と聞き手の関係性を重視すべきであるという文学理論は、聖書本文についても適用されてきている。評者の考えでは、高橋哲哉らの贖罪論批判にはこの聞き手の存在が欠落した論理のみを扱っていることに問題がある。例えば内村の発言には、関東大震災によって絶望し、神の存在を疑う具体的〇〇さん、△△さんという他者が確実に存在していることを無視すれば、内村批判は空虚な揚げ足取りに陥るだけである。それは原始エルサレム教会における「贖罪信仰」そしてパウロの「贖罪信仰」についても言える。
柄谷行人は『探求Ⅰ』(講談社、1986年)において、モノローグと対話を区別し、「対話とは『命がけの飛躍』である」と述べ、語り手と聞き手の間における緊張をはらんだ力動的関係性に着目し、言語における他者性の重要性を指し示した。
原始キリスト教の贖罪論もパウロの贖罪論も内村の言説も、元来はそのような「命がけの飛躍」であったはずであり、その他者性を無視した普遍的論理などは、花をいけてない花瓶と同じである。贖罪論を論ずる際にこの視点が欠けていることが多く、エマニュエル・レヴィナスの述べる「普遍的構造の彼方に、個人と個人の、人間と人間の関係の重要性を証し立て、匿名的な原則の背後に他の人間の顔を見ること」(「原則と顔」『困難な自由』内田樹訳、国文社、2008年所収、270頁)が不可欠であろう。
著者大貫は、自己完結したモノローグとなってしまった贖罪論を相手にしており、それ自体は正当に批判をしている。しかしキリスト教贖罪論は元来モノローグではなく対話であった点に著者は触れかかっている箇所があるにはあるが、十全とは言えない。その点で今までの一連の諸氏の発言を必ずしも適切に交通整理しているとは評者には思えない。
とは言え、本書は原始キリスト教の力動的な伝播を知ることができるものであり、Ⅵ章における日本の諸研究者の紹介(評者の博士論文も含めてくださった)と批判からは、著者の誠実な研究姿勢が感じられる。