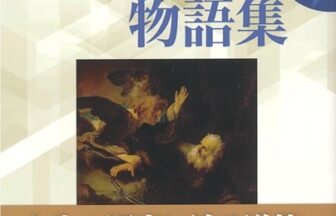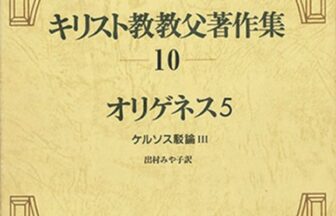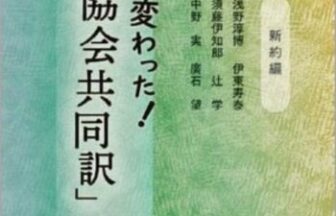新約テキストの新たな解釈への道標
〈評者〉吉田 新
本書の著者である住谷眞氏は牧師として教会に仕える傍ら、フルートを奏で、歌人として短歌を詠み、ダンテの神曲についての著作も公にしている。様々な顔を持ち合わせている氏であるが、聖書学者として新約聖書と真摯に向き合い続けることが、多芸多才な氏の活動の根底にあるように思える。
本書は住谷氏が先に上梓した論文集『烈しく攻める者がこれを奪う─新約学・歴史神学論集』一麦出版社(二〇一四年)の続編という性格をもっており、二〇一五年以降に発表した研究論文、講演録の集成である。主に新約テキストの新しい解釈と翻訳を提案している。
評者は翻訳者、及び編集委員の一人として、住谷氏と共に聖書協会共同訳の事業に携わった。個人訳とは異なり、日本聖書協会が発行する聖書翻訳は共同作業である。それゆえ、訳文に関して持論を押し通すのではなく、他の翻訳者、編集者と共に訳文を練っていくことが重んじられる。温厚かつ協調性を尊ぶ住谷氏はこの事業には適任であった。氏は自身が提案する訳文に対する修正意見が出された際、それらの意見を取り込みながら皆が納得いく訳文へと見事に仕上げていった。時に氏は斬新な訳文を提案し、自説を展開することもあった。学識に支えられた氏の訳案はとても説得力があり、何度もハッとさせられたことを覚えている。本書を読むと、その時の驚きと感動が呼び起こされた。
例えば、本書の「ヤコブの手紙3・6aの新しい解釈と翻訳をめぐって」では、「そして舌は火、悪の世界である。それはわたしたちの肢体のうちに置かれている」という従来の翻訳とは異なり、「そして舌は火である。わたしたちは肢体にあって不義の世界となっている」という新たな訳案を打ち出している。ヤコブの手紙全体の論理の流れを鑑みつつ、この訳文の意義を詳細に説いている。さらに「ルカによる福音書2・49の新しい解釈と翻訳をめぐって」では、「わたしの父のものである人々の中(間)にいることになる」という訳の妥当性が解説される。この訳案に関して、ルカ福音書の文脈、特徴的な用語の分析、そして同福音書の対応関係等から説明される。さらに、「イエスは『仕事』(ビジネス)や『家』にいるべきであるよりも、まず『人々の間に』いなければならない。それは、その在り方が人間の条件であるからである」(五二頁)と説かれ、ハンナ・アーレントの言説が紹介されている。ごく短い訳文の提案であるが、ルカ福音書全体、そして、イエスとは何者であったのかという大きな問いから考察されていることが分かる。氏のこれまでの学究の深さと幅の広さを感じさせる。他にもコリントの信徒への手紙二11・21、ヨハネによる福音書20・17 ab、ヨハネの黙示録22・2の新しい解釈と翻訳に関する考察においても、そのことを感じさせる。
本書において住谷氏が論じる解釈と翻訳案は、それまでの通説を覆すような創見に富んでいる。いずれも説得的で納得させられることが多い。本書を手にする者は、氏の提案を踏まえて、再度、原典と向かい合うことを促されるはずだ。本書は読者一人一人が、新約テキストを新たに読み直すための道標となる。従来の学説に立脚するこれまでの研究を取り上げ、批判的に向かい合う箇所で、先行研究に関する住谷氏の見解をもう少し詳しく聴きたいと思った。各論文が発表された際に字数の制約があったのかもしれないが、独自の見解は、従来の学説と対決的に突き合わせることでより説得力を持ち、読者を深い考究へと導けるはずである。
本書では今後のさらなる研究も期待させる箇所も多々ある。たとえば「ヨハネによる福音書1・15の新しい解釈と翻訳をめぐって」では、同書の1・14−18が編集者による加筆挿入であると判断されているが、その理由は詳しく論じられていない。住谷氏はあとがきで、本書をもって「私の学問的営為の区切りとしたいと考えております」と述べているが、その区切りをつけるのはまだ早いのではないかと評者は考えている。通説の壁を打ち破る氏のさらなる学問的営為を心から待ちたい。そう強く思わせる良書である。