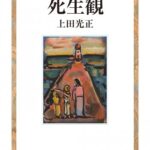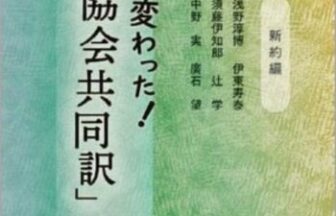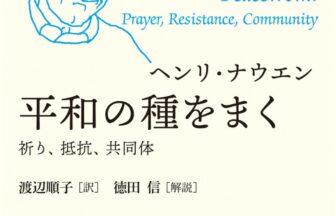知られざる歴史をたどり聖書翻訳のあり方を考える
〈評者〉月本昭男
本書の表題に意外な感じを抱く人は少なくないだろう。モンゴルと聞けば、大草原を思い浮かべ、チンギスハンや大相撲の力士の名が口をついて出ても、キリスト教との関連に思いをはせる人はまずいない。本書をひもとく者は、それゆえ、モンゴルとキリスト教との深い関わりに、モンゴル語聖書翻訳の歴史に、いたく驚かされるにちがいない。評者もその一人であった。
もっとも、7世紀にネストリウス派が景教として唐に伝えられたことを思えば、大帝国成立以前のモンゴルにキリスト教が伝わっていても不思議ではない。本書第一章「モンゴルとキリスト教──近代以前」(芝山豊)は、そのようなモンゴルとキリスト教との関係史を詳しくあとづけ、モンゴル大帝国の成立さえもがキリスト教と無関係ではなかったことを具体的に教えてくれる。
第二章以下には、表題に示された、聖書のモンゴル語翻訳をめぐる10の諸論考が連なり、そこに池澤夏樹「世界文学としての聖書と翻訳」、山浦玄嗣「聖書のケセン語訳から見えてきた日本の翻訳文化」が、さらに仏典のモンゴル語翻訳論(金岡秀郎)、フランシスコ会邦訳聖書をめぐる報告(小高毅)が添えられる。
新約全書がカルムイク語と狭義のモンゴル語とに翻訳され、刊行されたのは1827年、旧約全書のモンゴル語訳出版は1840年であった。日本における最初の『新約全書』(1880年)と『旧約全書』(1887年)に半世紀ほども先立つ。その後も、聖書のモンゴル語翻訳(改訳)事業は続けられた。それは西欧諸国によるキリスト教宣教活動と連動していたが、本書は聖書翻訳に携わったモンゴル人たちを紹介することも忘れない(第六章)。1924年にはじまる「社会主義」時代、モンゴルにおける宣教活動は困難をきわめた。1990年の「民主化」以降は、ふたたびキリスト教宣教活動は活発化し、あらたな聖書翻訳も様々に試みられている。いまや、モンゴルにおけるキリスト教徒は10万人前後、人口比では、日本の1パーセントをしのぎ、3~4パーセントにおよぶという(95頁)。
本書は、しかし、モンゴルにおける聖書翻訳史を紹介するにとどまらない。独自の自然風土と生活様式と文化伝統をもつモンゴル社会における聖書翻訳の可能性が、その困難さとともに、多角的に論じられている。そこには、たとえば聖書が語る「神」は、あるいはイエスが教えた「愛」は、モンゴル語でどのように表現すべきか、といった具体的な課題が横たわる。それは漢訳、邦訳、韓訳聖書が経験した問題と重なる。さらに、信仰の規範となる聖書の翻訳は、訳語の問題とは別に、基本的な翻訳理念と無関係ではありえない。聖書の翻訳とも深く関わる翻訳論上の課題がそこに浮かび上がる。本書の副題が「翻訳文化論の新たな地平へ」とされた理由もそこにあるだろう。
本書はモンゴル語聖書をめぐる学際的な共同研究の成果であり、モンゴル人研究者もこれに加わる。研究会を重ね、本書を編まれた方々への敬意と感謝をもって拙い紹介とさせていただこう。
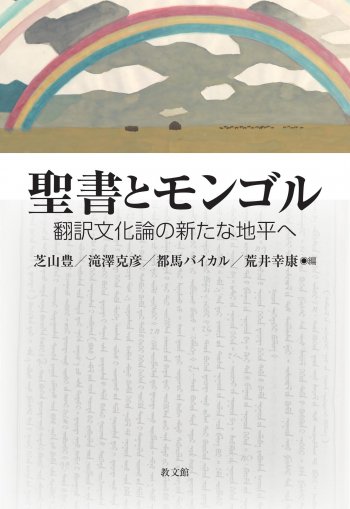
聖書とモンゴル
翻訳文化論の新たな地平へ
芝山豊、滝澤克彦、都馬バイカル、荒井幸康編
A5判・342頁・定価3520円・教文館
教文館AmazonBIBLE HOUSE書店一覧

月本昭男
つきもと・あきお=立教大学・上智大学名誉教授、古代オリエント博物館館長